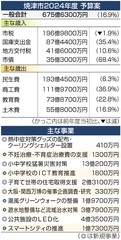なくなる学校。地域にできることは?⑥ しずしんニュースキュレーターと読者の意見【賛否万論】
学校がなくなると地域は廃れるのか、学校がなくなっても地域が廃れないようにするにはどうしたらいいのかをテーマに取り上げてきました。4月5日付本紙で報じましたが、少子化の影響で過去10年間に県内の公立小中学校50校が中山間地を中心に閉校しており、今後、市街地も含めて学校統廃合の動きがさらに進む見通しです。今週もしずしんニュースキュレーターや読者の意見を紹介します。保護者の意見を尊重すべきだという考えや小規模校の良さを生かすべきだという声が寄せられています。
中山間地の廃校に不登校者向け高校
キュレーター 教員おにいさん(静岡市)

中山間地は、豊かな自然や、親密な地域コミュ二ティーに引き継がれる伝統など、教育資源が豊富です。よって、私は、不登校に対応する高校の本校を中山間地の廃校跡地などに設置して、その分校を都市部に設置するという構想を模索しています。まずは自宅から近い都市部の分校で、教員と生徒と個別の教育活動からスタートして、徐々に人と触れ合う感覚を取り戻していきます。
本校では、木々の香りや鳥のさえずりのなかでの体験活動や、地域の祭事に参加して習俗を学ぶなど、地域の特性を生かした集団教育を行っていきます。1年間を通じて多彩な教育活動を展開することで、生徒個々の状況に応じた出席が可能になります。分校は複数設置し、広範に生徒募集すれば経営効率と教育多様性を同時に追求できるようになります。
中山間地には、こうした教育展開の可能性が秘められています。
行政の統廃合計画再検討して
読者 酒井政男さん(静岡市葵区) 今、静岡市の中山間地で学校統廃合が進められています。学校がなくなることは、子育て世帯の転居を余儀なくさせるとともに、その後、JAや郵便局なども統廃合となり、働く場の喪失はさらなる転出を促進させます。
国、文部科学省による財政削減策として「学校統廃合」が進められているのであり、子どもたちの教育環境を考えてではないということです。こうした現状を踏まえ、学校統廃合問題を考えてみたいと思います。
1973年文部省「Uターン」通達、「小規模校には教職員と児童・生徒との人間関係の触れ合いや個別指導の面で小規模校としての教育上の利点も考えられる」と小規模校として存置し充実する方が望ましい場合もあるとしていました。文科省となっても「豪雪地帯・遠距離・学校がコミュニティーの中核の場合、小規模校を存続した方がいい」としていました。
しかし、第2次安倍政権は2012年「平成の学制大改革・小中一貫校」が新たな「学校種」となり、15年の経済財政諮問会議は経済財政一体化推進委員会改革工程表で「学校の適正規模」が教育の筆頭ページとなります。
その後、文科省は一つの学年で学級を編成できない小中学校の統廃合の適否を速やかに検討、スクールバス通学はおおむね1時間以内とする「学校統廃合の手引き」に改正したのです。また、総務省も14年から地方創生で公共施設等総合管理計画を16年度までの作成を全自治体に求め、期限付きの交付金により老朽校舎の改修財源に悩む自治体が飛びつくように仕向けたのです。
今、都市部において統廃合による学校用地を都市再開発区域とする動きが目立つようになりました。そのため、市街地の学校統廃合も始まっています。静岡市街地でも青葉小と城内小、一番町小と三番町小の統合に続き、田町、駒形2小学校と安倍川中の3校の小中一貫校が子ども、保護者や地域の合意形成もないまま進められようとしています(市教委は「合意形成の途上」と説明)。
子ども支援対策により移住する世帯が増える自治体が注目されています。中山間地で学校の果たす役割は大きいことは、昨年度まで水見色小があった水見色地域の人口減少率が、他の地域と比較し小さいことからも明らかです。
水見色地域は小学校もある「村」としての意識を地域の人々が持つことで人口減少にストップをかけてきたとも言えます。今回の水見色小廃校は今後の地域へ与える影響は大きなものがあり、静岡市の学校統廃合計画への批判は避けられません。コンパクトシティ計画と学校統廃合計画について再検討を求めます。
小中一貫ならではの豊かな生活
キュレーター 長沢弘子さん(浜松市中央区)

さて、浜松市では2010~12年に引佐地区の3小学校と1中学校、14年には庄内地区の2小学校と1中学校、17年には中央地区の2小学校と1中学校が統廃合され、小中一貫校として開校された。それぞれ事情は異なっていたようだが、「地域の子どもたちが通う学校をなくすわけにいかない」という地域の強い思いがあり、小中一貫校という形で開校したと聞いている。私も引佐地区の学校へ開校間もないころ講座で伺ったことがあったが、立派な体格の中学3年生の男子や体育会系の中学校教員が小さな小学1年生に優しく声をかけながら活動する様子はとても楽しそうでほほ笑ましく、生徒と教員ともに豊かな学校生活を送っているなあと感じた。
学校は、地域の核であり住民のアイデンティティー、ハード、ソフト両面で非常に重要な存在である。とはいえ、まずは子どもたちが通う学校なのだから、小規模校だからこそのメリットとか、大規模校の優位性とか、小中一貫校の良さとか、多分、それぞれにさまざまなことはあるだろうが、どんな選択であっても子どもたちが楽しく幸せを感じられる居場所になってほしいと願っている。いずれにせよ、何年かしたら子どもたちは巣立っていく、それはとても幸福なことだ。
バス通学拡大し登校支援を
読者 座光寺明さん(磐田市) 私の地域でも、2年後に三つの小学校と一つの中学校が統合され、小中一貫校になる予定です。現在、地域住民にとって一番の不安ごとが登校方法です。4キロを超える家が地区内にあれば、全員バス通学になります。しかし、4キロ未満の地区は徒歩通学となります。住んでいる地区が許可されれば、自分の家より近い家でもバス通園になるという子どもに理解しにくい定義になります。
本園では、園外保育を取り入れていますが、年長児の徒歩は最大3キロと考えています。途中2回の休憩を取り、糖分、塩分補給も必須です。これを考えると、小学校低学年がランドセルを背負って、荷物を持って4キロ近く歩くのはかなりの負担だと思います。雨の日や、近年の異常とも思える暑さを考えると危険すら感じます。
ちなみに現時点では、中学生は2.5キロ以上の距離があれば自転車通学を許可されています。それを考えると小学生は2.5キロ以上でバス通学許可とするべきと思います。
いずれにしても新しい学校に移行することへの不安に対して懇切丁寧に対応する行政の姿勢を望みます。
子どもの気持ちを尊重
読者 読者 澄んだ青空さん(焼津市) 73歳 学校の統廃合について関係者に調査や聞き取りをしていないので、その声は分からないが、次の観点からも考えることが大事かと思う。
①「対象となる地域の子ども」の気持ちや意見を尊重し、聞くことがまずは大事である。どうしてもこのような問題は大人や組織からの観点や意見がメインになってしまうからである。
②学校の統廃合による子どもの「心の統廃合」を利点面から考えることも大事である。それぞれの文化と歴史と生活様式のある地域に住み、その学校に学ぶ子どもは統廃合により、他地域のそれを肌で感じ学ぶことができ、広がった新たな学び場の場になる。
こうした学校の統廃合の課題は少子化等の進行によって各地で起こってくる。地域の中の学校や家庭の中の学校の在り方はまだその波が押し寄せてない地域でも、先を見て常にみんなで考え議論し整理していくことが大事ではないかと思う。日本をこれから背負っていく子どもの育成のためにも。
■次回も同じテーマでしずしんニュースキュレーターや読者の意見を紹介します
キュレーター 「しずしんニュースキュレーター」は、新聞記事や時事問題の“ご意見番”として、静岡新聞の記者が推薦した地域のインフルエンサーです。毎回それぞれの立場や背景を生かしたユニークな視点から多様な意見を寄せてもらいます。






 いい茶
いい茶