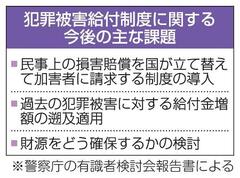クリスマスの銀座を照らす柔らかな「ねぶた」の光 女性初のねぶた師・北村麻子さんが挑む新たな伝統工芸のカタチ
青森の伝統工芸「ねぶた」で作られた巨大なクリスマス・イルミネーションが東京・銀座のデパートの吹き抜けに現れた。クマやトナカイ、リボンで飾られたプレゼントの箱、モミの葉など、大小さまざまなねぶたが柔らかな、優しい光を放っている。制作したのは、青森市に住む女性初のねぶた師、北村麻子(きたむら・あさこ)さん(40)。2021年も同じ場所にクリスマスの装飾ねぶたを展開し、今秋「日本空間デザイン賞2022」の金賞を受賞した。
「多くの買い物客でにぎわう銀座で、ねぶたを見てもらうことに意味があると感じた。これまで全く興味がなかった人たち、特に若い女性から大きな反響があることがうれしい」。ねぶたの新たな可能性に、北村さんを突き動かした背景には、新型コロナウイルス禍や後継者不足など、ねぶたを巡る厳しい環境があった。(共同通信=内田朋子)
ねぶた名人、父・隆さんの背中を追って
「青森ねぶた祭」は東北三大祭りの一つで、毎年8月2日から7日に青森市で開催。200万人以上の観光客が訪れ、国の重要無形民俗文化財にも指定されている。
「ねぶた祭りの最大の魅力は、開かれた公共空間で誰でも自由に参加できるところ。美術館のように入場料を払わなくても、ねぶたの迫力と光の美しさを楽しむことができる」と北村さん。父親はねぶた師の6代目名人、北村隆(きたむら・たかし)さん(74)だ。「ねぶた師は青森では特別な存在。メディアにも登場する父は自慢であり、誇りだった」という。
ねぶたは大量の針金で大きな立体像を紙で作り、槌やのこぎりも使って仕上げる。高所作業も多く、体力が必要なねぶた師は「男の職業」という固定観念が地元にもあった。幼い頃から身近に接してきた北村さんだが、ねぶた師を目指そうとは思わなかった。
高校を卒業後、別の仕事をしていた時、長引く不況の影響で、ねぶたの制作をサポートする企業・団体が減ってきたという。「もし、父がやめてしまったら、貴重な技術を継承する人がいなくなってしまう」と強い危機感が芽生えた。07年、隆さんが制作し、最高賞のねぶた大賞に輝いた「聖人 聖徳太子」に感銘を受け、同じ道を進むことを決意。隆さんに弟子入りした。
「若い頃から、私には『こうなりたい』という夢がなく、大きなコンプレックスだった。だからこそ、ねぶた師になる決意をした時、この気持ちを絶対、手放してはだめだと思った」。厳しい修業を経て、12年、青森市民ねぶた実行委員会から作品を依頼され、デビュー。そのときの「琢鹿(たくろく)の戦い」が優秀制作者賞を受賞し、注目を浴びるようになった。
「女性初のねぶた師」と後継者難
2017年には「紅葉狩」でねぶた大賞も獲得。「初の女性ねぶた師」としてメディアで紹介されることが多くなった。「実力が伴わなければ、嫌悪感があったかもしれないが、それなりの作品を残してきたという自負がある。土台があって注目されることは、ねぶたにとってもプラスと思う」
その上で、30代以降は男女の体力差をはっきり認識するようになったという。「それまでは、男に負けたくないという気持ちが勝っていたが、いまは自分の体に負担をかけすぎないよう、大工仕事などは助けてもらおうと割り切れるようになった。そうしないと重労働でもあるねぶた師の女性後継者は育たない」と語る。
北村さんによると、プロのねぶた師は13人しかいないという。70代の隆さんを筆頭に、30代まで各年代に数人ずついるが、20代は皆無。若手の少なさは深刻な問題だ。「10年ぐらい修業しないと、大型ねぶたは作れない。ニュースなどで取り上げられるので、憧れて門を叩く人は多いが、すぐにやめてしまう。才能が重視される世界でもあり、大きな賞を取ったり、活動をサポートしてくれる人に出会えたりするかどうかの運にも左右される。『家族を養えない』と経済的な理由でやめてしまう男性もいる。文化の伝承には、国の支援が必要だと思う」と訴える。「ねぶたは伝統工芸だけれども、歌舞伎などと違い、世襲制ではない。才能と努力があれば、誰にでも開かれた世界であることをもっと知ってもらいたい」
コロナ禍と新たな挑戦
コロナ禍により2020、21年と2年連続、青森ねぶた祭は中止となった。「戦時中に中止になったとは聞いていたが、まさか、自分が生きている間にこんなことが起きるとは思っていなかった。当たり前のようにあったねぶた祭りがなくなったことは、青森の人々にとってすさまじい喪失感があったのではないか」
今年は規模を縮小して3年ぶりに開催されたが、コロナ禍の試練を経験したことで、祭りに対する意識が変わったという。「『ねぶたはこうあるべき』という思い込みから解放され、自分の素直な気持ちを最大限、表現できるようになった。人の心を明るくするような美しいものを作っていきたい。それまでは力強さを前面に出していたが、人を包み込むような作品にしたいと思った」と話す。テーマは「琉球開闢(かいびゃく)神話」。沖縄返還50周年にウクライナ侵攻などの戦争も重ね合わせ、平和のメッセージを込めた。
世界中にねぶたの魅力を
銀座でのねぶた装飾に当初は、周辺関係者から不安視する声も出ていたという。しかし、北村さんは「伝統工芸だからといって、いつも同じ形に縛られてはいけない。時代に合わせ、生まれ変わっていく勇気が必要」と話す。同じ青森の伝統工芸、南部鉄器にも触発された。「旧来の黒色ではなく、カラフルな色の作品も作られ、若い人の関心を集めている。ねぶたも現代のニーズを捉え、新しい空気を吸収すれば、表現の幅を広げることができる。そのことを、東京での仕事で実感できた。青森から世界中にねぶたの素晴らしさを広めたい」と目を輝かせた。
「『青森ねぶた』クリスマス」を企画した銀座「松屋」の担当者、柴田亨一郎さんは「北村さんには人を引きつける力があり、みんなが応援したいという気持ちになる。今後も地方創生のために、あっと驚く作品を一緒に企画してみたい」と期待する。北村さんの挑戦はこれからも続きそうだ。










 いい茶
いい茶