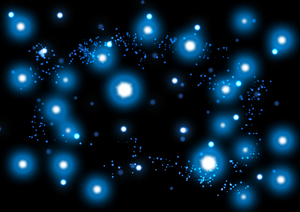咬まれたら怖いマダニ
最近、マダニへの注意喚起を見る機会が多くなったと思いませんか? マダニに咬まれたことが原因でおこる感染症の重症化や、死亡する事例が増えているそうなんです。今回は、この時期注意が必要なマダニ対策について、浜松医療センター感染症内科部長の田島靖久さんに、SBSアナウンサー牧野克彦がお話をうかがいました。
牧野:そもそも家にいるダニとマダニは何が違うのでしょうか?
田島:ダニというと、みなさんは家の中に住むイエダニやヒゼンダニを思い浮かべると思いますが、これらとは見た目の大きさから異なります。マダニは吸血する前の大きさが約2~4ミリぐらいと、ダニの中では比較的大きいダニになります。この大きさですので吸血する前から肉眼で確認できますが、吸血すると10〜20ミリとかなり大きくなります。ちょっと大きいホクロぐらいのサイズ感ですね。
牧野:その大きさですと、肉眼で確認することができますよね。
田島:そうですね、見える大きさになります。
牧野:どういう場所で咬まれてしまうのでしょうか?
田島:基本的には、やはり山や森、広い公園や河川敷の草むらなどに潜んでいて、そばを通りかかった動物に飛び移る機会を狙っています。
もしもマダニに咬まれたら?
牧野:マダニに咬まれたら、どうなるのでしょうか?田島:この虫に咬まれると「日本紅斑熱」や「重症熱傷血小板減少症候群(SFTS)」など、致死率の高い病気にかかることがあります。
牧野:マダニに咬まれたことが原因で、死んでしまうリスクがあるということなんですね。「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」の罹患者が実は静岡県内でも3月に浜松で、4月に焼津で確認されているということです。これはどういう病気なんですか?
田島:マダニに咬まれた後、大体6〜14日後に熱が出たり体がだるくなり、全身筋肉痛、頭が痛くなったりするなどいわゆるインフルエンザ様疾患を呈する症状が出て、その後に嘔吐、下痢、腹痛など消化器症状が認められたりします。
牧野:外から見ても、これはその病気だなということはわかりますか?
田島:ちょっとわかりにくいかもしれません……。他の病気と間違えられることが多いのではないかと思います。
牧野:病院に行って判定してもらうということになるんですね。
田島:マダニに咬まれている状態であれば皮膚科を受診して、マダニをとってもらうのがいいと思います。また、マダニに咬まれた後に、SFTSや日本紅斑熱を疑うようなインフルエンザ症状がでた場合には、内科や皮膚科を受診するのがいいと思います。
牧野:その他にもマダニによる感染で気をつけたい病気はあるのでしょうか?
田島:先ほど出てきた「日本紅斑熱」や、稀なものでは「野兎病」などがあります。あとは、マダニではありませんが、マダニよりも小さいダニである「ツツガムシ」が原因の病気として、「ツツガムシ病」や「ダニ媒介性脳炎」「回帰熱」などが知られています。
活動が活発になる時期は?
牧野:これから夏に向けてマダニに注意が必要になるのは、マダニが活動しやすい気候になるからでしょうか?田島:その通りです。マダニ自体は基本的に1年中活動しているんですが、特に気温が15度以上になると活動が活発になると言われているので、特に4〜10月は気をつけた方がいいと思います。
咬まれないためには?
牧野:私もゴルフ場で咬まれたという話を聞いたことがあります。ロストボールを追いかけ、草むらの中に入っていって咬まれてしまったというケースなんですが、咬まれないための対策というのは何かあるのでしょうか?田島:マダニは露出した肌から吸血するので、帽子、手袋、長袖長ズボンなどを着用したり、シャツの裾はズボンの中に入れたりして、マダニが侵入してくるのを防ぐことが大事なポイントです。
マダニなどには、吸血対象者(動物)を感知するセンサーがあるのですが、その働きを悪くする作用があるディートやイカリジンという虫よけ成分が入った虫よけスプレーを一緒に使うのも、補助的な効果になると思います。
牧野:夏は蒸し暑いので半袖という方も多いでしょうが、草むらに入っていくときには長袖長ズボンというのは基本ですね。
田島:その方がいいと思います。
どんな症状になる?
牧野:マダニに咬まれたらすぐに気がつくものでしょうか? どんな症状になりますか?田島:実は咬まれて気づく人はほとんどいなくて、痛みはほぼないんじゃないかと思います。私の経験では、血を吸って大きくなったまま咬みついていたマダニをご本人のホクロと思っていた方もいました。
牧野:逆に言うと、それぐらい膨らんでくるということなんですね! マダニに咬まれたことに気づいたらどうすればいいでしょうか?
咬まれたときの対処法
田島:血を吸ってるマダニを無理に取ろうとすると、マダニの口の部分が皮膚の中に残って化膿することがあると言われています。ですから、できれば皮膚科など適切な処置ができる医療機関でマダニを取ってもらうのがいいでしょう。牧野:ということは、今吸われていると気づいても、パッと取らずに吸わせた方がいいんですか?
田島:吸わせすぎるのもいいわけではありません。咬みついてから24時間を超えると、前述の感染症のリスクが高くなると言われているので、真夜中でも行く必要があるかまではちょっとわからないですが、できるだけ早く医療機関にかかった方がいいかと思います。
牧野:その後も安静にした方がいいとか、何か気をつけるべき点はありますか?
田島:日常生活は基本的に普通でいいと思います。ただ、熱が出たとかだるくなってきたという場合には、医療機関にかかってもらいたいです。受診時には、いつマダニに咬まれたかも伝えてください。「日本紅斑熱」や「重症熱性血小板減少症候群」を診たことがない医者が多いと思うので、こういう病気が心配だと伝わることが、早く、正しい診断に繋がると思います。
牧野:マダニに咬まれているのに気づき、それをぱっと取った。その後、特に症状が出ていないという場合は、そのまま家にいてもいいのか、 一応病院に行った方がいいのでしょうか?
田島:基本、症状がなければ行く必要はないと思います。
牧野:症状が出た場合には、できるだけ早めに行く方がいいということですね。マダニによる感染症は昔からあったのでしょうか?
マダニの感染症はいつからある?
田島:「日本紅斑熱」という病気が、マダニが知られるきっかけになったと思います。この病気は1984年に、日本人の馬原文彦先生が報告して世界で認知されるようになりました。先ほど言った「重症熱性血小板減少症候群」は2011年に中国から報告され、2013年に日本にも患者がいることが確認されました。その後の調査で、実は2005年の時点で日本にこの患者がいたことが確認されているので、それ以前から日本に存在していたと考えられています。牧野:最近はより増えてきてるんですか?
田島:この「重症熱性血小板減少症候群」は治療薬がなく致死的病気、特に50歳以上の方には致死率の高い病気だということが、2013年頃から医療界でも盛んに注意喚起されるようになり、診断される症例もどんどん増えています。
牧野:それはますます気をつけなければいけませんね。では最後にみなさんにひとことお願いします。
田島:草むらやハイキングに行った後は、家に入る前に衣服などにマダニがついていないかをチェック。お風呂に入った後も、ご家族などにマダニがついていないかをチェックしてもらってください。リスクや適切な対応をちゃんと知って、夏を楽しんでいただければと思います。
※当サイトにおける情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。記事内容は個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当サイトで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、並びに当社と契約した情報提供者は一切の責任を負いかねます。
免責事項
今回お話をうかがったのは……田島靖久先生
1978年静岡県生まれ。自治医科大学卒業後、静岡県の地方診療に従事し、現在浜松医療センター感染症内科部長。COVID-19診断も難しかった2020年2月、当時世界が認めていなかった唾液でのCOVID-19診断を鹿児島大学隅田泰生教授と研究開発し、浜松から世界に発信。モットーは『明日のよりよい医療のために、今何ができるか』。



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る