 厳しい言動で相手の成長を促す「愛のムチ」。げんこつから叱咤[しった]激励の言葉まで、幅広い行為の比喩として使われてきました。虐待やパワハラが強く非難されるようになった近年は耳にする機会が減り、逆に「叱らない指導」の試みが注目を集めています。一方で、しつけや教育には「愛のムチ」も時には必要という声も根強く、特に他人の子どもを預かる仕事をしている人の中には、「この子には愛のムチが必要では」と思いたくなる場面も少なくないという人がいます。皆さんは「愛のムチ」という言葉はもう死語だと思いますか。
厳しい言動で相手の成長を促す「愛のムチ」。げんこつから叱咤[しった]激励の言葉まで、幅広い行為の比喩として使われてきました。虐待やパワハラが強く非難されるようになった近年は耳にする機会が減り、逆に「叱らない指導」の試みが注目を集めています。一方で、しつけや教育には「愛のムチ」も時には必要という声も根強く、特に他人の子どもを預かる仕事をしている人の中には、「この子には愛のムチが必要では」と思いたくなる場面も少なくないという人がいます。皆さんは「愛のムチ」という言葉はもう死語だと思いますか。■「避ける」社会の風潮
県東部の学童保育支援員の女性(63)は今年、地元の市の放課後児童クラブに再就職し、あまりに騒がしい現場に「学級崩壊のようだ」と衝撃を受けました。
机に乗って悪態をつき、特定の児童に暴言を吐く児童たち。諭そうとしても耳を貸してくれません。散らかるごみを片付けた児童に「ありがとう」と声をかける大人はいても、叱る姿は見当たらず、仲間に相談すると「背景を見よう」と言われるだけ。無力感で精神的に追い込まれた女性は2カ月弱で退職しました。
女性は別の市の放課後児童クラブで約20年働き、求められる指導の変化を肌で感じてきました。かつては「ダメなものはダメ」と厳しく向き合い、児童と心が通う実感があったそうです。全国で体罰が問題になり、「大声で叱らない」といった運営方針が示されて、戸惑いながらも適応に努めました。研修で推奨された、怒らずにチームで雰囲気を改善する新たな指導法も実践し、手応えを得つつありました。
ただ、女性には、口うるさい大人がいない場所で弱い相手を攻撃するような、状況に応じて態度を変える児童が増えているようにも映ります。「善悪を学べていないのでは」―。再就職先の施設で、その懸念が現実になったと感じた女性は「大人には許されないことをしっかり教える責任があるのに、みな他人任せのよう。叱ることを避ける社会の風潮が、行き過ぎたブレーキになっているのでは」と疑問を投げかけました。
20年前には
この20年余りで指導の考え方は教育、保育の現場だけでなく、子育てやビジネスの世界を含めて、社会全体で変わってきました。
平成初期までに学生時代を過ごした人は、指導者による体罰、叱責[しっせき]を少なからず経験したのではないでしょうか。「愛のムチ」という言葉も、相手の成長を願う真剣さを表す意味で使われていました。
静岡新聞社が1999年に展開した読者投稿特集「トークバトル・体罰は愛のムチか」を振り返ると、教員の体罰に対する賛否は割れつつも、愛のムチの必要性に疑問を呈する意見はほとんど見られません。厳しい態度で相手と向き合う指導者に、多くの投稿者が敬意と共感を向けている印象です。「生徒が先生からの体罰を愛のムチだと考えれば、将来絶対に役立つ時がくる」と書いた中学生もいました。
進む法整備
その後、指導と称する暴力や暴言で若い命が失われる事件が絶えず、体罰防止の法整備が進みました。教育現場では違法な体罰と指導上必要な「懲戒」が明確に区別され、2020年の改正児童福祉法・児童虐待防止法施行で家庭内の体罰も禁止されています。脳科学の研究から、暴力や暴言が脳の機能に深刻な悪影響を及ぼす危険性も明らかになってきました。
厚生労働省などは、法改正の流れに合わせて「愛の鞭[むち]ゼロ作戦」と題したキャンペーンを始めました。子育て中の保護者に「虐待にエスカレートする愛の鞭は捨ててしまいましょう」と呼びかけ、社会全体で「叱らなくて良い環境づくり」を形成するための考え方を発信しています。
永遠のテーマ
愛のムチが意味する行為のうち、心身に強いストレスを加える暴力や暴言は、もはや違法であり指導には使えません。
では、感情を伴った言葉で改善を強く促す「怒る」「叱る」も避けるべきなのでしょうか。法務省が虐待禁止の法改正をまとめた資料には「社会的に許容される正当なしつけ」は可能だと明記され、職場のパワハラ防止措置を定めた改正労働施策総合推進法は、「業務上の適正な範囲」での叱責を容認していると読めます。とはいえ、時と場合、程度によって評価が分かれる面があり、以前より非難されるリスクが大きくなりました。それだけに、怒り方や叱り方について悩む人が増えているようです。
日本アンガーマネジメント協会認定ファシリテーターで、企業や学校、地域向けの研修講師を務める山崎美代子さん(53)=掛川市=によると、叱り方に関する講習は要望が多く、「怒るのは悪いことなのか」という質問もあるようです。
山崎さんは「受け手に耐性がないと深く傷つける場合がある」と注意点を示した上で、「怒りは自然な感情。叱りは相手の気づきになることもある。避けるのではなく、正しい使い方を学ぶことが大切」と説明します。怒りの感情があると理性が利きにくく、相手を責めることが目的化してしまいがち。講習では感情を制御し、相手に明確なリクエストを伝えるため、知識や技術を高めていきます。
「私自身も怒りをうまくコントロールできず、叱り方に自信がなかった」という山崎さんは、さまざまな叱り方の使い分けができるようになり、気持ちに余裕が生まれたそうです。一方で「コミュニケーションの中でも他人の問題を指摘するのは特に難しい。誰もが悩んできた、永遠のテーマでは」とも話しています。

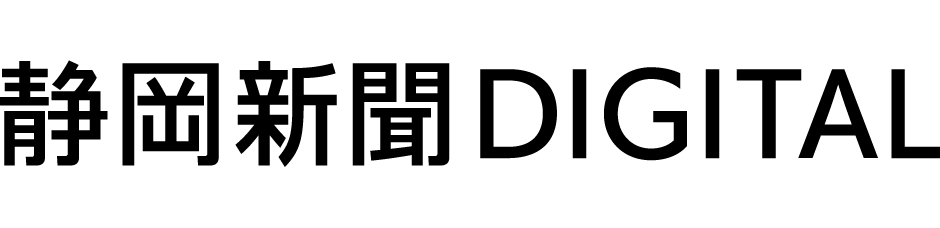

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る
































































