 業界に衝撃を与えた訪問介護の基本報酬引き下げから1年がたち、在宅介護の根幹をなす静岡県内の訪問介護事業者の窮状が浮き彫りになってきた。ガソリン代などコスト高も追い打ちをかけ、効率的な移動で利益を稼ぐ大都市の事業者との地域間格差が拡大。団塊の世代の介護需要増加を前に、地方で訪問介護の経営基盤が揺らぎ、自宅で過ごす高齢者を支える「最後の砦」が危機にひんしている。
業界に衝撃を与えた訪問介護の基本報酬引き下げから1年がたち、在宅介護の根幹をなす静岡県内の訪問介護事業者の窮状が浮き彫りになってきた。ガソリン代などコスト高も追い打ちをかけ、効率的な移動で利益を稼ぐ大都市の事業者との地域間格差が拡大。団塊の世代の介護需要増加を前に、地方で訪問介護の経営基盤が揺らぎ、自宅で過ごす高齢者を支える「最後の砦」が危機にひんしている。「段差があるので気をつけてくださいね」「お薬は飲みましたか」―。細やかな気配りをしながら、弱視の伊豆市の女性(83)=要介護2=に声をかけるのはホームヘルパー松下素子さん(69)。伊豆中央ケアセンター(同市)で訪問介護事業のサービス提供責任者を務める。女性宅で清掃や洗濯、入浴介助、調理などを約1時間で手際よくこなすと約5キロ離れた次の利用者宅に車で移動した。
到着すると息つく間もなく、服などが散乱した部屋の片付け。同市内で独り暮らしの女性(87)=要介護2=は認知症のため物を散らかしてしまう。近所のコンビニがなくなって買い物にも行けなくなり、松下さんが代わりにスーパーで食材を購入してきた。
同センターは伊豆半島中央部の面積約300平方キロメートル(東京・山手線内の約5倍)の利用者をカバーする。ヘルパー7人が1人1日6、7件を車で回るが「収益を出すのは難しい」と松下さん。高騰するガソリン代も事業所の介護報酬に反映されず「田舎では効率が悪く、訪問介護単体では採算が厳しい」と嘆く。
一方、県内外の都市部では近年、集合住宅タイプの住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が急増した。ヘルパーが集合住宅内を効率良く回って利益を稼ぐ訪問介護事業所とひとくくりにされ、介護報酬引き下げの一因になったとされる。人口密度が少なく移動の時間や費用で不利な農村部の事業所が結果的に割を食った。県中部の訪問介護関係者は「件数が多ければ薄利多売で収益が出やすいが、場所によって収益性が全く違う」と明かす。
特に小規模事業所は、低報酬に加えて人材不足や人件費高騰の影響も大きい。関係者は「このままでは訪問介護を利用したくても対応できる事業者が少なくなる。困るのは高齢者自身やその家族」と訪問介護サービスの空白域が出かねないと警鐘を鳴らす。
■仕事 もっと評価されるべき
介護問題に詳しい日本総研の岡元真希子副主任研究員の話 訪問介護の人材確保は困難を極め、経営努力として対応できる水準を超えている。事業所単位ではなく自治体レベルで供給体制の確保に向けて動く必要がある。介護報酬を決める国の役割も大きい。訪問介護は介護技術に加えてコミュニケーション能力や臨機応変な対応など高いスキルが求められる仕事であり、もっと高く評価されるべきだ。保険料を上げてでも介護報酬を引き上げないと、介護サービス不足によって家族の介護負担が増え、四半世紀かけて推進してきた介護の社会化の流れが逆行する恐れがある。
<メモ>訪問介護 介護保険サービスの一形態。掃除や洗濯、買い物支援などの「生活援助」と排せつや入浴の介助などの「身体介護」があり、自宅を訪ねたホームヘルパーが一定時間内に対応する。ケアマネジャーの作成するケアプランに基づき計画的に利用する。デイサービスなどの通所介護と組み合わせることもあり、家族の介護負担の軽減につながる。要介護度や状況によって介護施設に入れない場合があり、介護保険の利用者は施設介護よりも在宅介護が圧倒的に多い。

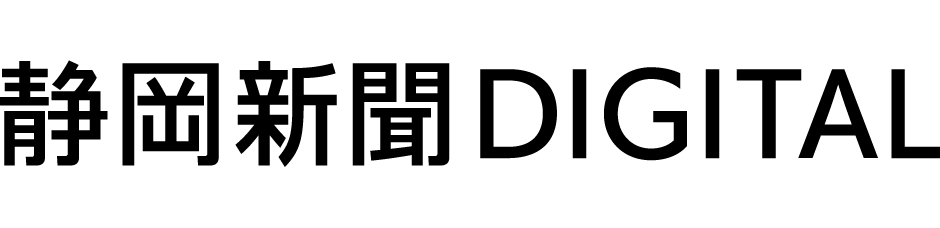

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る































































