
かつて、安倍川の上流、梅ヶ島には金山があり、江戸時代に流通した慶長小判にも、そこから産出される金が使われていました。
この金山にまつわる逸話があるのが、駿府の銘菓「安倍川餅」です。江戸時代のはじめ、安倍川のほとりの茶店に立ち寄った徳川家康に、つきたての餅にきなこをまぶしたものが振る舞われました。豆の粉を、安倍川上流の金山から採れる金の粉に見立てて「金な粉」(きんなこ)と称していたのを、家康はたいそう気に入り、この餅を「安倍川餅」と名付けたといわれています。
以来、安倍川のほとりには、安倍川餅の店が並ぶようになったと伝わり、江戸時代中頃に東海道の旅の名所が描かれた「東街便覧図略」にも、駿府の名物として安倍川餅が登場しています。
三代将軍 家光の時代、初代主人が明の僧侶から羊羹の製法を伝授され、東海道と清水港へ向かう道の分岐点に店を構えたことから、その名が付けられたという「追分ようかん」。
江戸時代の文人であり食通として知られた大田蜀山人(おおたしょくさんじん)の歌にも詠まれた「うさぎ餅」とともに、「安倍川餅」は駿河三大名物とも呼ばれています。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

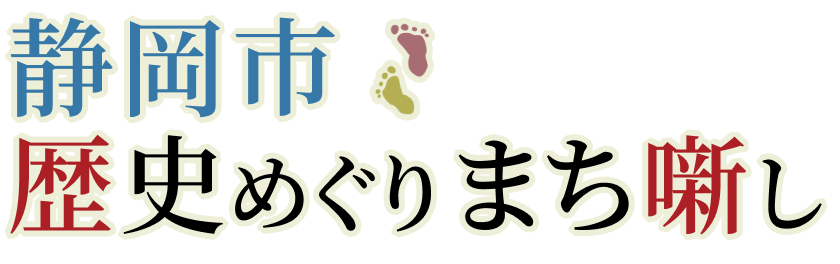

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る



































































