 能登半島地震や2022年の台風15号で断水が長期化したことを受け、民家や事業所の井戸を災害時用に市町に登録する制度が静岡県内でも広がり始めた。断水時に生活用水を住民に無償提供してもらうのが目的。国は3月にガイドラインを策定し、全国に普及を促した。本紙の取材では、県内では本年度に3市が導入したのを含めて9市町が既に実施し、準備・検討中も9市町と拡大しつつある。導入済みの9市町はいずれも、災害下では井戸水を非飲用での使用に限定。一方、井戸所有者の個人名公開については対応が分かれている。
能登半島地震や2022年の台風15号で断水が長期化したことを受け、民家や事業所の井戸を災害時用に市町に登録する制度が静岡県内でも広がり始めた。断水時に生活用水を住民に無償提供してもらうのが目的。国は3月にガイドラインを策定し、全国に普及を促した。本紙の取材では、県内では本年度に3市が導入したのを含めて9市町が既に実施し、準備・検討中も9市町と拡大しつつある。導入済みの9市町はいずれも、災害下では井戸水を非飲用での使用に限定。一方、井戸所有者の個人名公開については対応が分かれている。同制度は「災害時協力井戸」「防災井戸」などの名称で民間の井戸を登録し、所在地の住所も市町がホームページなどで公表する。県内では21年4月に藤枝市が開始して以降、浜松、静岡、島田、磐田、清水の6市町が導入。本年度中に焼津、牧之原、下田の3市も井戸の登録を始める予定だ。これらの市町の中には、登録した井戸の所有者に対し、ポンプの設置や修繕、水質検査などの費用を補助している自治体もある。
内閣府が今春公表した南海トラフ巨大地震の新たな被害想定でも、県内の断水率は被災1週間後で70%(影響人口約250万人)、1カ月後でも24%(同約85万人)と示され、災害時の水の確保は喫緊の課題となっている。県も22年の台風15号で静岡市清水区などが長期断水したことを受け、23年度から災害用井戸制度を設けている市町への補助を開始。能登半島地震を受けて25年度からは既設井戸の活用に加え、新規の井戸設置にも補助を行うなど拡充した。県危機政策課は「市町と連携し、制度の普及を図りたい」としている。
災害用井戸を登録した民家や事業所には、水を求める住民が敷地内に立ち入り、行列ができるような状況も想定される。制度を導入した県内市町の中でもプライバシー保護やトラブル防止の対策まで具体的に規定している例は少なく、普及を図る上での課題は多い。
県内でも中東遠などの一部市町には地下水が豊富でなく井戸の少ない地域があるほか、貯水槽や河川水の活用などに重点を置く市町もあり、災害用井戸制度への関心には温度差がみられる。同課の担当者は「水の確保にはさまざまな方法があり、市町の実情に合った形で進めるのが基本。災害用井戸は選択肢を増やす一つの方法として検討してもらえれば」と話す。
■井戸水使用目的 国の指針では「生活用水」
内閣官房水循環政策本部と国土交通省が3月に公表した災害時地下水利用ガイドラインでは、井戸水の使用目的を主に「生活用水(飲用以外の洗濯、掃除、トイレなど)」とした。平常時に飲用している井戸水でも「周囲の下水道管破損の影響や水脈の変化で水質が変わる可能性がある」ためだが、水質の条件が確保されれば飲用も可とした。
災害下で必要な水の量として、発災から3日間は飲用で1日1人当たり3リットル、4~10日目は最低限の炊事用なども含めて20リットル、11~21日目は洗濯用なども含めて100リットルと例示した。

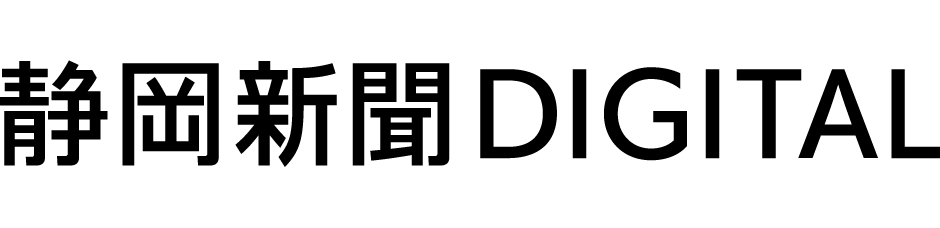

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る






























































