語り:春風亭昇太

2000 年前の「ムラ」の姿がよみがえる歴史的発見となった登呂遺跡。復元された水田、住居、高床式倉庫に、弥生時代の稲作文化の様子を知ることができます。
住居は、4本の柱を立てて、その間に横に渡した桁(けた)と梁(はり)で安定させる造りになっており、床の真ん中には、調理をするための炉がありました。
収穫した米を保管していたのが、高床式倉庫。湿気を防ぐために床を高くし、床下には柱からのネズミの侵入を防ぐ「ネズミ返し」の板が挟み込まれていました。
昭和33 年に「静岡考古館」が開館し、それを前身として昭和47年に開館したのが登呂博物館。古代ロマンに魅せられて多くの人々が訪れ、2010年に現在の建物にリニューアルされています。
平成に入ってから、5年間にわたって 再び本格的な調査が行われ、登呂遺跡の中で一番大きな建物である祭殿(さいでん)は、その際に発見されました。祭殿のあたりから発掘されたのが、占いに使われた「灼骨(しゃくこつ)」といわれるシカの肩甲骨です。大陸から伝わった占いでは、動物の骨に熱した棒を押し当て、骨のヒビ割れ具合から、ものごとの吉凶を占い、豊穣を祈願していたようです。
弥生時代を象徴する水田と住居が一体になった遺跡であり種類豊富な多数の出土品が他の遺跡の指標となった登呂遺跡は、日本の国の成り立ちを知る上で、大変重要な役割を果たしてきました。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

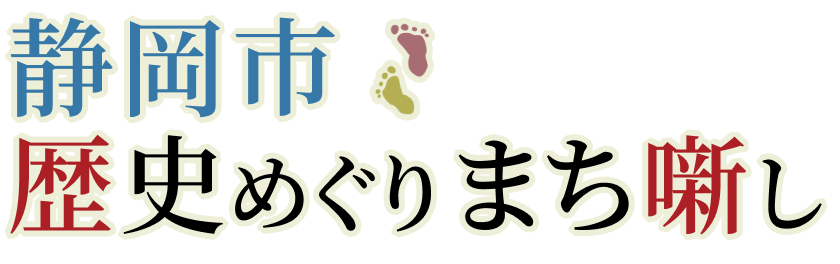

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































