語り:春風亭昇太

1889年(明治22年)東海道本線が東京・新橋駅から神戸駅まで全線開通し、これをきっかけに、興津の町は大物政治家たちの別荘地として注目されるようになりました。
明治維新の立役者のひとり、井上馨(いのうえかおる)も、明治29年、現在の清水区興津・横砂に別邸を建てました。「長者荘」と呼ばれた その邸宅は、5万坪といわれる広大な敷地にあり、ミカンの栽培も行われていました。
茶の輸出を推進するなど 地域経済にも貢献した井上馨。亡くなったときには、この偉人の葬儀のために、邸宅の敷地を通っていた東海道線に臨時の停車駅が設けられたと言います。風光明媚で、冬でも温暖な興津は、別荘地として、また海水浴場や、避暑地として、賑わいを増していきました。
江戸時代に興津宿の脇本陣だった、旅館「水口屋(みなぐちや)」 。昭和60年に400年の歴史に幕を下ろすまで、政財界人、小説家など多くの著名人がここを訪れていました。水口屋を度々訪れていた、明治の元老(げんろう)、西園寺公望(さいおんじきんもち)は、興津の地を愛し、1919年、別邸「坐漁荘(ざぎょそう)」を建設しました。京都から大工を呼び寄せて造られた、純和風建築の別荘には、見事な竹の欄間など職人の技が光ります。
2度の首相就任を果たし、一時代を築いた西園寺公(さいおんじこう)のもとには第一線を退いたのちも、ときの首相や閣僚が訪れ、それは「興津もうで」と言われました。昭和15年、西園寺公は92歳にして坐漁荘で亡くなり、その棺は、興津駅から列車で東京に運ばれました。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

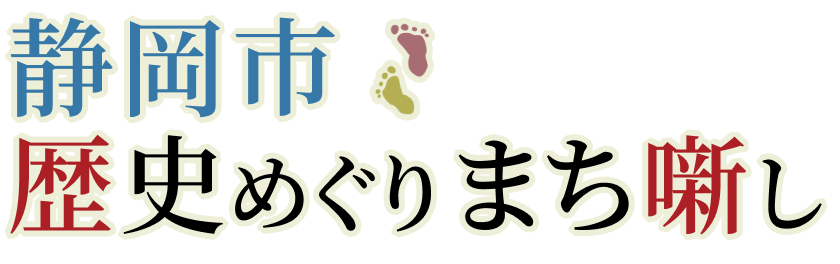

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































