語り:春風亭昇太

清水の夏の風物詩「清水みなと祭り」。清水次郎長、妻のお蝶、山岡鉄舟、そして28人の子分衆に扮した旅姿の市民が次郎長の生家が残る、次郎長通り商店街を練り歩く次郎長道中が祭りを盛り上げます。
明治維新前、「弱きを助け、強きをくじく」生き方とともにその名を知られた清水次郎長。若い頃の次郎長親分の姿は、映画や浪曲などで国民的英雄として描かれ地元、清水での功績が語り継がれています。
港湾の発展に尽力した次郎長は明治19年、清水波止場に船宿「末廣」を開業しました。現在は巴川のほとりに移築、復元され、かつての「末廣」の姿を今に残しています。
建築当時そのままの欄間には、三保の松原の風景があしらわれ、次郎長の清水への思いがうかがえます。「これから世の中、英語が必要になる」と、当時の日本では珍しい大人も子供も学ぶことができる、英語塾を開いた次郎長は貿易港・清水の未来を見据えていたのでしょうか。
次郎長とのゆかりが伝わるゆびまんじゅう。次郎長が、まんじゅうに指をつっこみ「これじゃあ、売り物にならない。わしがもらっていかざぁよ」と言ってそのまんじゅうを子供たちに配ったという逸話が残っています。「波止場のおじいさん」と子供たちから慕われた清水の次郎長は74歳で、その激動の生涯を終えました。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

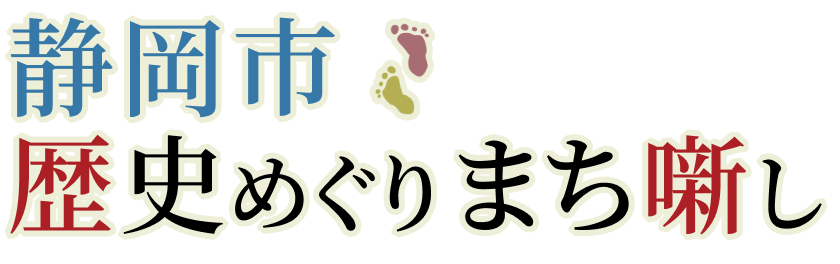

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































