
清水の次郎長こと山本長五郎は、商家 高木家の次男として、この家で生まれました。母親の弟、山本次郎八の養子となり、次郎八の所の長五郎と言う事で「次郎長」と呼ばれるようになったと言われています。清水湊で廻船業を営んでいた高木家。その住宅であった次郎長生家は、清水の庶民の暮らしを伝える、貴重な歴史資産として平成30年に国の登録有形文化財になりました。
次郎長生家がある清水区の美濃輪町。次郎長通りと呼ばれる通りと、巴川に挟まれたこの地区は廻船問屋が並び、清水港の歴史を今に伝えています。平成29年に改修された次郎長生家は、間口二間半、奥行き五間半の平屋で、幅一間の土間が奥まで続き、残された家具などに江戸時代の生活が垣間見えます。次郎長の産湯に使ったという井戸が当時のまま保存され、次郎長や子分の大政・小政が使った道具も展示されています。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

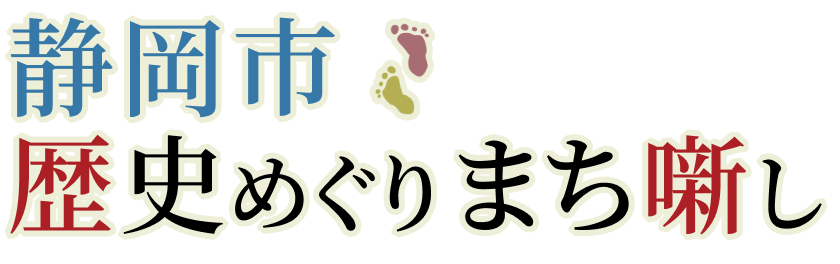

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































