語り:春風亭昇太

清水の山あい 庵原、両河内、小島、そして日本平。清水地域でお茶が本格的に栽培されるようになったのは明治時代初期のことでした。
きっかけを作ったのは、旧庵原郡杉山村(現・清水区杉山)の片平信明。幕末、生活が苦しかった村人に片平はお茶の栽培を勧めましたが、「お茶を植えると人が死ぬ」という迷信が広がり、資金不足もあって、なかなか受け入れられませんでした。片平は杉山青年夜学校を開いて、若者に読み書きそろばんから産業や経済についてまで熱心に教え、茶栽培を広めていきました。さらに「杉山報徳社」を結成し、資金難の村人に貸付を行った事で村人の生活は安定するようになっていきます。
静岡県内で栽培されているお茶の多くが「やぶきた」という品種で、このやぶきたを発見し、育てたのが杉山彦三郎です。良いお茶を求めて、全国を探し回っていた彦三郎は、現在の静岡県立大学の芝生広場近くで竹藪を開墾したときに、新しい品種のお茶を発見しました。竹藪の北側で発見されたことから「やぶきた」と名付けられたと言われるこのお茶は、品質が良く、収量が安定していたことから全国に広まって行きました。
「やぶきた」が発見された場所の近くにある、杉山彦三郎記念茶畑。彦三郎が全国から集めた100あまりのお茶の品種のうち13種類が、現在、地元の茶業関係者やボランティアグループによって育てられています。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

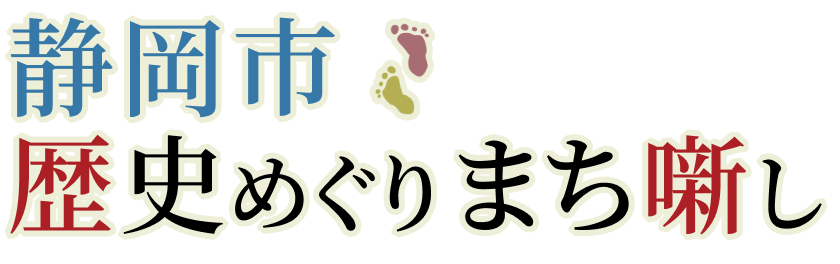

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































