
東海道丸子宿近くに残る名勝、吐月峰柴屋寺(とげっぽうさいおくじ)は、今川氏に仕えた連歌師「宗長(そうちょう)」ゆかりのお寺です。宗長はこの地の風景にほれ込み京都の銀閣寺を手本にして、月が綺麗に見える庭を仕立てました。
池には、北斗七星のかたちに石が置かれ、その脇には「月見石」と「座禅石」があります。宗長はここで月が出るのを待ち、池に映る月を楽しんでいたといわれています。「丸子富士」と呼ばれる山をのぞみ、背後の風景までを庭の一部とした借景庭園は国の名勝に指定されています。寺の山号にもなっている、ラクダの背中のような形をした天柱山(てんちゅうざん)。園内の東山に植えられた竹の先からは、ちょうど吐き出されるように月が浮かぶため、『吐月峰』の由来となっています。
宗長は、今川氏親のために当時都で流行していた「枯山水」を裏庭に造りました。京都嵯峨野の竹を植えたこだわりにも宗長の想いがこめられています。
今川氏が滅びたのち、この寺が荒れていくのを惜しんだ徳川家康によって、修復されたと言われています。この名勝には、数多くの文人が訪れ、山岡鉄舟もそのひとりでした。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

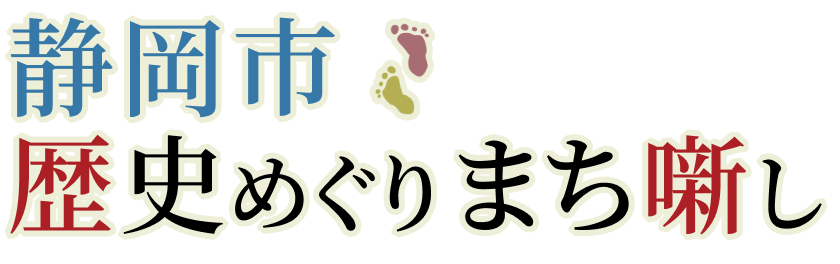

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る





































































