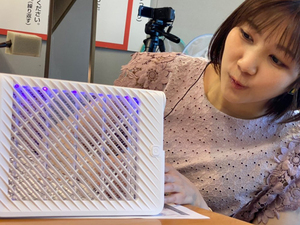(橋爪)きょうは火の見櫓(やぐら)の話です。静岡新聞では毎週金曜日の「ローカル文化」面で2023年12月から県内の火の見櫓を、主に文化の側面から紹介する連載を始めています。すでに2回掲載しましたが、1月に入っても続きますので、この機会に静岡の火の見櫓について、リスナーの皆さんにも知ってほしいと思い、取り上げることとしました。
(山田)そもそも火の見櫓って何なんですか。
(橋爪)火の見櫓は見たことないですか?
(山田)今は手元で写真を見てるから、見たことあるかもと思ったぐらいですね。日ごろはあまり意識していないので、電柱や電波塔なのかなという感覚でしか見てないですね。
(橋爪)火の見櫓は、集落において、火事の発生をできるだけ早く見つけ、釣り鐘の「半鐘」をたたいて知らせる施設です。集落の中に火事を知らせるのと同時に、別の集落への注意喚起も担っていたと言われています。
火の見櫓の発祥は江戸時代
(橋爪)火の見櫓の歴史は江戸時代にさかのぼります。1657年に江戸で起こった「明暦の大火」を契機に造られるようになったそうです。地方に広がったのは明治時代。第2次大戦時に鉄製の櫓や半鐘が供出の対象になって減ってしまったんですが、戦後に建て直す動きが出てきました。昭和28年、1953年に消防施設強化促進法が施行され、ポンプ小屋など消防施設が公的補助を受けて刷新されました。ということで、現存している火の見櫓は昭和20年代後半から30年代に建てられたものが中心です。(山田)すごい歴史があるものなんですね。
(橋爪)そうなんですよ。2000年代初頭に、県職員や当時の常葉学園大の先生たちによるグループ「火の見櫓からまちづくりを考える会」が、県内全域を調査して1016基を確認しています。それから20年ほど経つので、今はもっと数は少なくなっているとは思いますが、よく注意して探してみると、意外と県内のあちらこちらで見かけます。
(山田)早速、「X(旧ツイッター)」の方でも、リスナーさんから写真つきで「うちの前にもあります」との情報が寄せられました。
(橋爪)本当ですか!この会の代表の塩見寛さんは私の火の見櫓の師匠です(笑)。何度も取材し、すっかり火の見櫓好きになってしまいました。きょう、お話していることも多くは「まちづくりを考える会」関係の取材に基づくものです。
(山田)歴史のあるもので、火事などの防災関連施設だということは分かりましたが、それ以外に何か見どころはあるんですか?
(橋爪)デザインや建築構造が全て違うんです。集落ごとに地元の鉄工所が造ったりしているので、同じ形のものが二つとない。
(山田)個性があって、デザインなど建築物として面白いということですね。
(橋爪)高さや色も違ったりします。多くが鉄製なので銀色が最も多いですが、私が実際に目にしたものの中には白や水色、赤などもありました。「まちづくりを考える会」の調査によると、御殿場市で当時確認された7基は全部赤色だったそうです。
(山田)へぇー!
(橋爪)旧天竜市も赤ばかりだったという報告でした。現在はどんな火の見櫓が残っているのかについて、静岡新聞に昨年12月に2回掲載した記事を元に話をしたいと思います。
富士山と同じ視覚に入る「映える」スポットは?

(橋爪)最初に記事で紹介したのが富士市南松野にある火の見櫓でした。ここは火の見櫓ファンならずとも知られた場所です。カフェ「無上帑(むじょうど)」の敷地の一角に立っています。原稿にも書きましたが、貴婦人のような美しさがあります。
(山田)確かに。写真を見ると、ウエストの部分が細い感じがあって。
(橋爪)19メートルで結構高いんですけど、スラッとしていてあまり圧迫する感じがないんです。
(山田)足の部分も何かハイヒールを履いてるような感じにも見えますね。
(橋爪)すごい素敵な表現、感覚ですね。素晴らしい。これは1951年にドイツ人の設計士がデザインして完成し、「東海一美しい」と言われたらしいです。
富士山と火の見櫓が同じ視界に入る場所としても知られていて、非常に「映える」スポットになっています。
(山田)前提として、今は火の見櫓としては使われていないんですよね?文化財として残っているんですか。
(橋爪)富士市南松野の火の見櫓は、2006年に国の登録有形文化財に認定されています。
静岡市には別の役割を担う”現役”も

2つ目に紹介したのは静岡市駿河区池田の火の見櫓です。しずてつジャストラインのバス停「池田」のすぐ近く。静岡市消防団静岡第14分団の器具置き場の駐車場敷地内にあります。ここの特徴は半鐘が残っていることです。
(山田)写真を見ていますが、本当ですね。
(橋爪)高さは15メートルほどです。終戦後まもなく建てられたましたが、材料は当時の中部電力静岡支社から譲り受けたと聞きました。はっきりしないところですが、送電用の鉄塔だった可能性もあるそうです。
(山田)鉄塔をそのまま火の見櫓にしたということですか。
(橋爪)現在はスピーカーが4台付いていて、地域の情報を伝える役目を果たしています。
(山田)そうなんですか!
(橋爪)リスナーの皆さんにも火の見櫓の画像を見ていただきたいですね。もしよかったら「X(旧ツイッター)」で、ひらがな「しずおか」の後に1角空けて「火の見櫓」で検索してみてください。静岡新聞教育文化部のアカウントで、「しずおか火の見櫓コレクション」と題して多種多様な火の見櫓を紹介しています。
藤枝市にあったサッカーW杯のトロフィー型

(2014年撮影)
(山田)小さいのや細いのとかいろいろありますね。(橋爪)コレクションにも写真がありますが、藤枝市本郷の火の見櫓はサッカーワールドカップのトロフィーのような形をしていました。今回、新聞連載の取材候補に挙げていたのですが、1年ほど前に取り壊しになってしまっていました。そういうこともあるので、気になったものは今のうちに見ておいた方がいいと思います。
(山田)知りませんでした、火の見櫓の魅力。、
(橋爪)1月12日にも火の見櫓の記事が出るんですが、今回は森町なんです。取材した記者によると、1992年に48基を数えた町内の火の見櫓は現在29基まで減少しているとのことでした。
腐食の進行があったり、今は防災拠点としての機能がなかったりするので、取り壊すことに躊躇がないのが実情のようです。火の見櫓は徐々に消えゆく運命にあるのかなと感じます。
(山田)残したままだと危ないということもありますもんね。
(橋爪)そうですね。地震のときに倒れたらどうするんだという議論も一部ではあるようです。
(山田)でも、今日のような解説付きで見ると面白いですね。
(橋爪)写真を撮るとコレクションできるので、ドライブするついでに見つけたら撮影するといいかもしれませんね。
(山田)火の見櫓の写真コレクターが増えそうですね。次の記事も楽しみです。
(橋爪)安心安全のまちづくりというものを再認識させるようなモニュメントでもあるので、今のうちに大事にしておいた方がいいかなという気はしますね。
(山田)ありがとうございました。今日の勉強はこれでおしまい!

(2014年撮影)



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る