
(橋爪)今日は2月10日から一般公開されている県立美術館(静岡市駿河区)の企画展「天地(あまつち)耕作」展を取り上げます。県立美術館は1、2年に1回、現代アートの展覧会を開催するのですが、今回の「天地耕作」展は、わたしの知る限り、屈指の「とがった」展覧会になっています。
(山田)とがった展覧会?
(橋爪)尊敬の念を込めてそう表現させていただきます。これに匹敵するのは2022年度の「みる誕生 鴻池朋子展」。裏山に皮のでかいトンビを展示したかなりアバンギャルドな展覧会でした。
あと思い出すのは、2019年度の「やなぎみわ展 神話機械」。展示室に入ってすぐ、骸骨を次から次へと投げつける機械が設置されていました。今回はそれ以来の衝撃的な展覧会です。
浜松市の兄弟含む3人によるプロジェクト
(山田)その「天地耕作」展について教えてください。(橋爪)何より今回の「天地耕作」展がすごいのは、作品がほとんど現存しないことです。
(山田)作品は現存しない?
(橋爪)どういうことか、説明しましょう。「天地耕作」は浜松市の美術家・村上誠さん、渡さん兄弟と、山本裕司さんの3人が1998年から2003年にかけて一緒に活動したプロジェクトの名前です。彼らの作品は基本的に野外、例えば山の中や採石場の跡地、湖畔でつくられます。
そういった人が訪れにくい場所なので、作品を実際に見た人も少ないんです。また、彼らは作品のことを耕作物と呼んでいます。
(山田)タイトルが天と地が作ったものということですもんね。
(橋爪)そうですね。材料は石、土、木材、流木、わら縄。ある意味でその場に置いたままにしても環境的に何も問題がないようなものを材料にしている感じです。今回の展覧会は、そんな彼らの知られざる耕作物の数々を、写真や映像で振り返る、というのが基本です。
それと同時に、今回新たに制作した作品が美術館の裏山にあり、構造物とも彫刻とも建築とも言えそうな物体が並んでいます。それも含めて楽しめます。
館内の展示にある映像には、35年前の3人が若い姿で映っています。場所は浜名湖の北側、細江町や引佐町の山の斜面。そこに流木を持ち込んで巨大なボウル、鉢のような形に組み上げて、家屋の壁を塗るように土を付ける作業をしています。
それぞれにインタビューがあるんですが、とてもおもしろいことをいっていました。この展覧会を象徴するような話だったのでちょっと紹介します。
村上誠さんは「多くの人に見てもらいたいとは思っていない」といきなり言い切ります。
(山田)作品なのに?
(橋爪)「僕らはいろんな意味で特権を持っている。いなかもんであることも特権の一つ。それを逆手にとって、好きなことをやらせてもらっている」とも言っているんですよ。まさにそういう内容なんです。わかりにくいですか?
(山田)難しいですね。作品には普通、何かのメッセージがあるじゃないですか。
人間と自然が絡み合ってこその芸術
(橋爪)そうですね。われわれが使う「作品」という言葉には一定のイメージがありますよね。例えば美術館で保存されていて、ショーケースの中に入れて大事に見るものや、形を少しでも欠くことがないように保存されたもの、という認識ですよね。彼らの「耕作物」はまったくそうではないんです。材料は自然のもので、野外で制作をするので雨や風の影響で崩れることがあってもOKで、それも含めて作品だという考え方なんです。
展覧会の会場には、1988~89年の「天地耕作」壱、1992年に旧引佐町の採石場跡で行った「天地耕作」弐、1994年に旧浜北市の社会福祉施設で行った「天地耕作」参など、プロジェクトごとの写真がずらっと並んでいます。オーストラリアやフィンランドに呼ばれて制作したときの様子もあります。
(山田)世界的に活躍しているんですね。
(橋爪)さきほどお話した、雨や風の影響も含めて作品だということが最もよく分かるのが1992年の「天地耕作」弍です。写真が展示されているんですが、このときは台風が直撃したんですよ。
(山田)どうなっちゃったの?
(橋爪)写真を見ると「耕作物」の前に池みたいな水たまりができていたり、一部が傾いたりしています。
(山田)それでもいいのだと。
(橋爪)彼らはそれありきで「完成」としたそうです。
私がいま話している内容は、ちょうど2月18日に県立美術館で金沢美術工芸大学講師の文化研究者山本浩貴さんが講演をしていて、ものすごく的確に解説してくださっていたので引用させていただいています。山本さんは「天地耕作」の芸術について「人間、自然というアクターが絡み合ってこその芸術」と評価していました。まさにそうだなと思えます。
(山田)大阪芸大時代を思い出します(笑)。おっしゃっていることは理解できます。
(橋爪)やや哲学的になってしまったので、最後に、ちょっと飛躍的な、かなり独自の解釈に基づく見どころ紹介をしましょう。
(山田)それは橋爪記者としての解釈?
独自の解釈による楽しみ方も!
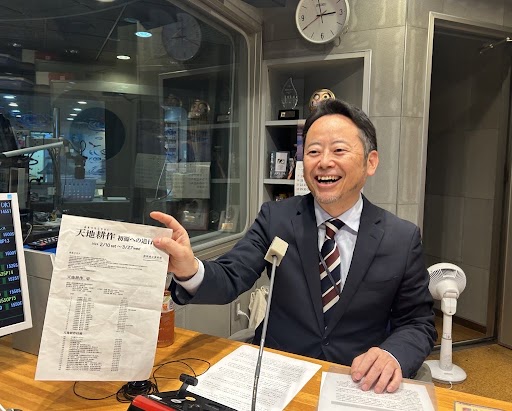
(橋爪)完全にそうですね。山本浩貴さんの講演は美術史に依拠したきちんとした論考でしたけれど、これから話すことに根拠はありません。根拠はないけれど、アートに興味がない方にも足を運んでほしいので、「こう見たら楽しいよ」という提案をしたいと思います。
(山田)はい、お願いします。
(橋爪)私は今回の展覧会を見て、アニメ「エヴァンゲリオン」との造形的共通性を見出しました。エヴァンゲリオンはわかりますか?
(山田)わかります。
(橋爪)テレビシリーズ「新世紀エヴァンゲリオン」は1995年10月から1996年3月までの放送で、2021年に「新エヴァンゲリオン劇場版」で完結しました。「天地耕作」は壱が1988年、弍が1992年、参が1994年ですから、「天地耕作」の方が先行しています。それを踏まえてお話すると、なんとなく「天地耕作」の作品がことごとく、「使徒」っぽい。
(山田)エヴァンゲリオンに出てくる使徒?
(橋爪)そうです。最も共通性が顕著なのは「天地耕作」壱に出てくる「辻」という作品。高さ4メートルの木を2本立てて、その上部に、土と流木でつくった球体を2本の横棒で串刺しにして設置しています。丸い顔から足が2本生えているように見えて、これがエヴァンゲリオンを見ていた方ならわかると思うのですが、「第7の使徒」にそっくりなんです。
(山田)手足が細いやつですか。
(橋爪)エヴァ2号機のパイロット、式波アスカ・ラングレーが初登場する場面で海からやってくる使徒ですね。
「天地耕作」壱でいうと、「氏神の祠」はテレビシリーズの「第4の使徒」に似ているし、「天地耕作」弍でつくられた「産土」は球や円筒から四方八方にわら縄が伸びているんですが、これは映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」に出てくる使徒を思わせます。
何より、「天地耕作」参で、四本足の動物のような作品を夕方、逆光で撮った写真があるのですが、これは暴走したエヴァ初号機が空に向けて吠えているようにしか見えません。
(山田)そうなんですね。リスナーさんから「エヴァの話になった途端、急に見に行きたくなった」というメッセージが来ました。
(橋爪)思うツボですね(笑)。ぜひ見に行ってください。
ここから先は完全に戯言ですが、1990年前後にエヴァの制作スタッフが「天地耕作」を見ていて、キャラクターデザインに生かしたとしたら面白いなと。あるのかな、そんなこと?そんな視点で見ることもできます。
(山田)もしそんなことがあったら鳥肌ものですね。でも美術ってそういうものかもしれないですね。好きに解釈をしていいという。
(橋爪)良いこと言いますね!そうだと思います。だから難しいと考えずに、気軽な気持ちで足を運ぶのはいかがでしょうか、ということで今日のお話は締めたいと思います。
(山田)ありがとうございます。僕は展覧会の写真を見たらスタジオジブリの「天空の城ラピュタ」のロボット兵に似ているなと思いました。
(橋爪)番組が始まる前にそれを言われて、そうかなと思ってしまいました(笑)。
(山田)というわけで、今日の勉強はこれでおしまい!



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































