
(市川)国会が岸田文雄首相と大臣の給与を上げる法律を可決したという話題です。先日、岸田首相ら国家公務員特別職と一般職の2023年度給与を引き上げる改正給与法が参院本会議で、与党などの賛成多数により、それぞれ可決、成立しました。与野党からの批判や物価高に苦しむ国民感情に配慮し、少なくとも首相のほか、閣僚と副大臣、政務官の政務三役は増額分を自主返納します。
(山田)今日のトピックスなんですけど、実は疑問があって僕から取り上げてもらいたいとお願いしました。
(市川)確かにこの話は分かりにくい部分があると思うので解説したいと思います。
(山田)僕がまず疑問に思ったのは、内閣支持率が下がり、内閣改造後に不祥事で次々と政務三役が辞任する状況の中で、なぜ首相や大臣の給料を上げるなんてことをしたのか。そこについて教えていただきたいのですが。
(市川)ざっくり言うと「民間の給料が上がっているから公務員の給料も上げる」ということです。「賃上げ」という言葉を最近よくニュースで聞くと思いますが、物価高に伴って全国的に賃金は上がっている、という調査結果が出ています。
民間の給料は基本的には市場原理で決まります。少ない社員数で大きな利益をあげている企業の給料は高くなるし、いろんな番組から引っ張りだこのタレントさんや、俳優さんのギャラはおのずと高くなっていくでしょう。一方で、市場原理で給料を決められないのが、公務員や政治家なんです。
(山田)そうか。
公務員の給与は民間の水準を基に決まる
(市川)公務員の給与は民間の給与水準を基準にして決めているんです。国には、人事院という組織があります。この人事院が国家公務員の給与水準を毎年勧告しています。複雑な計算式があるらしいんですが、民間の給与水準を調べ、公務員の給与を上げるのか、下げるのか、または据え置くのかを勧告しています。(山田)へぇー。そういう計算式があるんですね。
(市川)この人事院勧告が今年も8月7日にあり、国家公務員の給与について引き上げるように勧告しました。2年連続のことです。実感はありませんが、民間の給料が上がっているからということなんです。
ただ、人事院の調査は従業員が50人以上の企業に限っているので、いわゆる零細企業や個人事業主は調査対象になっていません。小さい企業の方とのギャップが生まれる原因はここにあります。ちなみに、今回の国家公務員の引き上げ率は一般的な行政職で0.96%引き上げるべき、との勧告でした。これは実に26年ぶりの高水準の引き上げだったんです。行政職の平均年収だと10万5000円増になる計算です。
(山田)いいですねぇー。
(市川)景気のいい話ですよね。ただ、これは公務員の話なのに、なぜ政治家の給与も上げるの?という疑問が出てくると思います。
首相や大臣は行政のトップである「国家公務員特別職」という位置づけなんです。
(山田)それは知りませんでした。
(市川)この特別職の給与の上げ下げについては、国家公務員の給与改定に準じて行うことが“慣例”になっているんです。つまり、民間の給料が上がっているから公務員の給料を上げた、公務員の給料を上げたから、慣例で首相や大臣の給与を上げた。特別職の給与を上げたときは国会議員のボーナスも上がるというのが慣例になっているので、今回それも上がった。これが引き上げの理由です。
(山田)公務員の給与を上げたら特別職も上げるという決まりだということですね。
(市川)慣例なので別に上げなくてもいいのかもしれませんが、今年だけやめるというと慣例が続かなくなってしまうという思惑があるんでしょうね。
給与改定は静岡、浜松など地方自治体でも
(市川)ここからは、もう少し身近な政治に引き寄せて考えたいと思います。これまで話したのは、国政の話ですが、これと同じことが、県政や市政などわれわれの身近な政治でも行われています。(山田)ほう。
(市川)静岡県庁や静岡市役所、浜松市役所も職員の給与を引き上げる条例がいま開催中またはこれから開催される議会に提出されます。県や市には、人事委員会という組織があり、人事院のように民間の給料を調査していて、毎年、職員の給与について勧告しています。今年は静岡県、静岡市、浜松市のいずれも職員の給与を上げようという勧告が出ています。
では、特別職はどうかというと、地方自治体の特別職は知事や市長、副知事、副市長などですが、静岡市と浜松市はボーナスを上げる方向になっています。
今回、一般の生活者が物価高で苦しんでいるのに首相や大臣の給与を上げるのはいかがなものかという声が強まり、政務三役は増額分を自主返納するということになりました。静岡市でも市長らのボーナス引き上げに異を唱えている市議会議員がいます。
静岡市は一般職員の給与引き上げに合わせ、特別職と市議のボーナスを0.1カ月分引き上げる条例を提出予定です。市長は15万円、市議は約8万円ボーナスが増える計算になります。
11月16日の静岡新聞に掲載されましたが、「緑の党」という一人会派で活動している松谷清市議が、新型コロナウイルスによる景気低迷や物価高の影響を受けている市民はまだまだ大勢いる、市民感情にそぐわない、という理由で、ボーナスを引き上げる議案を提出しないように静岡市に要望書を提出しました。岸田首相に対して巻き起こった世論感情と同じですよね。
実は静岡市は市長や市議のボーナスを昨年も市議会の賛成多数で引き上げています。政治家の給料やボーナスの上げ下げなどはこうした手続きを踏んでいるんですが、意外と皆さんに知られていないのかもしれません。
(山田)本当ですね。静岡市議会で反対している人は少ないんですか。
(山田)今のところは圧倒的多数が賛成して、ボーナスが引き上げられる公算が高まっています。市長や市議の給料、ボーナスを引き上げることに関してはさまざまな意見があると思います。ぜひ、みなさんも身近な話題として考えてもらいたいです。
(山田)はい。
(市川)ところで、給与の返上といえば、最近、川勝平太知事のボーナス返上のことで話題になりましたよね。給与改正の条例を出しても、県議会の多数派である自民党県議団が反対し、成立の見込みがなかったので提出しなかったという言い訳を覚えている方も多いと思います。ですが、今回、岸田首相が増額分の給与を返納するとなっても、あっさりとしていて、法律がどうのというような議論は出てないですよね。
(山田)確かに。
首相や大臣の給与返納は法律で認められている!
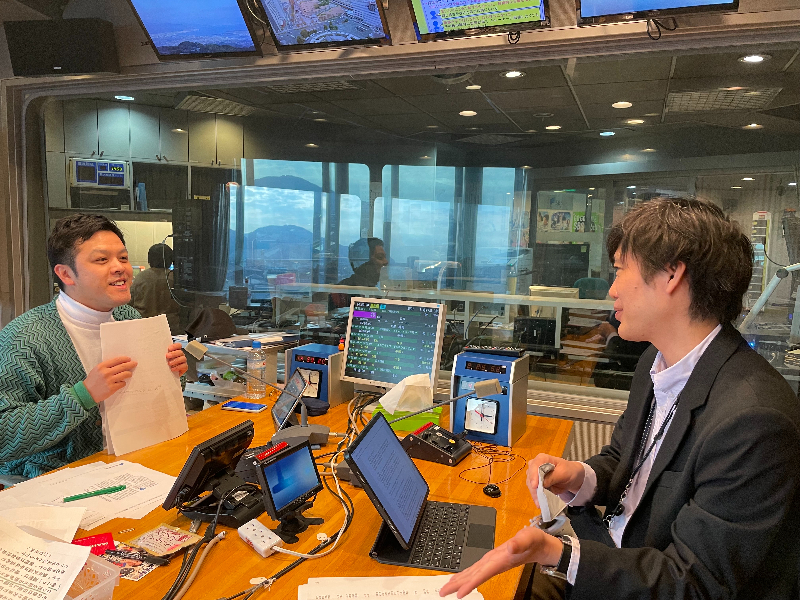
(市川)僕も今回、疑問に思って法律を調べてみました。首相ら大臣の給与は「特別職の職員の給与に関する法律」というものに基づいて定められているのですが、ここに附則として「国庫に返納する場合は、公職選挙法の寄附行為の禁止の規定を適用しない」と書いてあったんです。
(山田)返納してもいいということなんですか。
(市川)そうなんです。川勝知事が返納できなかったのは、政治家は寄附行為を禁じられているためでした。だから条例を改正する必要がありました。ただ、首相や大臣が給料やボーナスを返納するときは寄附行為に当たらないという例外規定が法律に書かれていたんです。僕も今回調べて初めて知りました。
(山田)いろいろと複雑ですね。
(市川)この規定がもし県知事の給与に関する条例にも書いてあったら、あんなに揉めなかったかもしれないですね。誰の許可も受けずに返納することができますから。
(山田)なるほど。そうなっているんですね。ただ、今回の首相と大臣の給与のニュースはタイミング的に良くない話じゃないかと思いましたけど。
(市川)給与の見直しは毎年この時期に行っているんですよ。
(山田)そうなんですね。
(市川)人事院や人事委員会の勧告が毎年8月ごろにあり、11月から12月に開かれる議会で給与改定を行っています。今回なぜこんなに大きな話題になってるのかと言うと、やはり岸田首相の人気が低下してきているので、岸田首相がやることに世論が敏感になっているということが理由だと思います。
(山田)毎年これが行われてるということですから、僕らはもっと注目していいですよね。
(市川)そうですね。民間の賃金が上がっていると言われていますが、実感はあまりないですよね。
(山田)ないですね。
(市川)それでもスーパーに並んでる食品などは確実に高くなってるじゃないですか。賃金の上昇はその動きに合っていない気がします。首相は物価高の対策はしているんでしょうけど、なかなか目に見える形になっていないのに自分たちの給与を上げるのかという批判は国民感情としては当たり前かなと思いますね。
(山田)ゼロから解説していただいてとても勉強になりました。今日の勉強はこれでおしまい!



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































