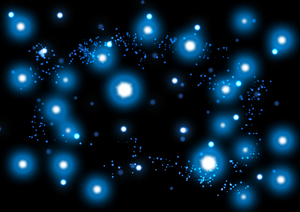「ピロリ菌」をご存知でしょうか。日本では、1960年より前に生まれた人の半数以上が感染しているとされています。そして、一般的には「胃にいる悪い菌」というイメージだと思います。
確かに、ピロリ菌が胃の粘膜に感染することで、慢性胃炎が引き起こされます。そうした炎症が進行すると、胃の粘膜が傷つき、胃潰瘍や十二指腸潰瘍にかかりやすくなります。ピロリ菌感染者の約15%が胃潰瘍や十二指腸潰瘍になると言われています。
また、WHO(世界保健機関)は1994年に、ピロリ菌を「確実な発がん因子」と分類しました。ピロリ菌による慢性胃炎をきっかけに、長い年月をかけ、胃が、がん化しやすい状態になるメカニズムです。
ところが、「ピロリ菌は、善玉菌の面も持つ」と話すのは、静岡県立静岡がんセンターの小野裕之病院長です。ピロリ菌に感染していない人に比べ、ピロリ菌感染者の方が逆流性食道炎や食道がんの発症率は低いことが知られています。

逆流性食道炎は、胃の内容物が食道に逆流する病気で、「胃酸の過剰な分泌が主な原因だが、ピロリ菌は胃酸の分泌を抑える働きをする」と小野病院長は解説します。
また、特に幼少期にピロリ菌に感染すると、喘息やアレルギーのリスクが低下する可能性があることが研究で分かってきました。「ピロリ菌が免疫の過剰反応を防いでいるためと考えられる」(小野病院長)のだそうです。近年、子どもに花粉症が多いのは、今の子どものピロリ菌感染率が数%程度とかなり低いからかもしれない、という見方もできるということです。
ピロリ菌が胃にいるか、いないかは、血液検査でチェックできますが、いると分かった場合、善玉の面も持つピロリ菌でも、退治したほうがよいのでしょうか。
小野病院長は、まず、「胃や十二指腸に潰瘍がある人、胃に不調がある人は除菌したほうが良い。胃がスッキリして食欲が出たという例が多い」と話します。また「20代以下では、胃がんになりにくくするという意味で除菌してもいい」という見解です。

一方、50代以上でピロリ菌がいる人は長年の感染で、すでにがんになりやすい胃ができあがっていると考えられ、症状がないならば、「除菌によって、逆流性食道炎になったり、胃粘膜が再生することで、胃カメラ検査で病変が見つけにくくなったりするので『除菌しないほうがいい』」と小野病院長は考えています。
50代以上で、ピロリ菌に感染している人が、胃がんに気をつけるには、「ピロリ菌除菌ではなく、毎年、胃カメラ検査をするのが有効」(小野病院長)だということです。
(SBSアナウンサー 野路毅彦)



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る