 静岡県民が年400円を負担して荒廃森林を整備する「森の力再生事業」が2025年度で最終年度を迎え、県は今後の在り方を本格的に検討する。タウンミーティングなどを通じて幅広く意見を聴取する方針で、財源となる「森林(もり)づくり県民税」の課税を継続するかどうかが焦点。国税の森林環境税と「二重負担」との指摘もあり、専門家は事業に対する理解醸成の必要性を訴える。
静岡県民が年400円を負担して荒廃森林を整備する「森の力再生事業」が2025年度で最終年度を迎え、県は今後の在り方を本格的に検討する。タウンミーティングなどを通じて幅広く意見を聴取する方針で、財源となる「森林(もり)づくり県民税」の課税を継続するかどうかが焦点。国税の森林環境税と「二重負担」との指摘もあり、専門家は事業に対する理解醸成の必要性を訴える。森の力再生事業は、所有者による整備が困難な人工林の間伐や、災害に遭った森林の復旧などを行う。06年度に始まり、24年度末までに約2万2千ヘクタールの整備が完了した。県民税の負担額は個人が年400円、法人が年千~4万円。税収は年約10億円に上る。
県は「下草や広葉樹が発生し、森林の持つ公益的機能は着実に回復している」と説明。有識者でつくる事業評価委員会も「目的にかなう効果が期待できる」と評価する。一方、豪雨災害やシカの食害による下草の消失など、新たな荒廃も進んでいるという。
県は5月13日から1カ月間にわたり、県内27カ所でタウンミーティングを開催する。森の力再生事業の成果や新たな荒廃森林の状況を説明し、事業への要望や県民税に対する考えを聞く。県民アンケートの結果や関係団体の意見なども踏まえ、今後の方針を決める。
県民税は5年ごとに延長している。国民1人当たり年間千円を課す森林環境税の徴収が24年度に始まってからは初の見直しのタイミングとなる。
県は二つの税の違いについて、県民税が上流域の緊急性の高い森林整備に使われるのに対し、森林環境税は市町が実施する里山や人家近くの間伐や木材利用などに充てられていると説明する。ただ、「違いが分かりにくい」との指摘が根強い上、長引く物価高騰もあって課税の見直しを求める声が強まる可能性もある。
県森林計画課の担当者は県民税について「延長ありきではない」とした上で、「負担感を指摘する意見も予想される。森林環境税との役割の違いや使途を丁寧に説明していきたい」と話す。
■森の力再生事業「知らない」52% 必要性は理解も、負担感
2024年度の県政世論調査によると、森の力再生事業を「知らない」と回答したのは52・0%で、「知っている」の13・1%を大幅に上回った。「聞いたことがあるが詳しくは知らない」は33・0%だった。
森林環境税の徴収が始まったことを踏まえ、森の力再生事業と組み合わせた森林整備について尋ねたところ、約8割が整備の必要性に理解を示す一方、このうち約6割は「負担額が増えるので税の在り方や使途を見直してほしい」と答えた。
森の力再生事業評価委員長を務める静岡大教育学部の小南陽亮教授(森林生態学)は「生物多様性の保全や土砂災害防止といった森林の公益的機能は、身近なこととして実感するのは難しいが、森林を健全な状態に保つことには大きな意義がある」と指摘する。税金を徴収して取り組む以上、県民の理解を得ることは不可欠だとして「学校教育や社会人教育など若い世代に対するアプローチも重要だ」と話した。

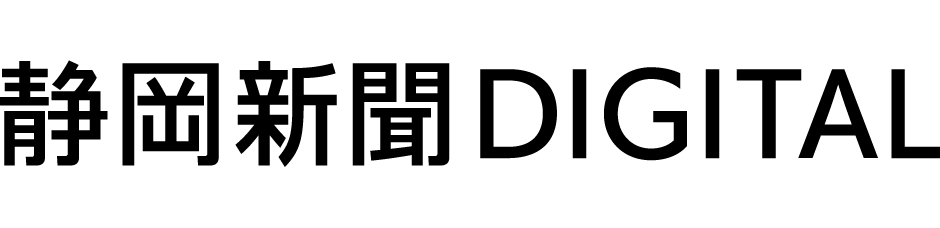

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る






























































