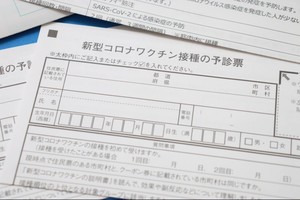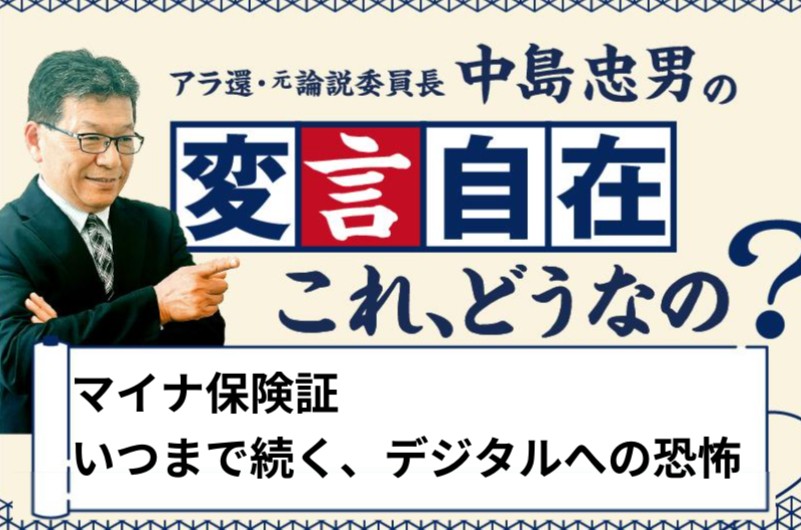 新型コロナウイルスへの医療対応が季節性インフルエンザと同等の扱いになって1年が経過しました。未知のウイルスは脅威で、多くの命が失われました。「三密」の回避や「黙食」を強いられ、生活生業が打撃を被ったのは遠い昔のことではありません。
新型コロナウイルスへの医療対応が季節性インフルエンザと同等の扱いになって1年が経過しました。未知のウイルスは脅威で、多くの命が失われました。「三密」の回避や「黙食」を強いられ、生活生業が打撃を被ったのは遠い昔のことではありません。コロナ禍での教訓の一つはスピード感を欠いた経済対策です。実務を担う自治体の窓口では紙と対面の手続きが煩雑で、支援金などの給付に時間がかかりました。ワクチン接種の手続きもしかり。反省した政府はIT化で行政事務を変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)を強化し、マイナンバーカードを国民の利便性を向上させるインフラ(生活基盤)にすると宣言しました。
私たちに最も身近な制度変更は「マイナ保険証」への移行でしょう。政府は年内に従来型の健康保険証を廃止し、マイナカードに統合する方針です。ところが…。ことはすんなりと進みません。
河野デジタル相「いつまでたっても不安とおっしゃる」
「イデオロギー(思想信条)的に反対される方は、いつまでたっても不安だ、不安だとおっしゃる。それでは物事が進みませんので、きちんとした措置をとったということで進めます」。河野太郎デジタル相は昨年末の記者会見でこう発言しました。記者は、国民皆保険制度の下で保険証を廃止すればマイナカードの事実上の義務化だと批判。各種データ連携でミスが続発しているのに方針を変えないのかと質問しました。河野大臣の「イデオロギー的に反対」との文言は、公正公平を掲げる報道機関にとって受け入れがたい表現でした。河野大臣とメディアとの見解の相違は解消されていません。
私自身はマイナ保険証の活用に賛成です。顕在化した問題点は公表して対処し、国民の人権や権利に支障を及ぼさないように知恵を絞り、デジタル化による行革を進めるべきと考えています。
かかりつけ医や、薬を処方してもらう薬局で、私はマイナ保険証を常用しています。人間ドックで勧められた総合病院での精密検査の手続きでも利便性を実感しました。こうした履歴は将来の診療や突発事態の処置に生かされることを強く期待しています。また、年末の医療費の確定申告は自宅でマイナカードの認証手続きを活用して済ませています。車の買い替え時に住民票の写しや印鑑登録証明書を仕事帰りにコンビニで取得し、手数料は役場の窓口より割安でした。将来、運転免許証の機能も統合されます。
マイナカードで「監視社会が到来」?
コロナ禍への対策で国が全国民に10万円を配った特別定額給付金の申請は郵送対応が軸で、政府予算の成立から1か月しても給付は総世帯の3割ほどで、事務費に約1400億円を要しました。他の給付事業と合わせた事務費の総計が6000億円超との試算もあり、複数のメディアが旧態依然の行政対応を批判しました。なのに、政府が行政事務のデジタル化にかじを切ると、進展のために何をすべきかを論じることより、課題を挙げてデジタル化を“羽交い絞め”にするような報道が続出します。例えば「デジタルに不慣れな高齢者は多い」「いまの保険証が使いやすいと感じる認知症や障害者の人たちもいる」「デジタル対応が困難な小さな診療所は廃業に追い込まれ医療過疎が進む」-など。何より、マイナカードへ個人情報を集約させるべきでないとの指摘は根強いものがあります。皆さんはどう考えますか。
もう四半世紀も前、サッカーの日韓ワールドカップが開催されたころ日本政府は「e-Japan戦略」を打ち出し、世界最先端のIT国家になると宣言しました。ところが戦略は頓挫します。政府が、情報やサービスの基盤を目指し、全国の自治体をつないだ住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に根強い反発があったためです。
住基ネットが管理したのは「氏名、住所、生年月日、性別」の基本4情報で、多機能なマイナカードとは隔世の感がありますが、当時「個人の自由と尊厳を覆す危険をはらむ」「行政があらゆる個人情報を瞬時に収集できるようになれば監視社会になる危険性が高い」と有識者は酷評しました。政府はいま、マイナカードの普及策で捲土重来を期しますが「政府の情報統制が進む」との考え方は根強く残っています。業を煮やす河野大臣が「イデオロギー的反対」と叫ぶゆえんでもあります。
行政事務の「無謬性神話」
スイスの研究所が公表した「2024年スマートシティーランキング」で、東京はコロナ禍前(19年)の世界46位から86位へと急落しました。治安や衛生、公共輸送などは高評価でしたが、行政手続きや役所情報の入手といった点で電子化への評価が極めて低く、全体の順位を押し下げました。また、世界の先進国が加盟する経済協力開発機構(OECD)が発表した23年版「デジタル政府指数」で、日本は調査対象の加盟33カ国中31位でした。各国が電子政府にまい進しているためで、前回順位(19年版)の5位からこちらも急落しました。日本は国際社会の中で「デジタル後進国」と評価されている現実があります。
さて、日本政府の行政改革推進会議の分析にデジタル化の遅れの要因を読み取ることができます。「わが国の行政には間違いを犯してはならない、現行の制度や政策は間違っていないと考える無謬(むびゅう)性神話が存在する」とあります。公務員は波風を立てるのを嫌い、政策にチャレンジせず、社会課題が複雑化しようとも縦割り意識のまま現状に固執しているとの指摘です。
公的事務は、その執行に慎重を期するべきは当然ですが、生じたミスが国民の福祉や権利、人権に影響しないようセーフティネット(安全網)を備えつつ、公務員がデジタル化の進展に歩みを進められるような環境整備と国民の理解が必要だと読み解くことができます。
世の中のデジタル化と隔絶したスローライフのような生活に憧れます。ただ、国の医療、社会制度に支えられて生活生業を営んでいく以上、どこかでデジタル化の恩恵に支えられていることは間違いありません。デジタル化への不信感、恐怖心が過ぎると、この国の成長は危うくなります。
中島 忠男(なかじま・ただお)=SBSプロモーション常務
1962年焼津市生まれ。86年静岡新聞入社。社会部で司法や教育委員会を取材。共同通信社に出向し文部科学省、総務省を担当。清水支局長を務め政治部へ。川勝平太知事を初当選時から取材し、政治部長、ニュースセンター長、論説委員長を経て定年を迎え、2023年6月から現職。



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る