 スマートフォンやタブレット端末といった携帯型デジタル機器の過度の利用などで発症することのある「後天的な斜視」が中高生で増えている。デジタル機器の視聴時間を減らすなど適切な指導を受けると、4割強で斜視の程度が改善したことが浜松医科大医学部の佐藤美保客員教授(元同学部付属病院眼科病院教授)らの調査で判明した。
スマートフォンやタブレット端末といった携帯型デジタル機器の過度の利用などで発症することのある「後天的な斜視」が中高生で増えている。デジタル機器の視聴時間を減らすなど適切な指導を受けると、4割強で斜視の程度が改善したことが浜松医科大医学部の佐藤美保客員教授(元同学部付属病院眼科病院教授)らの調査で判明した。国立成育医療研究センター眼科の仁科幸子診療部長らの協力で、5~35歳の「後天共同性内斜視」の患者194人を調査した。患者は16歳をピークに中高生(13~18歳)が多く、デジタル機器の使用時間は年齢が上になるに従って延びる傾向にあったという。
調査では、1日のデジタル機器の視聴時間が小学生以下で60分以上、中高生以上で120分以上の人を「過剰使用群」に分類。30センチ以上距離を取ってデジタル機器を使用する▽30分の視聴後に5分間休憩する▽小学生以下は1日の使用を60分未満、中高生以上は120分未満にするーといった適切利用を同グループに指導した。
グループの44%は3カ月後、斜視の程度に関する「斜視角」が減少する改善が見られ、完全に治癒に至った人も6・4%いた。
佐藤教授は「デジタル機器の使用方法の改善で治癒するのはごく軽症時に限られる。視機能が未熟な小児は特に早期発見、早期治療が望まれる」と話した。
<メモ>後天共同性内斜視 生まれつきではないが、デジタル機器の過度利用などをきっかけに両眼の視線がそろわず、視線が内側に寄る。物が二つに見えるなどの症状がある。手術や「ボツリヌス注射」で治療できるが、生活習慣などの影響で再発する場合もある。

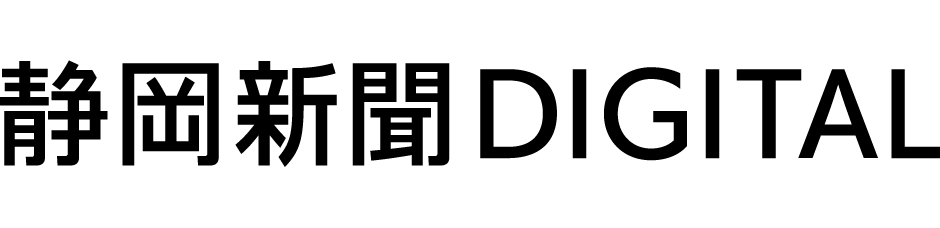

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る






























































