 受け入れ先を見つけるのに時間がかかる「救急搬送困難事案」が多発し、不安定な医療体制の改善が求められている富士市。「医師や看護師ら医療人材不足」「重篤な患者を診る3次救急病院がない」「不明確な搬送基準」といった複合的な要因が絡み合い、長年の地域課題として顕在化している。解消に向け、市と医療機関、消防などは2025年度、多方面から救急医療体制の強化に乗り出した。中核を担う市立中央病院の建て替えを計画し、中長期的な視点での対策も進める。
受け入れ先を見つけるのに時間がかかる「救急搬送困難事案」が多発し、不安定な医療体制の改善が求められている富士市。「医師や看護師ら医療人材不足」「重篤な患者を診る3次救急病院がない」「不明確な搬送基準」といった複合的な要因が絡み合い、長年の地域課題として顕在化している。解消に向け、市と医療機関、消防などは2025年度、多方面から救急医療体制の強化に乗り出した。中核を担う市立中央病院の建て替えを計画し、中長期的な視点での対策も進める。■「1次」輪番体制導入で一定の成果
静岡県内市町で3番目に多い人口約24万5千人を抱える富士市の医療現場では、搬送先が決まるまでに照会6回以上または30分以上かかる「630事案」が喫緊の課題。市と市医師会は24年、平日の朝昼夕の時間帯に医療機関が順番で、主に入院治療の必要がない患者を受け入れる1次救急の輪番体制を導入した。同年上半期(1~6月)の富士医療圏(富士、富士宮市)の630事案発生は186件で前年同期より約3割減り、一定の成果を上げた。一方、静岡市の同時期の21件と比べると、約9倍も多く対策が十分とはいえない。
現状に強い危機感を持つ富士市は25年度、民間病院の協力を得て、重症患者を受ける「2次救急」の医療機関を4病院に倍増する。これまで市立中央病院と川村病院(中島)が担っていた2次救急の輪番制に、新富士病院(大淵)と富士整形外科病院(錦町1丁目)が加わる。新たに担う2病院は当初の半年、月に1回の参加で、対象患者も限定するという。
70歳以上の内外科患者を引き受ける新富士病院の木島金夫院長(67)によると、医師や看護師の配置などを模索中。将来的には週1回の担当を目指す方針で「職員にとって誇れる仕事になる。まずは挑戦し、最適な運営方法を見つけたい。病院の強みを生かして地域医療の力になれたら」と意気込む。
日々多くの患者を診る市立中央病院は、人材確保に力を入れる。病院に常勤の救急救命士を置き、医師や看護師の負担軽減につなげる。東京慈恵会医科大に派遣を依頼する救急専門医は1人から2人に増やした。搬送時間短縮や受け入れ可能な患者数の増加を狙う。小長井義正市長は「全国的に医師不足が加速する中、特に富士医療圏は医師少数区域とされている。大学との連携を強め、医師に勤務を希望してもらえるような環境を整備したい」と強調する。
市は2次救急医療機関への委託料を含む救急医療事業費として、3億4800万円を25年度当初予算に計上。常勤の救急救命士と週2回派遣される救急専門医の人件費にも約1100万円を充てた。24年度まで保健医療課長を務めた後藤剛・資産経営課長(57)は「医療圏全体でバランスを取りながら負担を分散し、安定した医療体制を実現できれば」と期待する。
各機関が役割を分担し、地域医療の底上げを図る。
■市立中央病院建て替え、31年開院目標 救急科新設で「3次」望む声
富士医療圏で最大規模を誇り、救急医療を支える「圏域最後のとりで」として、24時間365日体制で患者を受け入れる富士市立中央病院。市は老朽化に伴い、2031年10月までの新病院開院を目標に現在地での建て替えを進める。新病院はより質の高い救急医療を提供するため、市内初の「救急科」を新設する方針で、将来的な3次救急指定病院への移行も視野に設計を工夫する。
さまざまな患者の初期診療にあたる救急科には、専属スタッフを配置。手狭になっている救急外来の診察室を増やし、緊急入院受け入れ専用病棟や手術室の整備も計画する。各専門科と連携し、迅速で適切な治療の提供に努める。
新病院は集中治療室と高度治療室、診察スペースなどを同じフロアに置く。現行と同じ2次救急として開院するが、3次救急への機能転換もレイアウト変更で対応でき、大がかりな増改築は不要という。
近隣市への搬送を余儀なくされている重篤患者もいるため、富士市議会などから圏域初の3次救急誕生を期待する声があがる。一方で、新病院建設準備室の担当者は「最大の課題は医師や看護師らの人材確保」と指摘する。
■緊急度判定の共通ルール導入 対応可能病院を早見表に
富士医療圏の救急隊と医療機関は4月中に、救急現場で患者の容体や搬送先の明確な判断基準となる「プロトコル」の運用を始める。患者の緊急度を判定する共通のルールを導入し、救急搬送困難事案の改善を図る。
関係機関でつくる富士地域救急プロトコル策定委員会によると、搬送困難事案はさまざまな要因で発生している。主には「救急隊が2次救急相当と判断して照会しても、病院側から1次救急と指摘される」「容体を説明する救急隊の伝え方が曖昧で、やりとりに時間がかかる」などが挙げられるという。
プロトコルでは、搬送側と受け入れ側の認識の違いで時間的ロスが生じないよう、容体ごとに対応可能な病院を早見表でまとめた。極めて緊急度の高い患者の場合、照会3回または20分以内に搬送先が決まらなければ、医療圏外の医療機関に照会することも決めた。

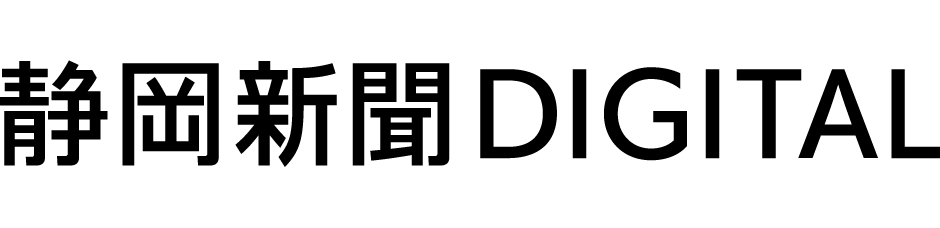

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る





























































