 近年の急速な出生減を受けて、静岡県内でも分娩(ぶんべん)対応を中止する医療機関が増えている。物価高や人件費上昇などのコスト増も伴って厳しい経営が続く中、国が検討する出産費用の保険適用の制度内容次第では有床産科診療所の減少は加速し、地域の周産期医療体制の崩壊が懸念される。現場からは、国に対して持続可能な体制構築に向けた丁寧な議論とともに、継続的な支援を求める声が上がっている。
近年の急速な出生減を受けて、静岡県内でも分娩(ぶんべん)対応を中止する医療機関が増えている。物価高や人件費上昇などのコスト増も伴って厳しい経営が続く中、国が検討する出産費用の保険適用の制度内容次第では有床産科診療所の減少は加速し、地域の周産期医療体制の崩壊が懸念される。現場からは、国に対して持続可能な体制構築に向けた丁寧な議論とともに、継続的な支援を求める声が上がっている。「分娩数が減れば減収になるが、24時間体制の人件費や施設維持費は抑えられない。地域から分娩施設がなくなるのは時間の問題」。上山レディースクリニック(伊東市)の上山和也院長が危機感を示す。年間220件前後の分娩数は昨年度1割減に。出生数が減少し続ける社会状況では、今後も減少が見込まれる。
県によると、県内の分娩施設は80施設(2月時点)で、2020年度末と比較して11施設減少した。賀茂地域では2月以降、実質出産ができなくなった。静岡市内の有床産科診療所はこの2年で7施設から4施設に減り、さらに1施設が今夏までに分娩を終える。
有床産科診療所は国の出産育児一時金50万円が主収入となり、分娩数の減少は経営を直撃。地方は人材確保も難しく、上山レディースクリニックは地方勤務がメリットとなる待遇で首都圏の助産師も雇用する。上山院長は「一時的な補助金よりも、出産一時金や(保険化される場合は)保険点数を上げる継続的な対応がないと、地方での事業継続は厳しい」と訴える。
国は26年度をめどに出産費用(正常分娩)の保険適用導入を検討している。制度の中身は示されていないが、依藤産婦人科医院(静岡市葵区)の依藤崇志院長は「安全に診られるお産の数は決まっている。保険化で安く見積もられたら多くの産科が赤字を続けてまでやらない」と指摘。その上で「少子化対策として、妊婦の負担軽減と地域で出産ができることは両輪のはず。分娩施設が急減したら困るのは妊婦」と国に丁寧な議論を注文する。
24時間体制で高度医療を担う総合周産期母子医療センターの指定を受ける順天堂大付属静岡病院(伊豆の国市)産婦人科の田中利隆科長は「医師の働き方改革もあり、病院の人繰りは大変。(リスクの低い分娩に対応する)一次施設が減少し、人手不足の地方病院ほど負担が増すだろう」と不安は尽きない。
■ハードル高い集約化 関係者の合意形成必要
国は周産期医療体制について、基幹施設を中心に医療機関や機能の集約化・重点化を進めている。少子化や産科医の偏在、医師の働き方改革などを背景に集約化は避けられない状況ではある一方で、公的病院の運営・経営母体はさまざま。県内のように病院によって医師の派遣元大学が多岐にわたる地域にとって、集約化は容易ではない。
掛川市の中東遠総合医療センターと磐田市立総合病院は1月から、毎週金曜の診療時間外の産科救急当直を当番制にした。医師の働き方改革に対応しながら、中東遠地域の持続可能な分娩(ぶんべん)体制を維持していくため、関係機関が3年ほどの議論を経て実施を決めた。県地域医療課は「本県の公的病院は多くの大学が絡み、自治体の思いもある。持続可能な体制構築に向けて、関係者間で合意形成を図りながら進めることが必要」と話す。
集約化・重点化では、ハイリスクではない分娩は基幹病院以外の医療機関で対応し、分娩を扱わない医療機関は妊婦健診や産前産後ケアを実施するなど、施設間の連携や役割分担を促している。
<メモ>出産費用の保険適用の検討は、国が2023年に閣議決定したこども未来戦略で掲げ、24年から検討会で妊娠期や産前産後に関する支援の強化と併せて議論している。子どもを産んだ人に公的医療保険から支払われる出産育児一時金は23年度、42万円から50万円に増額された。同年度の正常分娩(ぶんべん)の都道府県別平均出産費用は、本県が48万5857円。最も高い東京都は62万5372円、最も低い熊本県は38万8796円と地域差が大きい。
人口動態統計によると、23年出生者の出生場所は病院が54%、診療所が45%で、この割合は近年変わっていない。日本医師会総合政策研究機構が公表した産科診療所の調査結果では、同年度に191医療法人の42・4%が赤字となった。

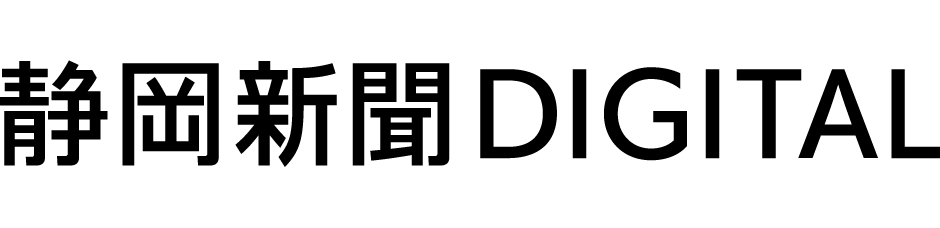

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る






























































