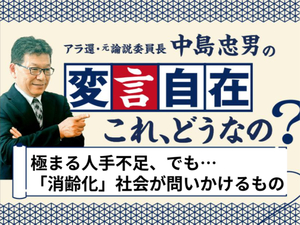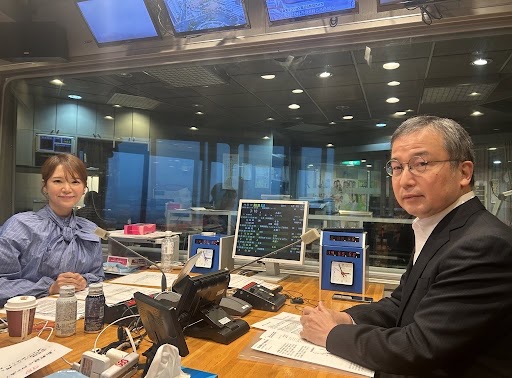
(橋本)厚生労働省が発表した人口動態統計の速報値によると、2023年に生まれた赤ちゃんの数は、外国人を含め、過去最少の75万8631人でした。初めて80万人を割った2022年から5.1%減り、少子化が一段と進みました。静岡県は7.4%減の2万171人でした。
(内山)また少子化が進んでしまったんですね。
(橋本)厚労省が今年1月に2023年1月から11月までの11カ月間の人口動態統計を発表していて、このときに、既に2023年1年間で出生数が過去最低になるのではないかと予想されていました。
出生数が最少だっただけでなく、高齢化の進展で2023年は死亡数が過去最多の159万人になりました。そうすると、死亡数と出生数の差に当たる83万人余りが人口の自然減ということになります。その幅も過去最大になりました。
日本政府も地方自治体も、近年は少子化対策が喫緊の課題だということですごく力を入れていますが、なかなか歯止めがかからない状況です。
(内山)静岡もかなり減っているんですね。
(橋本)2月27日付の静岡新聞の記事にもありましたが、静岡は7.4%減。国全体が5.1%なので、それを大きく上回る減少率ということになります。厚労省の国立社会保障・人口問題研究所が昨年末に発表した将来推計人口では、静岡県の人口は2020年の363万人から2050年に282万人と約80万人減るとされていましたが、これを裏付ける、場合によってはさらに減るかもしれないというような数字なのかなと思います。
(内山)出生数が過去最少で75万8631人ということでしたけど、多かった頃というのは、どのぐらいだったんですか。
(橋本)日本の出生数の統計は1899年から始まっていますが、それ以降で出生数が最も多かった期間が、1947年から49年までで、戦後の第一次ベビーブームと言われています。団塊の世代として知られていますが、この3年間は毎年260万人台でした。この世代がちょうど75歳以上になるということで、2025年問題と言われて注目されています。
その団塊の世代の皆さんのお子さんが生まれたのが、第2次ベビーブームということで、団塊ジュニア世代と呼ばれます。1971年から74年生まれで、年間200万人余りでした。以降はほぼ右肩下がりで、第3次ベビーブームと言えるような出産数がぐっと増える時はありませんでした。
それでも2015年までは100万人いたんですが、2016年に100万人を割り込んで97万人になり、2022年には統計開始以来初めて80万人を割り込んだということで大変話題になりました。75万人というと、ピーク時の約260万人の3割にも満たないという状況なので、いかに減っているかがわかるかと思います。
(内山)ここ10年で、ぐっと減っちゃったんですね。
(橋本)第2次ベビーブーム以降は右肩下がりですが、ここに来てまたちょっと減り方が加速してるような感じかなと思います。
未婚化、晩婚化…コロナの影響も
(内山)何が出生率低下の要因なんですかね。(橋本)背景としては、未婚や晩婚化があります。2023年は婚姻数も90年ぶりに50万組を割り込み、戦後最少ということでした。逆に19万組近くが離婚して、これは前年より増えているという状況ですので、子供も生まれにくくなっています。
先ほどの研究所の将来人口推計では、数年前の推計で、出生数が76万人を割り込むのは2035年と予想されていたんですが、これよりも12年早いペースということです。未婚化、晩婚化に加えて、新型コロナが流行したことで、出生数の減少に拍車がかかったというようなことも指摘されてます。
(内山)このままですと、どういうことに影響が出てくると考えられますか?
(橋本)最も懸念されるのは経済への影響です。2024年問題と言われていますが、もうすでにさまざまな業種で人手不足が顕在化してますよね。それがさらに多くの業種に起こったり、あるいは地域で人手不足が深刻になっていったりすることが考えられます。
物を買う人たちが少なくなっているので、日本という市場がどんどん縮小していくことにもなります。経済成長率も低下していく恐れがあるということです。
先日、2月に日本のGDPがドイツに抜かれて、今までの3位から4位に転落したという話が大きなニュースになりました。いずれインドにも抜かれて、5位に転落することが予想されていますし、市場が小さくなるということは、企業の業績やそこで働く人の賃金にも影響する可能性があるといえます。
社会的に税収が厳しくなると、行政サービスが低下するほか、高度成長のときに作って古くなったインフラを直さなくてはならなくても、予算が足りなくて直せないということも考えられると思います。
(内山)悪循環ばっかりです。まだ、影響はありますかね。
(橋本)行政サービスの低下にも関係しますが、地域の担い手の方がどんどん少なくなってきているので、コミュニティーが維持できなくなったり、地域の行事が行えなくなったりしています。
能登半島で地震があって、その後の復興がなかなか進まないということがあります。被災した地域もすごく過疎化が進んでいるので、復興を担ってく人たちも高齢化していたり、人数が少なかったりして、なかなか進まないという状況です。同じようなことが日本のあちこちで起こってくる可能性があると思われます。
(内山)聞いていて、ちょっと悲しくなってきてしまったんですけど、何か歯止めをかける方法というのはありますか。
(橋本)岸田首相は「異次元の少子化対策」と言って、力を入れようとしています。何とか子供を増やさないといけないということで、財源をどうするかが今問題になっています。大概の地方自治体は、人口減対策、少子化対策を政策の目玉にしてるんで、どこも力を入れていますが、なかなか思うような結果が出ていません。
子育て環境を整え、子育て世代に経済的な支援をするといった少子化対策というのは重要ですが、少子化を止める、逆に子供を増やすということにはなかなか繋がらないのだと思います。
米シカゴ大学の教授で、1992年にノーベル経済学賞を取ったゲーリー・ベッカーさんが提唱した理論で、先進国で少子化が進む理由を説明する学説があるんですけれども、貧しい国とか時代では、その子供は親を助ける「生産財」だけれど、国が豊かになっていくと、贅沢な「消費財」に変わると言っています。
貧しい国では子供が働きますよね。農業だったら農業を手伝い、親を助けて生産に役立つんですが、豊かになってくると子供を働かせるということもなくなりますし、逆に教育にものすごいお金がかかるので、子供もたくさんは持てないという状況になります。そうすると、自然とお子さんが減っていくということが指摘されています。
そういう理論を考えても、日本はもう豊かな国になっているため、これを逆転させるというのは難しいんじゃないかと思います。
先進国で、例外的に人口が増えているのは米国です。それは移民がすごく入ってくるからです。移民が入って来るおかげで人口は増え、経済も成長しているという状況です。米国は合計特殊出生率は下がっていますが、移民の増加がそれを補っているような状況ということです。
ただ日本の場合は、政府は「移民政策は日本にありません」と言っており、積極的に移民を受け入れる政策をとっていません。反対する方も多いので、すぐに移民を受け入れましょうという話にはならないと思います。
人口減が目に見えているので、経済団体などが移民を受け入れることを議論すべきだと主張していたりもするんですが、その議論自体にも時間がかかります。
ですので当面は、子育て支援を充実させ、出生数の減り方を少しでも緩やかにしていくことができることなのかなと思います。
男性が育児に参加しやすい社会に

(内山)具体的にはどういうところですか。
(橋本)一つは、男性の子育て参加が盛んな国は出生率が高いということが統計的にあるようです。今の日本はまだ、男性の育休取得率が低いので、男性も当たり前に休みが取れて、育児参加するということがもっと盛んになっていけば良いと思います。また、お子さんの声がうるさいというような苦情があって遊び場がなくなってしまったり、電車でベビーカーを乗せているとちょっと白い目で見られたり、というようなこともありますよね。そういう社会の雰囲気を変えていくことも重要かなと。
もちろん保育施設の充実など、今までやってきたことをさらに強化していくというのも重要で、経済的な支援は欠かせませんが、子育てに対する社会の考え方や見方を徐々に変えていくということも大切かと思います。
(内山)個人的には全国平均より静岡県の出生率が減っているのがショックだったんですけれども、昔みたいに、地域で子供を育てることも大切なのかなと思いますね。今日の勉強はこれでおしまい!



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る