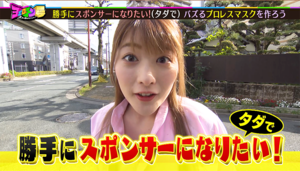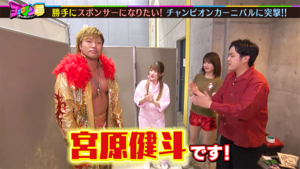出会いのきっかけは一冊の本
(山田)今日はプロレスラーのアントニオ猪木さんがテーマですね。(橋爪)猪木さんが10月1日に亡くなられてもうすぐ1年。9月19日付の静岡新聞教養面に、親交があった直木賞作家村松友視さんのインタビューを掲載しました。
(山田)昨年、スポーツ番組を担当していたので追悼コーナーをやったのを覚えてます。
(橋爪)村松友視さんは東京生まれなんですが、高校時代まで旧清水市に住んでいて、城内中、静岡高を出ていらっしゃいます。
(山田)僕の出身中学の大先輩ですね。
(橋爪)新聞に掲載したインタビューは2000文字ぐらいあり、静岡新聞の記事としてはかなり長いほうでした。ただ、内容が濃くて紙面では紹介しきれない話もたくさんあったので、Web版として倍ぐらいの分量に仕立てた別の記事も出稿しました。「村松友視」「静岡新聞」というキーワードで検索していただければ出てくると思うので、リスナーの皆さんにもぜひ読んでいただければと思います。
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1317910.html
村松さんは1980年に「私、プロレスの味方です」で作家デビューしています。当時は中央公論社という出版社で、編集者として働いていました。この本がベストセラーになり同年、本を読んだ猪木さんに出会っています。それ以来、猪木さんが亡くなる2022年まで、42年にわたってずっと親しくしていたそうです。インタビュー記事は、プロレスラーというスポーツ選手像にどうフォーカスしているかという、村松さんの作家としての視点も分かる内容になっています。
(山田)橋爪さん自身は猪木さんを知っていましたか。
(橋爪)僕はずっと詳しくは知らないできたというのが正直なところです。1990年ごろから2000年代後半にかけて、かなり熱心にプロレスや格闘技を見ていたんですが、猪木さんは既に一線を退いていました。柔道家の小川直也さんを操る総帥として、格闘技界とプロレス界をまたにかけて活躍されていたという印象が強いです。でも、猪木さんに関する書物や記事は膨大に出ているので、そういうものを一つ一つ読み込んでいって彼の歴史みたいなものはかなり頭の中に入っていますし、映像も見ました。
1990年代は、いわゆる「活字プロレス」が花ざかりでした。そこにどっぷりはまった世代でした。試合の奥底にあるレスラーそれぞれの思惑やドラマを取り上げる活字プロレスは、他のスポーツジャンルの試合レポートとは違う書き方をするんです。その時期に村松さんの「私、プロレスの味方です」も読みました。活字プロレスの原点が村松さんであるという言い方をしても差し支えないと思います。
昨年10月に猪木さんが亡くなったとき、村松さんに取材を申し込んだんですが、「心の整理がつかない」ということで叶いませんでした。1年を迎えるタイミングで再びお願いしたところ、今回は快諾してくださいました。
(山田)それで新聞に収まらないぐらい語ってくれたんですね。
(橋爪)村松さんはプロレスファンのことを「プロレス者(もの)」と呼びます。私のこともプロレス者として認めてくれたようで嬉しかったです。
村松さんは「私、プロレスの味方です」を出版した2年後に「時代屋の女房」で直木賞を受賞します。ただ、最初の本を出したときは出版社の社員だったのでほぼ無名でした。一方、猪木さんは当時、すでにモハメド・アリと試合を行い、新日本プロレスの社長も兼ねるトップレスラーでした。
インタビューの中でも触れていますが、猪木さんはそれでも対等の立場で接してくれたそうです。村松さんは今でもそのことを覚えていて、猪木さんの姿勢に感銘を受けたと語っています。
2人の最後の会話は「詩集のタイトル」
(山田)僕が中学1年のときの先生が猪木さんの大ファンで、「道」という詩を教わりました。猪木さんの活躍はリアルタイムでは見ていないですが、この詩は自分の中で大切にしています。(橋爪)引退試合のあとに披露した「行けばわかるさ」ってやつですね。
(山田)はい。
(橋爪)猪木さんは後年、詩人として自覚があったようです。亡くなる数日前に村松さんと最後の会話を交わしたときも、次の詩集のタイトルをどうするかという話だったそうです。
(山田)へえー。村松さんは「私、プロレスの味方です」の中で猪木さんについても書いているんですか。
(橋爪)書いてます。猪木さんには「過激なプロレス」という代名詞のようなものが付いてます。アナウンサーの古舘伊知郎さんは実況で「過激なセンチメンタリズム」と連呼していました。ただ、過激という言葉を猪木さんのプロレスに当てたのは、村松さんが最初なんですよ。
(山田)そうだったんですね。
「ルールこそ八百長」の真意とは?

(橋爪)プロレスは八百長だという言われ方をすることが多くて、当時も今も言う人はいますが、村松さんは本の中で「ルールこそ八百長である」という言い方をしています。つまり、(通常のスポーツの)ルールというのはそもそもしつらえられたもので、「あらかじめ定められた八百長である」と語っています。目からウロコですね。
他にも「プロレスはクソ真面目に見よう」とも言っています。勝負が決まった瞬間に、勝敗を見るのではなく、プロレスラー個人を自分の中に読み取るという見方を提唱しています。
(山田)ちゃんとプロレスを勉強したくなりました。実際に見たり、何人かの選手とも話したりしたことがありますが、理解できていない気がしてきました。
(橋爪)猪木さんがどういう人物かという部分は、本の中の一節を少し読み上げますね。
「カール・ゴッチの、機械のように精密で強力なプロレス、ルー・テーズの柔軟性のある鮮やかなプロレス、そして力道山のように火の玉となって壁を突き破る熱気あるプロレス……。これら最高峰の要素がミックスされ、アントニオ猪木の肉体から放射される。これをまた何万もの『観客』の眼玉が射返すという構造のすべてを含めて、アントニオ猪木流『過激なプロレス』は成り立っているし、また世間に対して過激に突き進んでゆくのである」
<「合本 私、プロレスの味方です」(ちくま文庫)から引用>
猪木さんのプロレスはこうとしか言いようがないです。
(山田)もう一つお知らせがあるんですよね。
(橋爪)取材の準備をしていたら、猪木さんの映画が10月6日から上映されるという話が入ってきました。「アントニオ猪木をさがして」というタイトルなんですが、ドキュメンタリー部分とドラマ部分が混在している映画だと聞いています。プロレス好きの芸人・有田哲平さんや俳優の安田顕さんらがコメントしています。ナレーションは福山雅治さん。プロレスラーでは藤原喜明さん、藤波辰爾さん、棚橋弘至さん、オカダ・カズチカさんが出演し、猪木さんの生涯を追っているということのようです。
(山田)楽しそうですね。今日の勉強はこれでおしまい!





 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る