 原子力災害時、中部電力浜岡原発(御前崎市佐倉)の緊急防護措置区域(UPZ、5~31キロ圏内)の全住民に即時避難はせず屋内にとどまることを求める「屋内退避」。被ばくの低減に有効とされるが、能登半島地震では住宅の倒壊が相次ぎ、複合災害での屋内退避の実効性に課題を残した。原子力規制委員会は屋内退避の運用に関する報告書を3月にまとめたが、東日本大震災では高齢者施設などの避難に混乱があっただけに、UPZ圏の市町では要配慮者の対策への懸念は根強い。放射線防護対策について国の補助対象拡充を求める市町も多い。
原子力災害時、中部電力浜岡原発(御前崎市佐倉)の緊急防護措置区域(UPZ、5~31キロ圏内)の全住民に即時避難はせず屋内にとどまることを求める「屋内退避」。被ばくの低減に有効とされるが、能登半島地震では住宅の倒壊が相次ぎ、複合災害での屋内退避の実効性に課題を残した。原子力規制委員会は屋内退避の運用に関する報告書を3月にまとめたが、東日本大震災では高齢者施設などの避難に混乱があっただけに、UPZ圏の市町では要配慮者の対策への懸念は根強い。放射線防護対策について国の補助対象拡充を求める市町も多い。重大事故時、原発から半径5キロの予防的防護措置区域(PAZ)圏内では、避難が難しい要配慮者を除く住民は即時避難するが、UPZの全住民は原則として自宅などで屋内退避する。東京電力福島第1原発事故で、避難を強いられた高齢者らの災害関連死が多く発生したことを教訓とした。
PAZとUPZを抱える牧之原市。PAZ圏の相良原子力防災センターは放射性物質を除去し、建物内の気圧を高める陽圧化装置や非常用電源を備える。要配慮者らの屋内退避先となる。6億円を投じて2021年に完成。全額を国の補助でまかなった。
一方で、同市のUPZ圏には放射線防護対策をした施設はない。「原発に近いPAZが優先されるのはやむを得ないが、屋内退避が原則のUPZでも線量が高ければ避難が必要になる。その場合でも入院患者や要配慮者はすぐには避難させられず、屋内退避が続くことになる」。市危機管理課の吉添所課長はUPZ圏でも医療機関などの防護化の必要性を強調する。ただ、事業費を踏まえると、市単独では現実的ではない。
静岡新聞社が浜岡原発周辺の首長に実施したアンケートでは、UPZ圏の9市町が複合災害での屋内退避に課題があると回答。「要配慮者のための放射線防護施設が必要」(藤枝、袋井)、「10キロ圏外も防護対策の補助を」(菊川、島田など)との意見が目立つ。掛川市は「家屋倒壊などにより自宅で退避できない人が多くなると、退避先が不足する可能性がある」と指摘した。退避が長期化した場合の備蓄、物資の確保や要配慮者への支援継続を懸念する声もあった。
これまで屋内退避の運用は原子力災害対策指針で明確にされていなかった。規制委は、解除の判断を退避開始から3日後とするなどの整理を行い、今後指針に反映させる。退避を継続する場合も、避難に切り替わったとしても要配慮者対応をはじめとする課題は残る。担当者は「残された課題は関係省庁と連携して検討を続ける」とした。

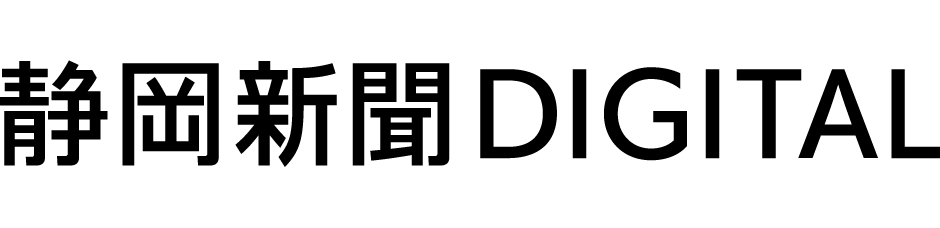

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る































































