 駿河湾フェリーが約3カ月ぶりに運航を再開した。1月の定期点検で岸壁と船をつなぐ台船の損傷が見つかり運休していたが、ターミナルの移転で乗船が可能になった。ただ、当面は車を積めない状況が続く。県は徒歩や自転車で楽しめる行程や、乗船時間の満足度向上につながる仕掛けの検討を急ぐ。県がゴールデンウイークを前に21日実施した「県道223号 清水―土肥の日帰り旅プラン」の実証実験に同行した。
駿河湾フェリーが約3カ月ぶりに運航を再開した。1月の定期点検で岸壁と船をつなぐ台船の損傷が見つかり運休していたが、ターミナルの移転で乗船が可能になった。ただ、当面は車を積めない状況が続く。県は徒歩や自転車で楽しめる行程や、乗船時間の満足度向上につながる仕掛けの検討を急ぐ。県がゴールデンウイークを前に21日実施した「県道223号 清水―土肥の日帰り旅プラン」の実証実験に同行した。青空が広がり汗ばむ陽気の中、車で清水港へ向かった。隣接する清水魚市場河岸の市の駐車場は満車で、JR清水駅東口駐車場に回った。チケットを購入して船に乗り込むと、河岸の市のにぎわいとは裏腹に乗客はまばら。平日の利用者確保の難しさを実感した。
出航してすぐ、左舷側には雪化粧した富士山が顔を出し、船上ならではの眺望を満喫できた。ただ、デッキにある売店は平日休業。90分弱の船旅はやや手持ち無沙汰だった。
土肥港で下船し、海沿いの歩道を歩くこと約15分。古民家を改装した宿に到着し、併設のカフェのジェラートやコーヒーで一息ついた。何度も訪れているという県観光振興課の担当者は「第1便で来て、パンを食べるのがお勧め。普段とは違う朝を楽しめる」と教えてくれた。
次に向かったのは土肥金山。一行は砂金取りを体験した。400年以上前の伊豆最古の手堀り坑道とされる「龕付(がんつき)天正金鉱」にも立ち寄った。山の神を祭った最深部の「龕」には厳かな雰囲気が漂い、新たなパワースポットとして発信する価値を感じた。
「船旅は非日常」。参加者の1人がそう答えた。確かに船が汽笛を鳴らして出航する瞬間は高揚感に包まれる。思わず岸壁の人たちに手を振ってしまった。
土肥港側は交通手段の乏しさが課題になっているが、徒歩圏内にも観光資源がそろい、車がなくても楽しめた。一方、船内施設や乗船中の娯楽の充実、清水港側の駐車場確保など、改善が必要な点も多い。
駿河湾フェリーは運航再開と同時にターミナルがJR清水駅直結のエリアに移転し、利便性向上による利用者増への期待もある。赤字が続き、廃止すべきとの議論がたびたび起こる中、経営改善戦略で掲げる「27年度の収支均衡」の達成に向け、実証実験を踏まえた抜本的な対策が急務だ。

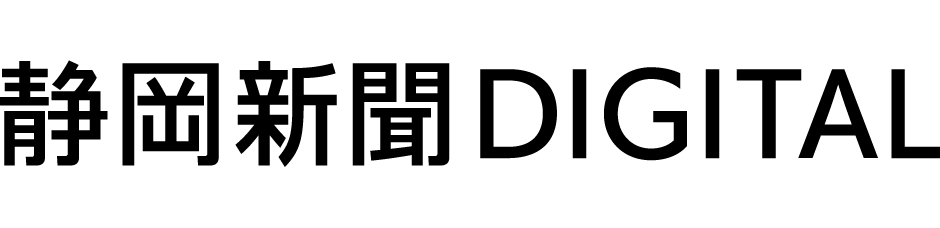

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る






























































