 静岡県内の中小企業や自治体に、奨学金の返済を後押しする動きが広がってきた。大学生の約半数は奨学金を利用しているとされ、長引く物価高騰もあって返済に苦慮する若者は少なくない。人材獲得競争が激しさを増す中、福利厚生を充実させて働きやすい環境を整え、県内への就職や定着につなげる。
静岡県内の中小企業や自治体に、奨学金の返済を後押しする動きが広がってきた。大学生の約半数は奨学金を利用しているとされ、長引く物価高騰もあって返済に苦慮する若者は少なくない。人材獲得競争が激しさを増す中、福利厚生を充実させて働きやすい環境を整え、県内への就職や定着につなげる。藤枝市の藤和乾物は2024年秋、従業員向けに奨学金返還支援制度を導入した。月1万5千円、年18万円を上限に10年間サポートする。佐藤文彦社長(46)は「会社で働く仲間の経済的、心理的な負担を減らし、働きがいを感じてもらいたかった」と狙いを語る。
同社で働く川島京介さん(30)は学生時代、日本学生支援機構の奨学金を利用し、200万円近く借りていた。37歳まで毎月1万円余りを返済する予定だったが、現在は会社が肩代わりする。「心にゆとりができ、モチベーションも上がった。資格の勉強や自己投資にお金をかけたい」と充実感をにじませた。
沼津市の佐藤建設も24年4月に取り組みを始めた。入社1年目から10年目は最大で年12万円、11~20年目は年24万円を支援する。佐藤宗徳社長(56)は「従業員を応援するとともに、人材確保につなげたい」と期待し、就職説明会などを通じて制度をアピールする。
日本学生支援機構の代理返還制度を利用する企業は増加し、24年10月末時点で全国2587社に上る。福利厚生や待遇面を基準に会社を選ぶ学生が増えているといい、担当者は「採用力向上や雇用安定につながる」と指摘する。
若者の流出に悩む自治体も対応を進める。県は25年度、市町や企業と連携して新たな奨学金返還支援制度を創設する。「他県に後れを取っていたが、ようやくスタートラインに立てる」と県幹部。県外に進学した学生のUターン就職率が落ち込む中、県内就職を選択肢に入れてもらい、人手不足に苦しむ中小企業の人材確保を後押しする。
県によると、県内では10市町が独自の支援制度を設ける。20年度から取り組む湖西市は「若者の移住促進に一定の効果があり、企業からも評価する声が上がっている」としている。
■借入平均は344万円 返済「不安」7割
労働者福祉中央協議会が2024年6月に実施したアンケートによると、日本学生支援機構の貸与型奨学金利用者の借入総額は平均344万9千円。返済を「不安」と感じている人は71・0%、「苦しい」は44・3%に上った。
返済が生活設計に及ぼす影響を尋ねたところ、「日常的な食事」は47・5%、「結婚」44・3%、「出産」38・2%、「子育て」37・0%などとなった。
自由記述では教育費の負担が大きいとの指摘が多く、「子どもには同じ思いをさせたくない」「奨学金返済がなければもっと楽しく生きられた」などの意見もあった。

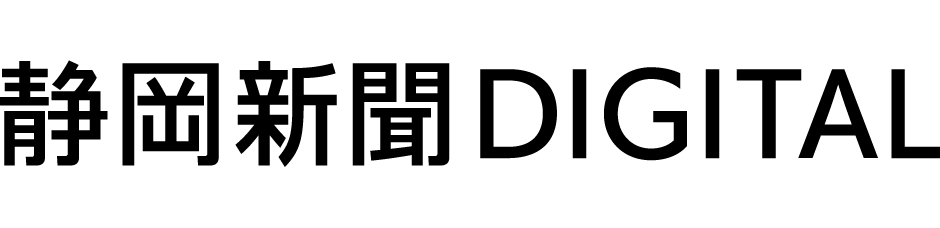

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る






























































