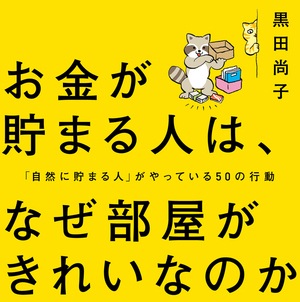年末調整は節税のチャンス!
年末調整の時期ですね。各種控除証明書が手元に届いて準備を始めているという方も多いと思います。会社員にとっては年に一度の節税のチャンスです。年末調整について改めて勉強していきましょう!今回はファイナンシャルプランナーの田中健夫さんに「鉄崎幹人のWASABI」パーソナリティの鉄崎幹人とSBSアナウンサー大槻有沙がお話をうかがいました。
そもそも「年末調整」とは?
田中:年末調整とは 1月から12月まで、一年間の給与や賞与を合算して、各種控除を差し引いた額を納税する制度で、一言で言えば「会社がみなさんの代わりに確定申告してくれる制度」なんですね。所得を得ている人は、会社員であろうとなかろうと、全員が確定申告をする必要があるんですが、確定申告って個人でやろうとすると面倒ですよね? それを会社員の場合は、会社が代わってやってくれるんです。この年末調整は国が会社に対して義務化していまして、国としては個人に任せるより会社に管理してもらって税金の納付漏れを防ごうという意図があるんです。
会社員のみなさんは毎月の給与から所得税が天引きされていますよね?
大槻:はい、天引きされてます。手取りと額面の数字が違いますよね。
田中:これを源泉徴収と呼びます。この源泉徴収は会社がみなさんの予想年収から計算した仮払金なんです。そして年末調整をし、清算した結果引き過ぎていたお金を返すのが「還付金」。
逆に、 昇進して手当が増えた場合、昇給した場合、ボーナスが多かった場合など、「源泉徴収額が少なかったな?」といった場合に徴収されるのが「徴収金」と呼ばれているものです。なので年末調整を、単にお金が返ってくるイベントと思っている人は払うこともあるので要注意ですよ!
大槻:なるほど……。それでさらに複雑なのが、毎年変更点があったりするんですよね? 2020年にも大きな変更がありましたが、2021年の年末調整の変更点はどんなところですか?
2021年、年末調整に4つの変更点
田中:大きな変更点は、以下の4つです。変更点1. 税務関係書類の押印義務の見直し
今まで押印義務があった多くの税務関係書類に、押印の必要がなくなりました。例えば、「令和3年分の給与所得者の扶養控除等申告書」のあなたの氏名欄の隣にあった印鑑の欄がなくなっています。変更点2. 年末調整を電子化するための事前申請の廃止
令和3年4月1日以降にこの承認申請の提出が不要になりました。変更点3. 住宅ローン控除特例の見直し
これは大きなメリットです! すでに2019年10月から通常10年間の控除期間を13年間に延長する特別措置が実施されていましたが、今までは2020年12月末までに入居した人が対象でした。今回これが2年間延長され、2022年12月末日までに入居した人が対象となりました。新型コロナウィルスの影響で工事が遅れ、契約年内に入居できない人を救済する措置で、2022年12月末日までに居住を開始すれば、13年間の住宅控除を受けられることになりました。変更点4. 退職所得課税の見直し
勤続年数が5年以内の従業員の退職金について、課税対象だった一部の項目が見直されたんです。今までよりも貰える額が増えるよう、有利に改正されました。ただし、対象となる人が「勤続年数5年以内で退職金が500万円を超える」人なので、あまり一般的ではないかもしれません。例えば、特殊技能職、特殊専門職などヘッドハンティングなどで職を動いている人は該当するかもしれません。控除が適用となるのはどんな人?
田中:具体的には個人で民間の保険料を払っている人、家族が増えた人、個人で社会保険料を支払った人、住宅ローンを組んでいる人、そしてiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している人です。所得税には、基礎控除や配偶者特別控除のほかにまず保険料控除があります。保険の種類としては生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料、個人で納付書や口座振替で支払った国民年金・国民健康保険です。そして、住宅ローン控除など14種類の控除があります。さらに見落としがちなのは、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金があげられます。
今話題のiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している人は、「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。iDeCoの掛金も、社会保険料と同様になんと全額が控除の対象なんです! 節税効果が抜群に大きいのですが、かなり提出を忘れている人が多いそうですから要チェックですよ!
鉄崎:これはぜひみなさん覚えておいてくださいね!
大槻:iDeCo(個人型確定拠出年金)をやっている人も増えていると思います。ここで提出しなければいけないということをお忘れなく!
気になる還付の時期はいつ?
田中:多くの場合、12月か1月の給与と同時に還付、または徴収されます。年末調整は1年分の収入が確定しないと行うことができないので、12月分の賞与や給与の額が決まった後で、還付金額や徴収金額が算出され、給与に上乗せされたり差し引かれたりして調整されるのが一般的です。鉄崎:会社の年末調整期日までに証明書が間に合わなかった場合はどうすればいいですか?
田中:もし、勤め先で年末調整を受けられなかったときは、自分自身で「確定申告」を行う必要があります。還付申告については令和4年2月15日以前でも行えますが、一般的には令和4年2月16日~4月15日です。
大槻:証明書をなくしてしまったらどうしたらいいですか?
田中:再発行が可能です。例えば、書面の控除証明書等を紛失した場合は、今までは保険会社に再発行を依頼しなければなりませんでしたが、先ほど話に出たように、年末調整の手続きが電子化している企業も増えています。データでの提供が可能な保険会社の場合は、手書きによる申告書の記入、控除額の計算などが不要となり、申告書の作成を簡素化できます。今日のようにテレワークが進めば、年末調整手続きの電子化はますます加速するかもしれませんね。
ちなみに、私が駐在していたアメリカではこのような年末調整はありません。自分で申告した決算月に確定申告をして、税金還付を受けます。タックスリターンと呼ばれるものです。確定申告が発達したアメリカでは常に節税を意識した生活スタイルが浸透しています。日本の方々も年末調整など税金について興味を持ってほしいと思います。
鉄崎:勉強になりますね!ありがとうございました。
今回お話をうかがったのは……田中健夫さん
1974年にヤオハン・ジャパンに入社。各店舗の店長を経験し、アメリカのYAHAN U.S.A本社に配属される。その後保険会社に転職し、ファイナンシャルプランナーと住宅ローンアドバイザーを取得、お金のアドバイザーとして活躍中。趣味は落語とバンド。



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る