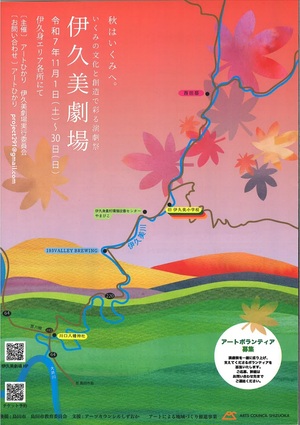(橋爪)今日はゴールデンウイーク恒例の「ふじのくに⇄せかい演劇祭2024」のお話です。県立の劇団SPACがおそらく1年で一番力を入れている活動です。ことしも演劇5作品のほか、パフォーマンスやダンスの催しが静岡市内で5月6日まで行われます。
(山田)「ふじのくに⇄せかい演劇祭2024」はもう既に始まってるんですよね。
(橋爪)そうなんです。4月27日から始まっています。27日は私、静岡市駿河区の舞台芸術公園野外劇場「有度」で行われた演目を見てきました。SPACと、鳥取市の劇団「鳥の劇場」が共同制作した「友達」という作品でした。
(山田))鳥取市の劇団と静岡のSPACが一緒に共同制作した?
(橋爪)演出したのは鳥の劇場の中島諒人さんなんですが、この方はSPACのOBだと聞いています。そういう繋がりもあったのかもしれません。この演出が本当に面白くて。
(山田)どうでした?
(橋爪)安部公房の戯曲で、SPACと鳥の劇場から5人ずつ、計10人の俳優が出演する主に会話劇で成り立つ演目です。
戯曲の発表は1967年。それを2024年に演じています。作家本人が「黒い喜劇」と言っているように、時の隔たりを越えてまさにブラックコメディーとして笑えるし、悲劇的な結末に同情もします。自分の中ではお笑い6、悲哀が4という感じで、大変優れた演劇でした。
(山田)なんか演劇的ですね。悲哀があって、でも笑いがあってというところが。
(橋爪)そうですね。どこかに偏って、めちゃくちゃ感動して泣きっぱなしというような感じじゃないところがいいんですよね。
(山田)演劇はそういうものですもんね。
(橋爪)簡単にストーリーを紹介しますね。都会に住んでいる若い男の部屋に、「友達」と称して3世代からなる家族らしき7人が住み着いてしまうんですよ。彼らはひたすら「隣人愛」を解き続けて、「あなた1人で寂しいでしょう。ここにいてあげる」というような話をするんです。
(山田)なんか怖いですね。
(橋爪)怖いですよね。客観的に見て彼らは侵入者なんですけど、理が自分たちの方にあるような口調でどんどん男を説き伏せるんです。そうすると観ているこっちまで、部屋を侵略されて「出ていけ」と言い続けているんだけど、もしかしたら「出ていけ」と言っている自分のほうが間違っているんじゃないかと思うようになっていくんですよ。
(山田)ほおー。
(橋爪)演技をしている俳優さんの力だと思うんですけど、舞台上の人物に同化し、理不尽に慣れていくことに気づくんです。共同体というものがそこにあったら、同化していかなければいけないんじゃないかとだんだん思ってしまいます。そういう怖さがあります。
(山田)日本的でもありますね。
(橋爪)半世紀以上前の戯曲だということを考えると、つくづく人間や社会は変わってないのではないかと思わされました。
(山田)なんか流されていったりとか、みんなが同じ方向を向いてしまうんだという感じはしますね。
野外だからこその“演劇マジック”
(橋爪)観ていて演劇マジックを感じることがすごく多かったです。最も大きかったのが、上演会場が野外劇場だという点です。日本平の「有度」と名付けられた場所で、木々に囲まれたエリアです。ウグイスの鳴き声がしますし、夕方から始まったので周囲がだんだん暗くなっていく。それも演出なんです。ぐずついた天気が続いたので、黒塗りのステージにはあちこち雨でぬれた跡があって、そこで演劇をしてしまうんです。(山田)へぇー。
(橋爪)しかも演劇のストーリーは、ほとんど部屋から出ないという内容。
(山田)でも野外でやっているという。
(橋爪)野外で繰り広げられる密室劇。このギャップが演劇マジックだと思いました。
ということで、せかい演劇祭がどのようなものか知らない方のために、説明しておきますね。歴史をたどると24年前にさかのぼります。国際的な舞台芸術の祭典「シアター・オリンピックス」がきっかけでした。1999年、ギリシャ・アテネに続く第2回大会を静岡市で開き、翌年以降はSPACが独自事業の「Shizuoka春の芸術祭」として定着させました。これを2011年に、改称しました。
現在は東静岡駅近くの静岡芸術劇場や日本平の舞台芸術公園に加えて、駿府城公園に約500席の特設会場を設置してSPACが上演することも定着しています。駿府城公園などでは同時期にストリートパフォーマンスの祭典「ストレンジシード静岡」も連動開催されています。昨年はこれらの催しにのべ約27000人が来場しました。
(山田)昨年はこの時期に「ゴゴボラケ」の公開放送を駿府城公演でやりましたよ。
(橋爪)私、客席にいましたよ(笑)。
今回、せかい演劇祭とストレンジシード静岡の開催意義を自分なりに考えてみました。一つは世界各国の演劇が観られるまたとないチャンスであるということです。静岡にいながらにしてヨーロッパやアジアの演劇を観ることができます。
ただ、私はもう一つ、大事な役割があると思っています。それは、劇場を飛び出した、自分も含めた一般の人の日常と隣り合わせの空間で演劇を観る機会だということです。例えば、4月27日から29日にせかい演劇祭の演目の一つとして実施された「かちかち山の台所」は、舞台芸術公園に観覧者が集まり、日本平のあちこちを自分の足で動き回りながら各所で俳優の演技を見るという2時間の演目でした。
(山田)俳優さんが散らばっているんですか。
(橋爪)残念ながら私は直接取材してはいないんですが、取材記者によると5カ所を巡るそうです。それぞれが別の演目じゃなくて、全体としておなじみの「かちかち山」の物語になっていて、最後に参加者全員に汁物が振る舞われるという…。
(山田)怖い。カチカチ山の話ですもんね。
(橋爪)この話、知ってましたか。
(山田)当然知ってますよ。
(橋爪)汁物の材料が何かも分かります?私は知らなくて、話を聞いてぞわっとしました。
(山田)ちょっとホラーが入ってますね。
何もない空間が舞台になる!

(橋爪)「演劇って芝居小屋や劇場でやるもの」と思っている方もいるかもしれませんが、こういう上演例をみると、そうした固定観念が壊される機会になるのではないかなと思いました。
(山田)ラジオを聞いている方からすると、劇場で用意された演劇を「今から始まります。どうぞ」という形で観たほうがおそらく理解しやすいと思うんですけど、野外で上演する作品の魅力とかはどのように説明しますか。
(橋爪)劇団「第三舞台」の演出家・鴻上尚史さんの著書に、世界的に有名な演出家ピーター・ブルックの言葉が書かれています。「演劇とは何か」という問いかけについてブルックは「どこでもいい、なにもない空間-それを指して、わたしは裸の舞台と呼ぼう。ひとりの人間がこのなにもない空間を歩いて横切る、もうひとりの人間がそれを見つめる-演劇行為が成り立つためには、これだけで足りるはずだ」と言っているんですね。だから本当にどこでもいいと言えます。
これは、普段演劇を見慣れない人ほど新鮮な経験になると思います。自分もそうだったので。こんな場所で演劇をやっていいんだ、こんな場所で演劇が成立するんだ、という驚きと納得感というのは、音楽ライブや映画、小説にはない演劇ならではの特質だと、私は考えています。
(山田)たしかにそうですね。
(橋爪)ということで、せかい演劇祭後半戦とも言える3日からの演目を紹介すると、SPACの「白狐伝」、アントン・チェーホフ作、トーマス・オスターマイアーさん演出の「かもめ」、カメルーン生まれ、パリで活動するダンサー・振付家メルラン・ニヤカムさんの「マミ・ワタと大きな瓢箪」が予定されています。ただ、 チケットは全部売り切れていまして…。SPACに問い合わせたら、「各公演の当日券の有無については、公演当日にお電話または演劇祭ウェブサイトにてご確認ください」とのことでした。
一方のストレンジシード静岡は観覧無料で投げ銭方式なので誰でも観劇できます。5月4日から6日までの3日間、全部で12演目を駿府城公園、静岡市役所・葵区役所、青葉シンボルロード周辺で上演します。
こちらも同じように「何もない空間」で演劇行為を目撃する良い機会です。私は4年ほど続けて観に行ってますが、駿府城公園の芝生広場の片隅とか、舗装されていない広場に線を引いてそこを舞台にして見せていたりとかしてました。市役所の大階段もそうです。
(山田)階段を客席にしたりしますよね。
(橋爪)そうなんです。大道具とかセットがない場合がほとんどです。まさに「なにもない空間」に物語が出現します。それを目撃することが演劇の醍醐味だと思っています。個人的にも取材で伺う予定ですが、とても楽しみです。
(山田)演技はハードルが高くて、知識がないと観られないんじゃないかなどと思いがちですけど、そうではなくて市役所の階段に座って観たりということですね。
(橋爪)手軽に観ることができる非日常というとこですよね。
(山田)それが面白いかどうかは皆さんの判断ですが、そういうのがすごくいいなと思います。
(橋爪)演劇鑑賞の入口には本当に最適だと思います。
(山田)ぜひ、皆さん静岡でこういった世界的な演劇を観るチャンスですので行ってみてください。今日の勉強はこれでおしまい!



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る