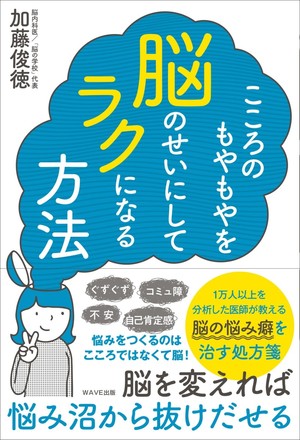(聞き手、撮影=論説委員・橋爪充)

「人と違う」に価値を与える
-このような体裁の本が企画された経緯について教えてください。宮城:文化庁の補助でSPACにコンサルが付いてくれたんですが、彼らが、SPACに蓄積されている知恵は演劇を見に来る人、客席に座る人以外にも 広く活用できるんじゃないかと感じてくれたんです。(SPACの演劇を)今の社会が直面しているさまざまな課題に関係があることとして捉えてくれて。
-これまでになかった視点かもしれませんね。
宮城:僕自身は劇団をどう運営していくかをひたすら考えてきたけれど、彼らから見ると、それが劇場の 内側でしか活用されていないのはもったいないと。なんとか外の世界にチャンネルを広げられないか考えてくれて、「対談本はどうだろう」というアイデアが出たんですね。
-ご自身はビジネスパーソンとの対談という企画に、どう向き合ったんですか。
宮城:当初は、面白い対談になるのか全くわからなかったんですよね。そういう分野の方々と対談をしたことがありませんでしたから。でも、話してみると驚くほど盛り上がって。最先端でやってらっしゃる方は、日本や世界の空気感に敏感に反応しながら、会社を経営されている。演劇の作品を作ることと、とても似ていたんですね。
-西村さんの巻頭言で、演劇とビジネスの接点や重なる部分について分かりやすく解説されています。「これからのビジネスには創造性と身体性を融合させた新たなリーダーシップが求められる。演劇はビジネスにおけるリーダーシップ、戦略、組織運営のヒントを与えてくれる。演劇はチームの力によって完成するアートである。この特性こそが、組織運営やリーダーシップの視点から学ぶべき大きなポイントとなる」。こうした外部からの見解が示される中で、〝演劇側〟から〝ビジネス側〟はどう見えていたのでしょう。
宮城:いわゆる民間企業の経営者の方のドラマには、もともと非常に興味がありました。例えばの話ですけど、あるところまでは「勘」で打った施策が当たっていたのに、あるところからはどれも外すようになる、とかね。どうしてそういうことが起こるんだろうという点は、演劇人としてとても興味があります。シェークスピアの歴史物でもあるんです。上り調子だった人があるところからどんどん下り坂になる。
-「人間とはそういうもの」だと。
宮城:ただ、演劇は日常から少し浮いている、離れているからこそ誰にとっても逃げ場や心を休める場所になると捉えていました。だから、現実の課題に接合していくことは、そんなに考えていなかったんです。
-もしかするとビジネスの在り方が、時代を経るに従ってどんどん創造性が必要になってきて、演劇的なものに近づいているのかもしれませんね。
宮城:少なくとも教育については前々からそのことを申し上げてきました。ある時点までの日本は、横並びで平均点がすごく高くて、これ、世界のどこと比べてもスタンダードが高いでしょうっていう状態だった。みんなある程度高いレベルのことができるっていうのが強みでしたよね。しかし、みんなが同じことしか考えてないという横並びの弱みが出てきています。
-近年は価値観が様変わりしつつあります。
宮城:演劇が教育の中に入っていく意味は、「人と違う」に価値を与えることだと思います。人と違うってことのポジティブな価値を、子供にも先生にも分かってもらえるとよく言ってたんですね。でも、いろいろ聞いていると、会社の経営、あるいは会社という組織が変わってきたようです。他の人と違うことを考える人が出てこないと、(会社が)伸びなくなったのかもしれません。

経営者と舞台上の俳優は「そっくり」
-9人のリーダーとお話しされた感想はいかがですか。宮城:まず思ったのは、トップの経営者は実に「人それぞれ」だということ。どの方も、誰にも似ていないですよ。でも瞬間、瞬間の自分を守っていないという点は共通している。よろいを着けて自分を守るみたいなことをしていないんですよ。それは舞台上の演劇、舞台上で演じてる俳優の在り方とそっくりでしたね。
-それぞれの対談において宮城さんの立場が微妙に違いますね。聞き役としての比重が高かったり、相手に話すことが中心になったり。いい意味で、カチッと決め込んで対話に臨んだような雰囲気がありません。
宮城:そうですね。出たとこ勝負でした。それなりにかっちりした企画書がありましたが、実際始まってみると、そのシナリオはあんまり関係がないんですよ。あらかじめ決めた結論に収斂させないように心がけました。
-ビジネスパーソンとの対話の中で、宮城さんご自身の演劇に対する考え方が 伝わる場面が多々あって、興味深かったです。
宮城:僕は前に考えたことをどんどん忘れていくタイプなんです。ただ、こうした対談では相手の方と話してるうちに、そういえばこういうシチュエーションではこう考えてたなといったように、いろいろ思い出されてくる。過去に考えたことが引き出されてきたんでしょうね。
-個人的にはマネックスグループの清明祐子社長との対話が特に印象に残りました。組織のファウンダー(創立者)からバトンを受け取ったという点において、清明さんと宮城さんは共通していて、とても話が盛り上がっていますね。「2 代目」という立場で劇団をどう運営してるのかについて率直に語っておられる。これまであまり聞いたことのない話だと感じました。
宮城:ファウンダー、あるいは中興の祖みたいな存在がガーッと引っ張った後、それを引き継いだ人がどこかサラリーマン的になったために、この 30 年間イノベーションが起こらなかったのではないかと。 2代目以降の人が、ファウンダーではないことの強みをもっと自覚できれば、例えば浄土真宗の蓮如のように活躍できるのではないでしょうか。ファウンダーとは違う視野が持てる。そこをもうちょっとポジティブに捉えるといいんじゃないかなという気がしますね。
-対談を通じて、何を得ましたか。
宮城:会社の経営を考える方の中にあるものと、演劇人として僕らが考えてきたこと、蓄積したことは共通する部分があると思いました。これからは、もっと接点を作っていくべきですね。



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る