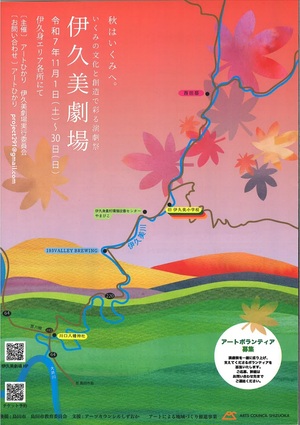藤枝市を拠点にする劇団「ユニークポイント」主宰の山田裕幸さんがフェスティバルディレクターを務める演劇祭が4年目を迎えた。東海道沿いの商店街各所にポスターが貼られ、街歩きを楽しむ人の姿も数多く見られた。この催しが春の風物詩として根付きつつあると感じた。
藤枝市を拠点にする劇団「ユニークポイント」主宰の山田裕幸さんがフェスティバルディレクターを務める演劇祭が4年目を迎えた。東海道沿いの商店街各所にポスターが貼られ、街歩きを楽しむ人の姿も数多く見られた。この催しが春の風物詩として根付きつつあると感じた。「小菅紘史× 中川裕貴」は俳優小菅紘史さんと音楽家中川裕貴さんのユニット。演目は中島敦の「山月記」をチェロ伴奏による一人芝居にしたもの。「花粉症がひどい」など小菅さんによるゆるめのMCから立ち上がり、物語のあらすじが説明される。
ほっぺたからあごにかけてたっぷりの「鍾馗ひげ」にスキンヘッドという小菅さんだが、まなざしは柔らかい。穏やかなトークが終わり「山月記」というタイトル読み上げとともに、芝居が始まる。小菅さんがまとった「気」のようなものが、一変するのが分かる。
詩家として身を立てようとするも挫折し、絶望の果てに虎の姿に変貌する男。「人食い虎」として人里で恐れられる存在だが、毎日一定の時間は人間の意識を保ち続けている。ただ、その時間は日を追うごとに短くなっている。そのことに自覚的な男は、目の前を通ったかつての親友に語りかける。やぶの中に浅ましい自分の姿を隠して。
 四つ足の哺乳類を表現する小菅さんの身体能力が凄まじい。つま先や足裏の一部だけで地面に接し、そんきょの姿勢からゆっくりと動く。まばたきまでも計算され尽くした顔相の変化にも見惚れた。家族の無事を願うせりふの後は、目を見開いたままの時間がどれだけ続いたことか。発言の重みとまばたきの回数に、そっと相関性を持たせていた。
四つ足の哺乳類を表現する小菅さんの身体能力が凄まじい。つま先や足裏の一部だけで地面に接し、そんきょの姿勢からゆっくりと動く。まばたきまでも計算され尽くした顔相の変化にも見惚れた。家族の無事を願うせりふの後は、目を見開いたままの時間がどれだけ続いたことか。発言の重みとまばたきの回数に、そっと相関性を持たせていた。かつての茶工場だった会場は茶箱が積まれている。約50席も茶箱を活用している。下界の風の音もほどよいBGMとなっていた。そんな環境下で中川さんはチェロを時に打楽器、時に電子楽器のコントローラーのように扱った。多くのエフェクターを駆使して、現場で多重録音のような作業を繰り返し、重層的な「伴奏」を響かせた。
虎になった男が発したせりふが記憶に残る。「山月記」の舞台は唐代の中国だが、現代日本を生きる自分に深く突き刺さった。「理由も分からぬものを受け取って生きていくのが生き物の定めだ」
(は)



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る