語り:春風亭昇太
.jpg)
旧暦1月7日、藁科川上流の日向地区で県指定無形民俗文化財「日向の七草祭」が行われます。
この祭りは、「田遊び」と呼ばれる民俗芸能のひとつで、一年の始めに、稲作の所作を演じて米の豊作を祈るものです。その歴史は古く、寛永21 年(1644 年)に記された古文書も残されています。
日向の七草祭は、日の出の祈祷と夜祭りで構成され、夜祭りで演じられる演目のひとつが駒んず(こまんず)ばやしです。笹竹をゆらす人たちの輪の中に
馬と山鳥に扮した子どもが入って出ていきます。馬は養蚕の神を象徴し、山鳥は、その羽根が蚕を育てる時に使われることから、この演目は、稲作とともに養蚕の繁栄を祈願するものであることがわかります。
続いて登場するのが、海の幸、山の幸をご本尊に奉納する「浜行き」と「若魚」。「浜行き」は、大きな煙草入れを腰に差し、米俵を背負って海産物を模した作りものを舞役に分け与えます。
「若魚」は、天秤棒を担いで山海の幸を運んできます。
七草祭りの中心となるのが「数え文」。田んぼに見立てた太鼓を囲んで舞役が座り、数え文を独特の節回しで読み上げます。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

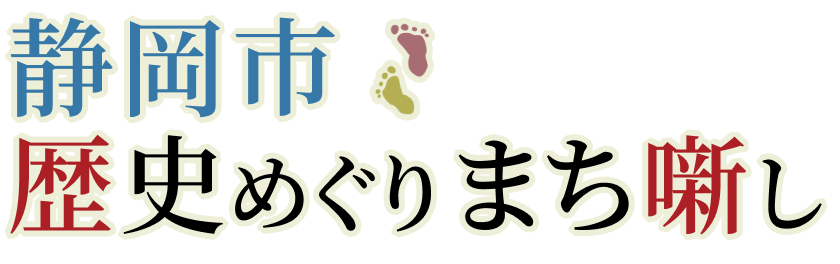

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































