
古に仙人が住むとされた富士山と人間の世界を繋ぐ架け橋と考えられてきたのが三保松原でした。羽衣伝説ゆかりの松は現在3代目。1922年に日本で最初の名勝に指定された「三保の松原」の象徴です。枯れてしまった2代目の羽衣の松の隣に鎮座する、御穂神社の離宮「羽車神社」。神が羽車に乗って三保に降り立ったことから名付けられたと言われています。
樹齢2・300年の松がおよそ500メートルに渡って三保の松原から御穂神社へ続く松並木。海からお迎えした神がこの道を通って御穂神社の社殿に向かう「神の道」と呼ばれています。神の道の先にある御穂神社も「羽衣伝説」ゆかりの地。天女の羽衣の切れ端が所蔵されるこの神社は戦国武将にも崇拝されて、徳川家康は慶長年間に壮大な社殿を寄進しました。江戸中期に再建された現在の社殿は、静岡市の指定有形文化財となっています。
御穂神社で古くから行われているのが、筒粥祭(つつがゆまつり)。大きな窯で粥を炊き、そこに竹筒を入れて筒の中に入った粥の量で豊作を占う神事は1年の豊作を祈って現在も地元で大切に受け継がれています。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

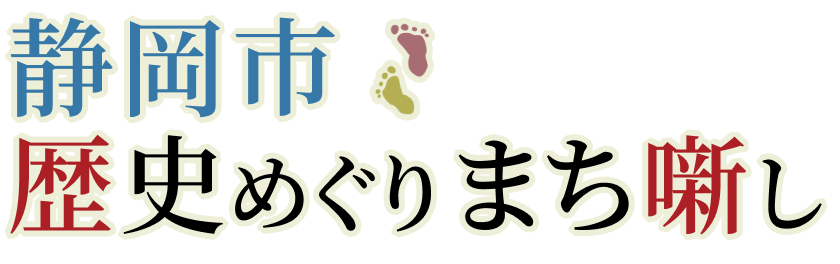

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































