 改修を目的に4月から休館となった静岡市葵区の市民文化会館は、1978年11月3日、東海地方随一の規模を誇る「文化の殿堂」として開館した。半世紀近くにわたって市内の文化事業の中核を担ってきたこれまでを振り返る。
改修を目的に4月から休館となった静岡市葵区の市民文化会館は、1978年11月3日、東海地方随一の規模を誇る「文化の殿堂」として開館した。半世紀近くにわたって市内の文化事業の中核を担ってきたこれまでを振り返る。市文化政策課に残る当時の資料によると、市民文化会館の建設事業計画は67年に「城内地区再開発計画」の一環として提案された。建設案について建物の規模や内部に設けるホールの大きさなどで市民レベルの議論となり、市民団体による陳情や寄付、経費を問題視して建設内容に反対する投書も相次いだ。最終的には「理想案」とも言われた大規模会館の建設案を採択。資金繰りも含めて8年の準備期間を経て75年にようやく政府資金の起債許可を受けた。急ぎ同年中に入札、議会承認、着工までこぎ着けたという。
建設場所は旧静岡刑務所跡地。江戸時代には罪人の収容所があり、1894年から刑務所となって、赤レンガの塀に囲まれていた。1964年に代替施設の建築を条件に市に払い下げられ、68年に刑務所施設の解体が完了。跡地には先んじて現在の中央体育館とプールが建設されていた。
開館まで市内の文化事業を支えていたのは、市役所本館の隣に建設された「静岡市公会堂」(35~78年)と、静岡国体に合わせて建築家丹下健三が現在の駿府城公園内に手がけた体育館「駿府会館」(57~78年)。両施設は各校の文化祭や吹奏楽大会、コンサート、演劇などが開催され広く親しまれたが、大地震に対する警戒感が強まり、老朽化と耐震性の問題などから惜しまれつつ同時期に閉館、解体された。
「超デラックス」「マンモス建築」「全国トップクラスの設備」「市民の誇りともいうべきもの」。市民文化会館建設を伝える当時の新聞紙面には仰々しい言葉が並ぶ。敷地面積3万6084平方メートル、建築面積9350平方メートル、延床面積2万2890平方メートル、鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上4階。総事業費53億9037万円の建築は、市制始まって以来の大事業だった。約2千人が入る大ホールと、約1200人収容し歌舞伎の上演が可能な中ホールを兼ね備えた県内一の威容で、東京-名古屋間にも比類する市民会館はなかったという。
内装も「文化の粋を結集した」(静岡新聞)。静岡市名誉市民で人間国宝の染色家芹沢銈介原画の緞帳[どんちょう]、彫刻家掛井五郎作のブロンズ像「南アルプス」、陶芸家神成澪作の壁画「讃光の詩」、市民有志が集まり制作した駿府城の漆壁画などが館内を飾った。館外に場所を移した物もあるが、これらは2028年の改修後も同館のシンボルとなる予定だ。
1999年に館内のレストランが営業を終了したり、コロナ禍の影響で喫茶店がなくなったりと変遷しつつ開館47年を経ての休館。改修は小規模となる見込みだが女性用トイレ増設や、効きの悪さが指摘されている冷房のオーバーホールなどを予定しているという。市文化政策課の担当者は「演劇や音楽を見る方にとっても披露する方にとっても市民文化会館は活動の中心だ」と変わらぬ重要性を語った。
■公演最多は「四季」
休館を前に静岡市文化振興財団と静岡市民文化会館は、1978年~2025年のコンサートや舞台の公演数ランキングを発表した。47年間累計の総合ランキングトップ5のほか、10年ごとのベスト10も算出している。
1位に輝いたのは、昨年10年ぶりのミュージカル「キャッツ」ロングラン公演を実施した劇団四季。2位には結成51年目のバンド「THE ALFEE」がつけた。10年別ランキングで見ても、1978~88年と99~2008年、19~25年は劇団四季がトップ。1989~98年と2009~18年はTHE ALFEEが1位とトップ2が圧倒的な強さを見せた。最新の19~25年では劇団四季に次いで富士山静岡交響楽団が2位となり、近年の旺盛な活動を示した。

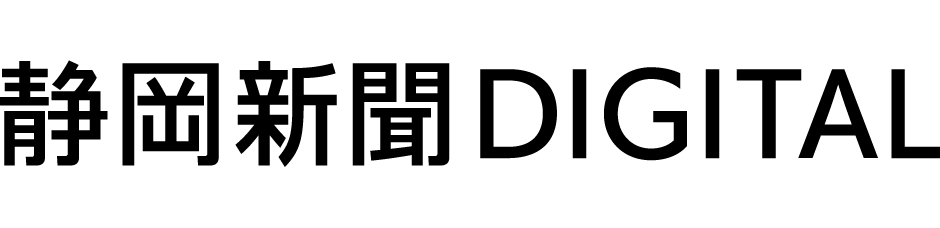

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る































































