 静岡、山梨両県は今夏から条例で富士山の入山料や通行規制時間を統一する一方、登山に必要となる登録や予約手続きが両県で異なる状況は続くため、混乱を懸念する声も上がる。静岡県が5月9日から公式アプリ「静岡県FUJI NAVI(ふじなび)」の配信と事前登録を開始するのに対し、山梨県は昨年導入した通行予約システムを継続する見通し。有識者は「登山者が混雑を回避できない」として両県で足並みをそろえることに期待する。
静岡、山梨両県は今夏から条例で富士山の入山料や通行規制時間を統一する一方、登山に必要となる登録や予約手続きが両県で異なる状況は続くため、混乱を懸念する声も上がる。静岡県が5月9日から公式アプリ「静岡県FUJI NAVI(ふじなび)」の配信と事前登録を開始するのに対し、山梨県は昨年導入した通行予約システムを継続する見通し。有識者は「登山者が混雑を回避できない」として両県で足並みをそろえることに期待する。県が新たに導入するアプリは電子決済を搭載し、現地で認証する直前まで変更や返金ができる。登山マナーや装備、ルールについてテキストなどによる事前学習を課し、「富士山テスト」に全問正答した人に入山証を発行する仕組みを準備中。テストは「10問程度の選択式で、テキストを読めば分かる簡単なもの」(県担当者)としている。
登山の安全に欠かせない大雨や地震、噴火などの災害情報を登山者のスマートフォンにプッシュ型で通知する。GPS機能を使えば位置を特定でき、遭難時の救助に役立てられる。県担当者は「富士登山に必携のアプリと認識されるようにしたい」と期待し、今後の機能拡張も視野に入れる。山小屋の宿泊予約や麓の施設のクーポン発行なども技術的には可能という。
一方、「富士登山オフィシャルサイト」によると、山梨県は昨夏に始めた任意の通行予約システムを継続する。装備や登山ルールについては誓約事項への同意を求めるが、本県の仕組みとは異なる。同県担当者は両県でのシステムの統一について「当面予定にない」との認識を示した。
富士山適正利用推進協議会専門委員の山本清龍東京大大学院准教授は「山小屋の予約状況を含め、両県にまたがる登録や予約の情報が得られないと、登山者が混雑を回避できない」と指摘し、富士山全体でシステムを統一する意義を訴えている。
■ アプリで電子決済、登山ルールのテスト全問正答で入山証
公式アプリは、スマートフォンからダウンロードする。「日帰り」か「宿泊」を選んで登山ルートを選択し、名前や登山日、宿泊する山小屋などを入力。電子決済で1人4千円の入山料を支払う。同一行程の家族やグループは一括登録・決済ができる。決済後、1人ずつ配布されるURLを通じて登山ルールなどを学び、テストで全問正答すると、QRコード入りの入山証が手に入る。登山当日は5合目などにいるスタッフにQRコードを提示して認証を完了させる。スマホや電子決済を利用しない登山者は5合目で登録や学習、支払いが必要になる。障害者や学校の教育活動は入山料免除の対象。県は事前に免除申請をする仕組みを検討している。

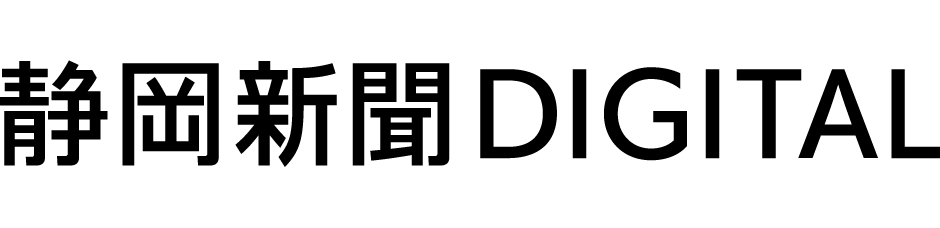

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る






























































