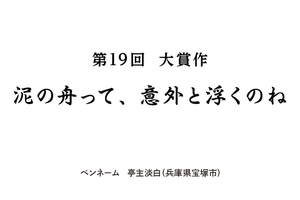参拝者にお金を貸し、病気も取り上げてくれる水神様-。「金貸水[かねかしすい]神社」(浜松市天竜区二俣町鹿島)のユニークな伝説を発信しようと、浜名高(同市浜名区)史学部が絵本「鹿島[かじま]の金貸水神伝説」を制作している。同部の卒業生で伝説研究の中心を担ってきた玉ノ木梓純[あずみ]さん(愛知大短期大学部1年)は「水神伝説を絵本で知った病気の人が、少しでも晴れやかな気持ちになれば」と願いを込める。
参拝者にお金を貸し、病気も取り上げてくれる水神様-。「金貸水[かねかしすい]神社」(浜松市天竜区二俣町鹿島)のユニークな伝説を発信しようと、浜名高(同市浜名区)史学部が絵本「鹿島[かじま]の金貸水神伝説」を制作している。同部の卒業生で伝説研究の中心を担ってきた玉ノ木梓純[あずみ]さん(愛知大短期大学部1年)は「水神伝説を絵本で知った病気の人が、少しでも晴れやかな気持ちになれば」と願いを込める。伝説によると1499(明応8)年8月14日、地元の船頭の権三郎が天竜川の氾濫で流されたほこらを命懸けで救った。体が冷えて病に伏せっていたある晩、夢に水神様が現れて全快させると約束。さらに「病気で苦しむ人がいたら病気を質として借金証文(借用証書)を上げさせよ。期限までに借金を返せなければ、その病気を取り上げよう」とも告げた。それ以降、病気を担保にお金を貸してくれる水神様として厚く信仰されてきたという。
玉ノ木さんは同高1年だった3年前、通学路に立つ神社の伝説を郷土誌で知り、起源に迫る研究を開始。同学年や後輩も仲間に加わった。
旧家の「田代家文書」や天竜市史などをひもとき、古くから水運業が盛んだった二俣地区では、人々が「暴れ天竜」の水難や水由来の病気に悩まされてきたことが分かった。「無尽講」をはじめ、お金の貸し借りが頻繁だった様子も浮かんだ。住民への聞き取りからは、伝説に基づく病気治癒の願掛けが受け継がれ、水神様が地域の守り神とされ続ける現状を知った。
神社が参拝客にお金を貸した事実は確認できず、起源も特定できなかったが「天竜川の脅威から守ってほしいという住民の願いと、お金の貸し借りの習慣が結びついて伝説が生まれた」と考察した。
研究は地域にも影響を与えている。同神社の本社・椎ケ脇神社氏子総代会は高校生の取り組みを受けて付近に案内看板を設置。伝説への関心はじわりと広がっていて、参拝客が納める「借用証書」は昨年約200枚となり、3年間で4倍に増えた。愛知県や関東など県外からの参拝もあるという。総代の鈴木悟さん(74)は「市内でも意外と知らない人がいる伝説に光を当ててくれた」と部員の奮闘をたたえる。
伝説をさらに広めようと、史学部は絵本制作に着手。イラストや文章など役割分担しながら作業を進め、現在は仕上げ段階を迎えている。同部の4代の30人余が関わることになった絵本は5月に完成予定。140部作り、市内の学校や図書館に寄贈する。
<メモ>絵本はA4変形判全32ページ。イラストと文章で伝説を表現し、英語訳も添えた。史学部の研究概要や考察にもページを割いた。公共施設への寄贈後は一般販売を目標とし、同部は個人や企業からの支援を募る予定という。問い合わせは浜名高史学部顧問の中村勝芳教諭<電053(586)3155>へ。

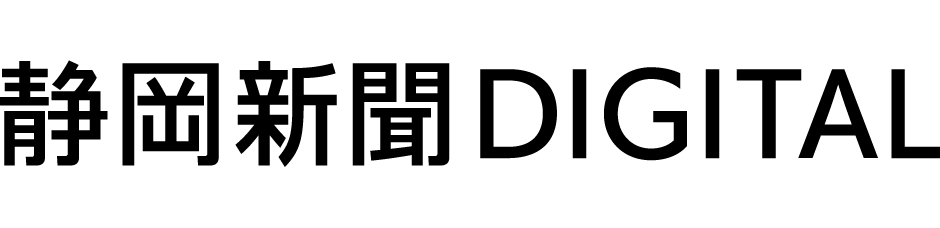

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る