 かつて久能山東照宮(静岡市駿河区)の境内に建っていた五重塔を、日本建築芸術大学校(富士宮市)を今春卒業した村松克美さん(22)=同区出身=が15分の1の模型で復元した。4月から宮大工として働く村松さんが卒業制作として手がけた高さ約2メートルの大作で、このほど東照宮に奉納、神楽殿で展示されている。
かつて久能山東照宮(静岡市駿河区)の境内に建っていた五重塔を、日本建築芸術大学校(富士宮市)を今春卒業した村松克美さん(22)=同区出身=が15分の1の模型で復元した。4月から宮大工として働く村松さんが卒業制作として手がけた高さ約2メートルの大作で、このほど東照宮に奉納、神楽殿で展示されている。五重塔は、1873(明治6)年に明治政府の神仏分離令で取り壊されるまで存在していた。社務所と社殿の中間付近に建ち、高さ約30メートルもの規模だった。
村松さんは同校の教員から勧められ、昨年春から本格的に制作を開始。確認できた当時の図面がわずか数枚と少なく、日光東照宮(栃木県)などの他の五重塔の図面なども参考にした。久能山東照宮境内の跡地を測量し、当時を推測して模型の図面を完成させた。
五重塔を構成する太い支柱や緩く反った屋根、「斗(ます)」と呼ばれる梁(はり)や桁を支える小さな部品など千個を超えるパーツは全て、「かんな」や「のみ」などで手作りした。組み立て作業では、一つの部品のわずかなずれが全体の高さに影響するため、慎重に微調整を重ねた。
約1年かけ完成させた五重塔は裏側が断面図になっていて、柱や梁が美しく重なった内部の構造も見ることができる。模型を奉納した村松さんは「こんなすごい模型を作ることができ、頑張ってよかった」と感慨に浸った。奉納に立ち会った東照宮の権禰宜(ごんねぎ)も「東照宮博物館に展示して目玉にできたら」と期待した。
4月から京都の工務店で働く村松さんは「後世に残るような建築物を造る大工になりたい」と培った技術を誇りに意欲を見せた。

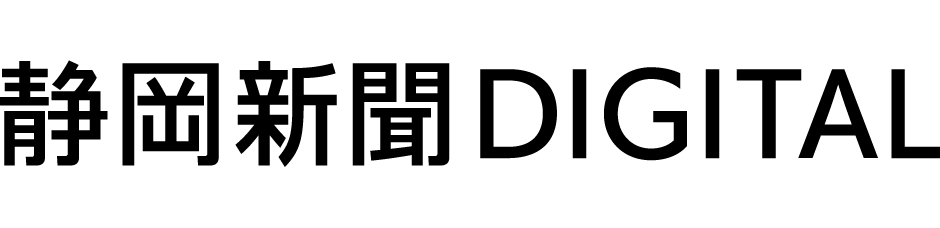

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る






























































