
安倍川と藁科川の合流点にある舟山。ここに、かつて舟山神社と呼ばれる神社がありました。
この場所は、安倍川が増水すると参拝できなくなったため、明治22年に、舟山神社は安倍川の右岸の神明宮に移されることになりました。藁科川が安倍川に合流する手前には、川の中洲に木々に覆われた小さな島、「木枯森」(こがらしのもり)があります。伝説によると、神である大蛇との間に子供を生んだ娘に父親が怒り、その子どもを川に流してしまいました。娘は子どもを追いかけましたが、この辺りで別れ別れになってしまい嘆き悲しんだ娘が子に焦がれた場所として木枯森と呼ばれるようになったとされています。
「木枯森」は、清少納言の「枕草子」にも記され、美しい風景として、数多くの歌に詠まれてきました。森の山頂には八幡神社が祀られ、江戸時代の国学者本居宣長の撰文を刻んだ「木枯森碑」や、駿府の医師であった花野井有年の歌碑が建てられました。現在ここに石段や鳥居は残るものの、度重なる災害や参拝の難しさから、羽鳥の八幡神社にご神体が移されました。毎年9月頃には羽鳥の八幡神社からご神体を神輿に乗せて木枯森へ戻す祭りが行われます。
東海道の旅の名所を記した「東街便覧図略」にも、安倍川と藁科川が描かれ、「舟山や木枯森などが川の中に浮かんだ様子は、非常に面白い。ここから見る富士山の姿は見事である。」と紹介されています。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

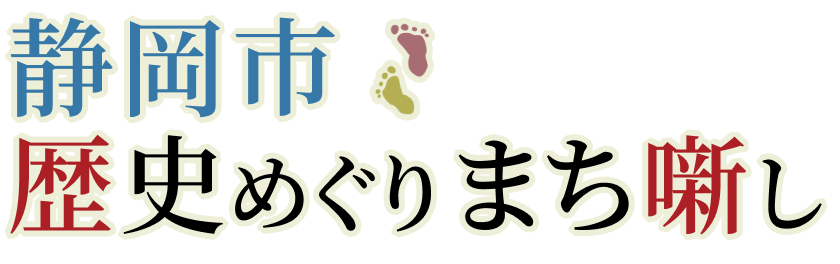

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































