語り:春風亭昇太

野鳥の宝庫といわれる麻機沼。かつてこのあたりには、麻機沼(あさばたぬま)を回り込むように安倍川が流れ込んでいました。
大御所として駿府に移り住んだ徳川家康は、城下を水害から守るために「さつま土手」を築き、安倍川を整備したと言われています。これによって安倍川から麻機地区に流れ込む水が少なくなり、現在のような麻機沼の姿になりました。
秋から冬にかけて、この沼で収穫される麻機蓮根は細身で、味が濃く、糸を引く粘りが特徴で昔から、上質な蓮根として栽培が続けられてきました。漢方に精通していた家康公が、カラダに良い食べ物として、この蓮根を食していたともいわれています。
麻機の東に広がるのは田畑の緑豊かな瀬名地区。瀬名には、江戸時代農民たちの共同倉庫であった「郷倉」が残されています。年貢米や飢饉のときのための備蓄米を保存した建物は、火災を防ぐため、厚い土壁をもった土蔵造で、外壁は白い漆喰と、腰瓦で固められています。
郷倉の隣には、盗難や天災から郷倉をまもる番人が住んでいた「番屋」も残されています。郷倉は番人が寝泊りして守るほど村にとって、大切なものであったのです。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

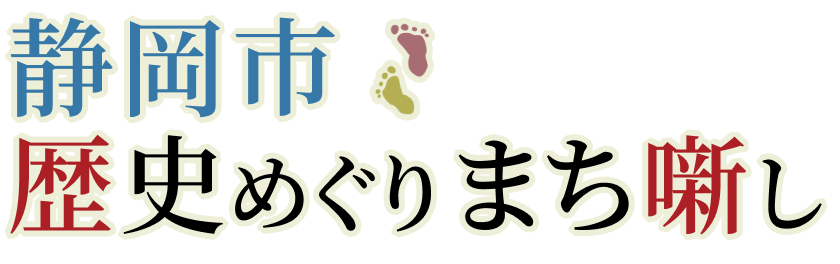

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































