
静岡浅間神社は、鎌倉時代から武将たちの崇敬を受けてきました。
三河・遠州の大名となった徳川家康は、武田氏の賎機山城(しずはたやまじょう)を攻撃するにあたって、麓の浅間神社を訪れ「無事に自分が勝利をおさめたならば、必ず社殿を再建する」と戦勝祈願の誓いを立てその社殿を焼き払ったと言われています。後に、家康は5か国を治めて、浜松城から駿府城に移り約束通り、浅間神社の再建を果たしました。
江戸時代、浅間神社は幕府から、変わらず手厚い保護を受け三代将軍徳川家光の時、幕府の直営工事として社殿の造営が行われ、全国から優れた職人が集められました。
華麗な社殿の数々はすべて漆塗り。富士山を模した高さ21メートルの大拝殿(おおはいでん)は、漆塗りの神社建築では日本一の高さを誇り浅間造りと呼ばれる重層建築の代表的な建物です。
現在の社殿は、火事で焼失したのちにおよそ60年の長い歳月と現在の金額に換算して約数十億円かけて江戸時代末期に再建されました。この時の技術が、職人たちに受け継がれ、駿河指物、駿河漆器など静岡の伝統工芸の発展に繋がったとされています。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

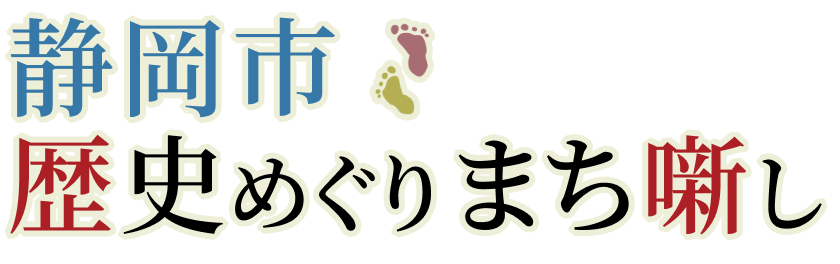

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































