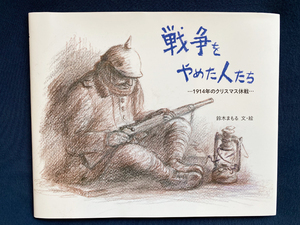新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府が国民に行動の自粛などを求めた緊急事態宣言から2025年4月で丸5年。新型コロナの感染症法上の位置付けは23年5月に「5類」に移行したものの、依然として厳しい面会制限を続ける医療機関や介護施設があるなど、コロナ禍の感染対策の影響は今も尾を引いている。
静岡県内唯一の第一種感染症指定医療機関として当初から患者を受け入れてきた静岡市立静岡病院は、国内でいち早く院内の感染対策の緩和に舵を切った。コロナ治療の最前線に立ちながら「通常の医療との両立」を掲げ、「余分な対策はやめる」という決断を重ねてきた。
同院の小野寺知哉理事長(前理事長兼病院長)がこのほど、医療人類学者の磯野真穂東京科学大教授と対談し、独自の決断の背景を振り返った。磯野教授は、コロナ禍になぜ行き過ぎた感染対策が行われ、多くの医療福祉現場でそれらをやめられなかったのかを考察した。進行はSBSの野路毅彦アナウンサー。
「病院に近寄るとうつる」と怖がられ 保育園が職員の子預かり拒否も
野路:静岡市立静岡病院は、コロナ禍でどんな役割を担いましたか?
小野寺:当院は静岡県でただ一つの、第一種感染症指定医療機関です。2020年2月、神奈川県からの依頼で、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の患者を受け入れたのが始まりでした。静岡県内で最初に、新型コロナに感染した患者の治療を担うことになりました。

野路:病院ではどんなことが起きましたか?
小野寺:まずマスコミが来て、なんとかして患者の写真や映像を撮ろうとしました。当院の職員がブルーシートで患者を隠しながら病室に運びました。その後、国内で感染が広がってきた頃から、当院に近寄るだけでコロナに感染してしまうんじゃないかと。それこそ半径500m以内に入るとコロナがうつるんじゃないかと。皆さんがすごく当院を怖がるようになりました。スタッフがタクシーを呼んでも「静岡病院へは行けません」と乗車を拒否されたり、スタッフが保育園から「子どもを登園させないでくれ」と保育を拒否されたりといった状況が、かなり続きました。
野路:2020年3月にはタレントの志村けんさんが、同年4月には俳優の岡江久美子さんがコロナに感染して亡くなった。元気に仕事をしていた方が、なすすべなく亡くなってしまう病気なんだと、我々は知りました。恐怖という感情を持つのは仕方がないことかもしれませんが、医学的には半径500m以内に近付いたから感染するというものでは、もちろんなかったですね。
小野寺:そうです。でも、最初は当然、皆さんにとって、コロナはやはり怖かったと思います。どんな病気なのか、うつったらどうなるのか、誰も分からなかったので。なんとかして感染から自分を守ろうとするのは、感情としては正しいでしょう。ただ、だんだんと、実は「それほど怖がるような病気ではないのではないか」ということが、少なくとも医療者はじわじわと分かってきましたよね。それなのに、初めの怖さがずっと、1年以上も続いたことについては、かなり問題があったと思っています。
病院が怖かったのは「ウイルスでなくマスコミの反応」

野路:そういった怖さが続くということに対して、(当時)病院長としてどう対応しましたか?
小野寺:当院も怖くて、患者や家族など一般の方々への情報発信はできませんでした。怖いというのはウイルスではなく、マスコミの反応です。
例えば、当院の感染管理室は早い時期から「感染者の中に重篤化する人は確かにいるが、新型コロナは、エボラ出血熱のような危険性の極めて高い1類感染症と同等の扱いを必要とするほど怖い病気ではない」と認識し始めました。では、我々がマスコミに出て「世の中で怖がられているほど怖い病気ではない。たいしたことはない」と言えるかといえば、言えません。それはとても根性がいることです。
私自身は当時、「未知の感染症」の対策であっても、少しでもスタッフが楽になるようにしたいと思っていました。「未知」だった当初は、どの程度の装備で治療に当たればいいか分からないから、防護服(PPE)を着て対応しますが、だんだん、それほどの装備が必要ではないと分かってくれば、そこまでしなくていいでしょう。
患者が感染症にかかっていようとなかろうと、すべての患者に対して我々は、標準予防策(スタンダードプリコーション)をとっています。標準予防策を基本とすることでよいのではないかと考えるようになってきました。
新型コロナの流行初期に、病院の入り口に額の表面温度を計る体温計を設置しました。少しでも寒ければ、額の表面温度は低くなるに決まっているし、体温が高い人は体が辛いので高いことを自覚しています。微熱があるかどうかを、表面温度で測定できるわけはありません。しかし、そういう「対策」をしていくことがお決まりのような感じで、社会から求められていました。体温測定についてはあまりに馬鹿げているからと、数日で撤去しました。病院として、少しでも余分なところに力を入れることなく、なんとか効率的に医療を回していくことを心掛けました。
2021年の春から当院は先行して、感染者の濃厚接触者となった医療従事者を一律に休ませるのでなく、毎日検査して陰性であることを確認するなど一定の条件の下で勤務してもらう体制を取り入れました。防護服も軽装化して、スタッフの着脱の負担を減らしました。
野路:磯野さんは医療人類学者として、コロナ禍も医療福祉現場のフィールドワークを続けてこられました。静岡市立静岡病院の取り組みをご存知でしたか?
磯野:初めは全く知りませんでした。2022年ごろ、静岡市立静岡病院の感染管理室長岩井一也さんのメディアでの発信に触れ、感染対策以外の全てを犠牲にしてでも対策を優先しようとするのでなく、組織としてその時々で何が重要かを見極めながら、柔軟な対策を行った病院も日本に存在したんだと、大変感銘を受けました。
新型コロナ流行初期は、これはとにかく恐ろしい病気で、とにかく不要不急のことをしてはならない。生活の全般で、感染しないための対策を取るべきだという声が、医療従事者をはじめ、社会の人々の間で圧倒的に大きかったですよね。その中で、いや、バランスをとることが大事だと、医療の側から、しかも第一線の病院の感染管理室長が発信されていたことに、非常に驚きました。
野路:小野寺さん、対策を緩めることでまた感染者が出た、濃厚接触者が出たとなると、病院の立場もないですし、マスコミも追及したと思いますが。
小野寺:実際には、対策を緩めたら感染者が増えるのかということも、初めは全く分からないですよね。辛い話ですが、新型コロナで亡くなった方を、家族に会わせないまま火葬するといったことが行われていました。亡くなった方は息もしていないので、うつらない。家族が会うこと自体は問題ないわけです。それなのに、絶対に顔も見せないという形になっていました。当院は2022年から、他の病気で亡くなった方の遺体と同じように、納体袋に入れずに葬儀社に引き渡すようにしました。葬儀社に説明をしたうえで、です。厚生労働省の遺体取り扱いのガイドラインが改定され、「納体袋に入れなくてもいい」と公言されたのは2023年でした。そのような、普通に考えれば、何もそこまでしなくてもいいだろうということが行われてきました。
野路:各地の各病院の医療者が、もっと「大丈夫です」と言ってくださったら、もう少し、日本全体の感染対策が適正なところでなされたのかなと思いますが、多くの医療者・病院は、そう言えなかったわけですね。この背景はどのように考えていますか?
小野寺:一つはやはり、マスコミにたたかれるのは嫌だということでしょう。病院というのは元々、どちらかといえば権力者に近いと思われているのではないでしょうか。何か弱点があればすぐに責任を追及されます。その中で医療者が声を上げて、「これはおかしいんじゃないか」と言い出すのは、なかなか大変だと思っています。私一人ならいくら責められても構いませんし、感染管理室長も自分一人ならどうということはないのですが、当院で働いている千人余りの職員全体がバッシングを受けるのは避けたい。どの病院も、そういうことは考えていると思います。
医療者は「権力者である」という側面

磯野:医療者からすると、「医療者は権力者だと思われているけど、そうではない」という感覚があると思います。しかし、医療人類学の立場から、臨床現場を見たり、患者にインタビューしたりしていると、やはり医療者は権力を持っているという側面があると思います。例えば、医師の資格があったら 見ず知らずの人の裸を見ることができる。同意を得て手術すらできる。普通の人間関係ではあり得ないことが、医師の資格を媒介すると可能になる。私は、これは大きな権力だと思っています。
患者側から話を聞く機会がありますが、患者は医師にものすごく遠慮しがちです。例えば家族が入院していて、医師に何か改善を求めたり要望したりしたら、入院している家族に何か(よくないことが)起こるのではないかという不安や心配事を抱えていることもあります。
私自身も、小野寺さんがおっしゃったように、コロナ禍の感染対策はちょっとやりすぎた面が多々あったと思います。なので、新聞社のインタビューに、そうした趣旨の発言をします。その記事を自分のSNSで発信すると、必ず医療者から批判が来ます。結構な量の批判がある中で、最も多いのは「お前は現場を知らない」「お前は勉強不足だ」。この二つです。
一方で医療者に聞き取りをすると、本当に理不尽なことで、患者の家族からたたかれたりメディアからたたかれたりして、辛い思いをされています。けれどもまた逆の側面から見ると、医療者は権力を持っていて、権力を持たない人を、「お前は何も知らない」「お前は医者じゃないだろう」と、同じようにたたくという構造があったのかなというのが、私の認識です。
「あまりに目が向けられなかった」生活の現場
野路:長期戦となったコロナ禍を、人類学者の立場からはどう見ていましたか?
磯野:私は情報という観点から、このコロナ禍を見ていました。特に初期の頃は、感染してる人はほとんどいません。ごく少数でした。静岡市立静岡病院の皆さんは実際の患者をみているかもしれないけど、かかった本人でさえ、他にかかった人を見ていない状況で、人々がどうやって「コロナという病気」を知るかというと、情報を得る手段は、文字と写真と映像と音声しかないんです。それで私たちは 「静岡市立静岡病院の半径500m以内に入ったら、コロナがうつってしまう」という印象を得てしまって、それを身体感覚の中に入れ込むんです。だから「病院に近付くと怖い」となって、病院のスタッフが大変理不尽な思いをすることになる。これはつまり、病気を体で学んだのではなく、情報として病気を身につけているということです。
実は、当時私は、医療専門家の方々とは全く違う風景を見ていました。コロナ禍に入った2020年、私は失業者でした。2020年4月からハローワークに行ったんです。すると、ハローワークの開室8時半前から、外にまで行列ができていました。恐らく、アルバイトや派遣、非正規の人が、早くも解雇されていたんです。そしてハローワークの中にも外にも列を作って待っているんですね。2020年5月頃になると「密を作ってはいけない」ということで、椅子が減らされました。でもみんな、自分の番をスキップされないように、立って待っているんです。
メディアはとにかく、医療現場の画を撮りたい。病院のICU(集中治療室)の映像などです。けれど、ハローワークの行列に並んでいる人たちを撮りには、誰も来ない。すごく違和感がありました。病院の外側に、とてつもない影響を及ぼしている病気であるにも関わらず、病気そのもののリスクを出すことにばかり、メディアが集中してしまった。「不要不急」といわれて、「あれはだめだ」「これもだめだ」となった。結果、職を失い、暮らしを奪われた人がいることに、あまりにも目を向けなさすぎなのではないかという観点から、私はコロナ禍を見ていました。
決して、医療関係者が大変ではなかったとか、楽をしていると言いたいわけではないんです。ただ、多くの医療従事者の方は、あまりハローワークには行かないと思います。職業的に保障された医療従事者の立場からは、恐らく見えないだろう生活の現場があります。私はそうした現場、そうした観点から、コロナ禍というのを、医療人類学という学問の力を使って発信したいと考えていました。
野路:新型コロナに感染するかしないか、感染して生きるか死ぬかの“外周”にも、自分の仕事や命に関わるようなことがあったんですよ、という視点ですね。そうした中で、新型コロナが感染症法上の5類になるまで、感染対策が厳しく続いたことについては、磯野さんはどう考えましたか?
磯野:少し引いた目線で見ると、日本の健康をめぐる「パニックの傾向」が再び現れたといえます。とりあえず混乱を沈めるために始めた、一時的であるはずの対策が、何年間にもわたって続いてしまうという傾向です。実はこれまでも、日本では同じようなことが起こっています。
例えば「狂牛病」といわれて恐れられたBSE問題。この問題では、科学的には無意味といわれる牛の全頭検査が約10年続けられました。積極的勧奨の中止期間が長引いたHPV(子宮頸がん)ワクチンの問題も同様です。一時的であるはずの対策が科学的根拠に応じて見直されることなく、年単位でだらだら続いてしまう。不要な対策だと分かってからも、やめられない。小野寺さんがおっしゃったように、遺体を納体袋に包んで死に顔を拝むことすらできないのは、明らかにやりすぎですよね。でもそれが、今回も数年という単位で続いてしまってやめられないという、日本社会の“思考の癖”が、またコロナ禍で現れたなと思っています。
ゼロリスクの追求と責任の回避 政府も専門家も

小野寺:流行初期は、医療者側にとっても情報は少なかったです。新型コロナとはどんな病気だろうかと海外の論文を読むのですが、実際にはなかなか、感染対策を本当にここまで緩めていいのか、もっと厳しくしないといけないのかという情報はほとんどなく、大混乱だったと思います。途中からは、感染症法上の位置付けを「早く5類にしてよ」と、当院から厚生労働省に対しても言えるようになってきましたが、初めのうちは大混乱でした。
専門家の人たちも「100%大丈夫」という根拠がなければ、すでにやっている対策をやめようとは言い出せない。そういうことは、やはりあったと思います。ただ、やめようと言い出せるか言い出せないかを左右する一番大きな要因は、空気ですよね。「対策は当然、やるものだ」という空気が全体にあると、それを変えよう、やめようという話は、なかなかしづらいんだろうと思いますね。
磯野:「100%大丈夫」というのは まずどんなことであっても、あり得ないですよね。一歩外に出て道を歩いたら車にひかれて死ぬ可能性は絶対にゼロにはなりません。「ゼロリスク」を求めることは、医療においてはまずもって無理だと思います。それでもなお、100%大丈夫じゃないから言えない、踏み切れない、というところでしょうか。
小野寺:そうですね。がっちりしたデータがなくて、研究者は皆、推計値を出すわけです。その中でこの「◯%」はリスクとして高いのか低いのかといった話はなかなか難しいですよね。専門家といわれた人たちは「それは政府が決めることでしょう」となったわけですよね。そして政府としても、怖くて「大丈夫」とは言えなかった。突き詰めると、コロナで1人でも死んだらどうするんだという話になるわけで。その責任をとるのは無理だとなると、じゃあこのままだね、というふうになるわけですね。
過度な感染対策で医療が滞る懸念 病院長「責任は私が」
野路:それでも小野寺さんは、感染対策をすることによって出てきた弊害を強くお感じになっていたわけですか?
小野寺:そうですね。実際、それほど症状が重くないコロナの感染者が入院することで、通常の医療ができなくなるという事態になりました。他の患者と隔離しなければならないので、コロナ治療以外の通常の治療に使う病床(ベッド)は少なくなりますし、手術も制限されました。例えばがん患者の手術を延期せざるを得ないということが起きました。そのような形で、コロナ以外の病気で亡くなった方が少し増えたというのは、あったと思います。
そして、そのあたりのバランスをとることは、それぞれの医療機関でやりなさいねと。そういう話になるわけです。かなり厳しい話です。当院は、通常の医療をできるだけたくさんしようということを行ってきました。だから、余分な感染対策はしない。少しでも省力化を図らないと、病院として通常の医療ができないだろうと。そう考えて指揮をしてきたということです。
野路:小野寺さんの方針で、うまくいきましたか?
小野寺:完全にうまくいったのかは分かりませんが、当院としては、できる限り通常の医療を提供するという病院の機能はずっと保てたと思っています。
磯野:未だに完全面会禁止などを続けている病院もある中で、静岡市立静岡病院の取り組みがなぜできたんだろうと思うんです。2020年の後半あたりから少しずつ感染対策を緩められていますよね。病院のスタッフの側にも、いや、そんなことをして、もし感染爆発が起きたら責任をとれるのかという話は必ずあったと思います。組織として緩和ができたのはなぜですか?
小野寺:責任は、私がとればいいわけで。責任をとると言っても、どう責任をとるのかは分かりませんが。道義的責任とかですね、責任の種類はいろいろありますが、どうぞ、責任はとりますよ、というのが私のスタンスです。そして当院のスタッフみんなの中にも、患者さんをとにかくみて、いい治療をするんだという強い覚悟があったことが大きいんだろうと思っています。
当院の感染管理室が、リーズナブルに合理的に、「これぐらいでいいでしょう」という話をした時に、病院長の私も「じゃあそれでいこう」と言って、責任は私がとればいいわけで。そんな形で進めてきたということです。
例えば、患者が家族と面会することは回復に効果的だということは明らかです。家族が病室に出入りすることで、ほんの少し、患者がコロナに感染リスクが上がるかもしれない。しかしそれよりも、面会を禁止することで患者にもたらすダメージの方が上回るだろう。だから家族との面会制限はやめたほうがいいだろうと。また、濃厚接触者という言葉がありましたが、濃厚接触者というのはどんどんたどっていったら、日本国民全員が濃厚接触者になるわけで、いちいち仕事を休んだらどうするんだという話になるでしょう。◯日から◯日まではコロナの感染力があるからと、どんどん規制が長くなっていく。そうすると、医療も回らない、社会も回らないだろう。そういうことは、ある程度バランスをとって、「ここら辺でカット」と、せざるを得ないだろうと思いますね。
医師の考えの違いで生まれた病院ごとの差

磯野:小野寺さんの考えは合理的で腑に落ちるのですが、静岡県の中で最前線で治療に当たっている静岡市立静岡病院が、「こういうふうにしても大丈夫でしたよ」といえば、そのやり方が派生して、東海地方に、全国に広がっていってもおかしくないと思いますが、広がらなかったですよね。なぜでしょうか?
小野寺:やはり、それぞれの医療のスタンスが違うからだと思います。感染管理を担当している医師の中には、「対策を緩和するなんて、絶対にそんなことはしない。この考えは譲れない」という人もいるわけです。例えば防護服一つをとっても「私はこの方法で感染が防げると信じているから、フルで装備しないと無理」と強く主張する人がいると、「ああ、そうか」となるわけです。それを誰かが説得するというのはかなり難しいですね。
静岡市でも静岡県でも、行政・保健所と病院の会議があって、その中で、どこの病院がコロナ患者をどのくらい引き受けるのか、感染対策はどうするんだといった話し合いがされました。それでも他の病院を説得するというのは、かなり難しかったと思いますね。「静岡病院はコロナに対しては最も緩い病院なので」というと、「ああ、先生のところは緩いですね。でも静岡病院に追随しようという根性はない」とおっしゃった病院長もいます。
磯野:根性の問題になっているんですね。
小野寺:多分、根性だと思います。
野路:「腹のくくり方」と言い換えてもいいかもしれませんね。
介護施設「お年寄りの幸せを守る」独自に感染対策緩和も
野路:静岡市立静岡病院のように、ここまでの対策でいいでしょう、それが合理的でしょうというふうに考えた病院や施設を、磯野さんは他にご存知ですか?
磯野:私はコロナ禍に調査をして、『コロナ禍と出会い直す』という本を書きました。調査で、鹿児島県にある「いろ葉」という介護施設を取材したんです。静岡市立静岡病院のように、「いろ葉」も非常に柔軟な感染対策をしていました。対策をガチガチにやってしまうと、お年寄りがコロナに感染するリスクは下がるかもしれないけれど、お年寄りの命、いわゆる人としての命というのを殺してしまう。施設に入ったら誰にも会えない。とにかく部屋に閉じ込めて、おむつにして、となってしまっては、むしろ体は弱るし、認知機能も落ちてしまう。何より人との交流が途絶えることで孤独にしてしまう。これはお年寄りの幸せを守ることではないという信念の下に、非常に柔軟な対策をとられました。
先ほど、小野寺さんが濃厚接触者の話をされました。病院や介護施設で、スタッフが濃厚接触者となって休んでしまい、仕事が止まることがあったと思います。なぜ仕事が止まるかというと、濃厚接触者を休ませてしまうからだと。そうすると、リスクのない人が働くことになる。そして次はまたその人たちが濃厚接触者となって休むことになる。すると濃厚接触者の無限ループが続いてしまう。そして働く人がいなくなる。だから「いろ葉」では、濃厚接触者の人は陽性者とみなして、陽性者として働いてもらうやり方をしたんです。すると、リスクのないスタッフが生まれます。そのスタッフには訪問介護などの外回りをしてもらう。そして陽性になったお年寄りは、陽性になったことのあるスタッフと、濃厚接触者になったスタッフがみるようにしたんです。結果的に、いつこの感染のループが収まるかというのも、ある程度予想がつくので、「あと◯日したら勤務態勢を戻そう」と見通しが立てられます。ループは長くても2週間くらいでいったん収まります。
マスクについても柔軟でした。マスクを着けたスタッフが近付くと、「お前は結核なのか」と言い出す方がいたそうです。結核が流行した時代を生きた方でしょう。マスクを着けた顔は、誰が誰だか分からないので、お年寄りが怖がって大声を上げてしまうこともあったそうです。耳が遠い方も多いので、スタッフはお年寄りの耳元で「◯◯さん」と大声で話しかける。すると、いくらスタッフがマスクをしていても、マスクの脇から息が漏れるのでマスクを着けている意味がない。そうした試行錯誤の中で、この場面ではスタッフがマスクを外した方がいいよね、こういう時は注意しようという形で、柔軟に対応しながら、少しずつバランスをとっていった。そんな介護施設もあったんです。
私は「いろ葉」を何度か訪問しましたが、コロナ禍とは思えないくらい、お年寄りもスタッフも、皆さん本当に幸せそうに暮らしていらっしゃいました。もちろん、お年寄りは家族にも会えるんです。しかし「いろ葉」の近くには、一度入ったらもう誰にも会えませんという介護施設も、やはりあるんです。その、施設ごとのギャップがすごかったですね。「いろ葉」では1回、クラスター(集団感染)が発生しました。その時だけは、完全に面会を止めて、デイサービスの利用者の受け入れもやめました。「◯日頃には開所できるので、それまでは家でみてください」と言えば、家族も自宅での介護を頑張れるんですよね。
小野寺:介護施設で多分、一番難しかったのは家族への対応だと思います。そんなふうに対策を緩めて、もしうちのおじいちゃんおばあちゃんがコロナに感染したらどうしてくれるんだと、家族から追及されたらどうしようと。みんな、ハリネズミのようになって、自分の組織、施設を守ろうとしていましたから。その点が、介護施設にとっては大変だったのではないかなと思います。実際には「そんなことは起こらない」ということも、「起きたらどうしよう」と怖がって、多くの施設が、「いろ葉」のように踏み切れなかったのだと思います。
磯野:確かに、最初の半年、または1年ぐらいは(怖がって緩和に踏み切れないのは)仕方がないと思います。しかしそれを、3年、4年と続けてしまう。今でも続けている病院や施設があります。それは、やはり一つの病院、一つの施設のみならず、日本社会の大きな問題点で、コロナ禍に限ったことではないんですよね。この点が、小野寺さんのおっしゃるような、「根性」という話に集約されてしまって、小野寺さんのような、非常に特殊な考え方の人にしかできない対応策だった、特殊な病院にしかできない、特殊な事例だった、という理解がなされがちです。そうなってしまうと、静岡市立静岡病院や「いろ葉」がされた非常に重要な対応策が未来に広がっていかないと思います。
小野寺:確かに、なぜもっと強く周りの病院に言わなかったんだ、働きかけなかったんだという批判はあり得るだろうと思います。
磯野:言ってもだめでしたよね、きっと。
患者と家族を面会させない理由は「ない」

小野寺:他の病院のことを、「お前の病院は」というふうには、なかなか言えないですよね。面会制限も、面会する人が無症状で、患者が感染症に対して特にリスクが高くなければ、「面会させない」理由は本当はないんですよね。しかも、入院している人は、お年寄りがほとんどです。お年寄りは、家族に会うことができなければ、病院にいてもどんどん弱ってしまいます。家族が会うことは非常に大切なことなので、それができない病院は、療養の環境としては非常にレベルが低いということになります。だから、それはなんとかしたいという思いは、コロナの流行当初からありました。
野路:静岡市立静岡病院では、面会の制限はないのですか?
小野寺:ありません。面会する人を家族に限っていた時期はありました。最近は患者さんが皆さん元気で、面会時間が長く、にぎやかになって苦情が出てきたので、30分間ぐらいにしてもらおうかという話もあったのですが、今も制限はしていません。一方で、いわゆる儀礼的なお見舞いは控えてもらっています。会社の上司が入院しているから、顔を出しておこうかなというケースです。これは、コロナ禍に“便乗”した形で、控えてもらうようにしました。
野路:マスクの着用についてはどうですか?
小野寺:マスクの着用を広く呼びかけることは、していません。「せきチケット」はやはり大切だと思っていますから、ゴホゴホしながら来られるならマスクはしてもらわないといけないと思います。手洗いもした方がいいです。しかし、普通の状況では、院内でマスクをする必要はないと考えています。
日本の組織「話し合いを避け ルールを増やし 張り紙だらけ」
磯野:「ハリネズミ」のようになってしまうとか、面会で羽目を外しすぎる方がいて「30分にしようとした」といった話を伺って、何か個別の問題が起きた時に、その人に対して「やめてください」ということが非常に言いづらい社会だと思いました。個別のクレーム処理が苦手なんですね。日本社会が全体的に抱える問題といえると思います。
とにかく事を荒立てたくない。個別の干渉はしたくない。だから個別の問題が起こると、全体のガバナンスの問題にまで事を広げ、張り紙をしたり、ルールを増やすなどして、全体に向けての発信を行う。別の個別の問題が起きたら、全体に対してさらにルールを増やして、それを張り紙で掲示する。一方で、ルールを減らすことはできません。「何かあったらどうするんだ」といわれると、足がすくんでしまうからです。こうしてルールだらけ、張り紙だらけの組織が出来上がります。
話し合いが大切といわれますが、話し合える社会にしていくのであれば、何か問題が起きた時に、きちんとその問題に対して議論し、調整をするべきだと思います。問題が起こるたびにルールを厳しくし続ける姿勢からは、議論は生まれません。コロナ禍の過度な感染対策は、そのような状態がずっと続いてしまった結果ではないでしょうか。
小野寺:そうですね。人と直接ぶつかりたくないというのは、よく分かります。初めから先回りをして、後から文句を言われても大丈夫なようにしておこうということですね。難しいでしょうが、人とぶつかることを怖がらないようにというのは、していくべきなのかもしれません。
磯野:医療者にインタビューすると、理不尽なことで病院が責められて、和解金を何百万円払ったといったことをしばしば聞きます。訴訟に発展するようなもめ事の時に、「こういうことは起こってしまうことなんです」などと交渉すること自体が、個人の道徳感や胆力があるかないかの問題ではなく、慣習的に非常に難しい社会なんだろうなと思いますね。
小野寺:医療訴訟は理不尽な事柄もありますが、自分が被害を受けたと思っている方にしてみれば、それは非常に怒りなどがあるわけで、そこを理解はした方がいいと思います。ただ、医療者にとっては、リスクを説明した上でまともな治療をしたのに、体にダメージが起きたと訴えられたら、説明をしていくしかないですね。
磯野:こういう話がありました。入院していて、ある程度回復した高齢者が、1日外泊をして、自宅で団子を食べた。すると団子を喉に詰まらせて亡くなってしまった。こんなことになったのは外泊をさせた病院の責任だと、家族が激怒して、結果的に病院が慰謝料を払うことになったと。めったにない事例かもしれませんが、そのようなことが一つでもあると、医療側としては構えてしまいますよね。入院患者が家族と外出する時に、外出先で食事をして、病院に帰って来た時に何か問題が起きると困るから、とにかく食事は病院で取ってくださいと。そのようなルールを設けている病院があると、最近聞きました。
「気の緩み」のせいにした反省を
野路:コロナ禍の行き過ぎた感染対策などを反省点として、教訓として生かしていくためには、何が必要でしょうか?
小野寺:今回の行き過ぎた対策の弊害は、実はまだ残っているわけです。例えば、子どもの成長を考える時に、一日中ずっとマスクをしていて、友達はできたのかな。大学もリモートで講義して、学生の身についたのかな。そういった社会に対するダメージは続いていて、これからかなり影響が現れてくるのではないかという気がします。
磯野:教育現場という観点からいうと、コロナ禍以前とコロナ禍後の、学生の講義の受け方が変化したと思います。学生がメモを取らないんです。ノートも開かない学生が一定数、出てくるようになりました。リモート講義では、学生はずっと画面を見ていて、録画も残るので、リアルタイムで聞いていなくても後で巻き戻せばいいから、というわけです。メモを取らない学生に私は衝撃を受けました。やはり体を動かすことで身につくものはあると思っていますが、それすらしない学生が出てきたなと。
そして、次のパンデミックに生かしたい今回の問題点は、感染が拡大すると、メディアを通じて必ず「気の緩みのせいで感染拡大した」といわれたことです。コロナは流行の波があって、おそらくインフルエンザのように周期的に訪れるものだと思います。それを我々の“自覚”の問題であると言いすぎないことは、私は非常に重要だと思います。「気の緩んだ国民」と「現場で必死に闘っている医療者」という対立構造が生まれたことで、病院のオペレーションがうまく機能せず、医療が逼迫しているという問題の本質に目が向きにくくなり、結果的に対応が遅れたと思います。いつまでも保健所が濃厚接触者を追い続けるなど、感染対策を過剰にしてしまった結果、現場が大変になるということもありました。それを、「気の緩み」のせいとか「自覚のない人」のせいにしてしまうと、そこにある具体的な問題点が見えなくなります。「気の緩み」を持ち出す報道は、次回は控えてほしいです。
小野寺:国内で最初にコロナの感染が始まった頃は、コロナにかかった人は「極悪非道の大悪人」だという風潮がありましたね。「あの人は東京に行ったからコロナにかかった。帰ってくるな」という話が出てきたわけです。最初から感染を封じ込めることは不可能だったのに、それでも「かかった人は悪い人」「帰省した人は悪い人」「他県のナンバーの車で走るな」。実際に石を投げられたりして、「私は◯◯県民です」と車にステッカーを張ったりする動きもありました。日本人の特性だから、という見方もあるかもしれませんが、次にパンデミックが起きたときにはマスコミなどが、「前の新型コロナの時にはこんなことがありましたが、こういうことはしないように」と、それこそコロナ禍に起きたことを振り返る機会を作っていただいて、ヒステリーにならないようにしていただきたいと思います。
野路:もちろん、感染対策は皆さん、真面目な気持ちで取り組んできたことですが、通り過ぎてみると、真面目にやっても「これはやりすぎたな」と思えることはいくつもあるのではないでしょうか。そこを冷静に受け止めて、教訓として、心に留めておきたいですよね。
<2人の略歴>
小野寺知哉(おのでら・ともや)
京都大医学部循環器内科臨床教授。循環器専門医。総合内科専門医。京都大医学部卒。同大医学研究科修了。米国シンシナチ大客員研究員などを経て1990年から静岡市立静岡病院勤務。2019年から病院長。23年から理事長兼務。25年4月から理事長専任
磯野真穂(いその・まほ)
東京科学大(旧 東京医科歯科大・東京工業大)リベラルアーツ研究教育院教授。早稲田大卒。オレゴン州立大大学院などで学び博士号(文学)取得。応用人類学研究所・ANTHRO所長。著書に『コロナ禍と出会い直す』『他者と生きる』など
(2025年3月21日にYouTubeチャンネル「SBSnews6」で配信した『面会制限やマスク…過度な感染対策いち早くやめた 静岡市立静岡病院長が医療人類学者とこの5年を振り返る』を基に追加取材して一部加筆、再編集しました)



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る