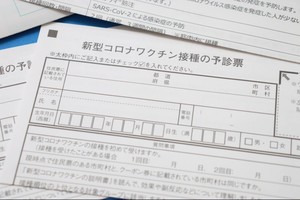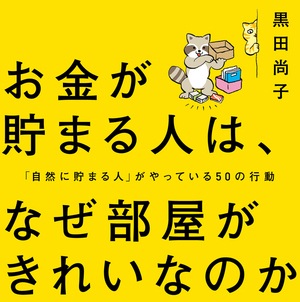なくならない、日本のスポーツ界でのパワハラ問題……
先日、サッカーJ1サガン鳥栖の福岡社長が、金明輝監督によるパワーハラスメント行為の告発文書が日本サッカー協会に届いた件に関し、ホームページ上で謝罪するというニュースがありました。この他にも、J2東京ヴェルディの永井秀樹前監督が選手を指導する際、パワハラと受け止められる行為があったとして、選手会がJリーグに意見書を提出していたという報道もあるなど、スポーツ界でのパワハラが問題となっています。そこで、自身も元プロ野球選手と活躍され、現在は人材育成にも携わってらっしゃる小島圭市さんに、スポーツ界のパワハラ問題についてお話しをうかがいました。
牧野アナ:小島さんは、1986年にプロ野球の読売巨人軍に入団後、アメリカのマイナーリーグ、中日ドラゴンズ、台湾プロ野球と各国を渡り、2000年よりMLBのスカウトに転身。プロ選手、アマチュア選手のスカウティングを担当され、アジア全域の責任者として活躍し、斎藤隆投手や黒田博樹投手の獲得にも関わられました。その後はビジネス業界に転身され、現在は、メンタル面から人や組織の育成、コンサルティングなどを行っているC3.Japan合同会社の代表を務められています。
パワハラといえば、数年前にも日大アメフト部やレスリング代表チームなどいろいろありましたが、再びこのようなパワハラ問題の報道が多くなっています。なぜ、日本のスポーツ界でパワハラ行為が繰り返されているのでしょうか?
小島さん:確かに最近また報道が目立つようになってきましたが、これは決して単純な話ではなく、複数の要因があって出てきていると思います。文化的背景、環境要因があるとしても、指導者のレベルに問題があるのではないかと考えています。
牧野アナ:私は40代なんですが、昔は根性主義で育てられてきました。自分自身がパワハラを受けてきたという年代の指導者も今、多いですよね。指導者への教育の面で足りない点があるのでしょうか?
小島さん:我々が訴えているのは、一般企業でいうと中間管理職、スポーツ界でいうと監督・コーチへのコーチングです。その方々がちゃんとした指導を受けてから、若い選手や部下に指導していくというような流れを作らないと、同じことが繰り返されると思いますし、牧野さんが言われた通り、「自分たちも殴られてきたんだ」というような話が今後も続いていくのではないかと思います。
牧野アナ:指導者だけではなく、まわりの人が声を上げやすい環境というのも大事かなと思うのですが、この辺りは、日本の文化的になかなか難しいのでしょうか?
小島さん:日本は素晴らしい文化を持った国ですが、それを悪用というかいい方向に使われていないなという気がするんです。例えば特に年配の人の間では、年齢がひとつでも上だと偉いなど、縦社会が根強く続いています。学閥ですとか、地域閥などに囚われていたりしていて、相互理解をしようという意識が薄いですよね。
牧野アナ:上の人が間違っていたとしても、下の人が声を上げにくいという日本社会。小島さんはアメリカや台湾のチームにも在籍されていましたが、日本と海外で、指導方法や雰囲気などに違いはありましたか?
小島さん:アメリカや台湾では明確に違うと思います。現在の詳しい制度などについてはわかりませんが、アメリカではパワハラなどのハラスメントに関しては、明確なペナルティが設けられています。中学生や高校生でもそうですが、パワハラ行為が認められた場合、これは「事件」なわけです。ですので、その地域の委員会が出てきて調査を行い、場合によっては指導者は解雇されたり、指導自粛というペナルティを受けたりします。ペナルティの中でもこれは重いなと思ったのが、指導しているチームのグラウンドに3km以内近づいてはいけないといったものも。アメリカでは犯罪という認識なので、犯罪者に対するような措置を取っています。
「コミュニケーション能力」と「支える」という意識
牧野アナ:今後、日本のスポーツ界でもパワハラ行為をなくしていくためには、その辺の明確なペナルティが必要となってくるのか、どのようにお考えですか?小島さん:日本では非常に馴染まないと思うのですが、一定のペナルティ制度を作ることはかなり有効ですし、パワハラに対しての抑止力になると思います。またライセンス制度というと、免許を取らないと指導できないなど、ハードルが高いと感じますが、セミナーなどを開催して、指導者は年間に10時間以上受けてください、というように指導者たちも発散、議論できる場所を設けてあげるといいと思います。
牧野アナ:その中で意識が高まっていくという部分がありますね。ご覧くださっている方々にもスポーツチームでコーチをされている方や管理職の方も多くいらっしゃるかと思います。私たちが指導をするときに、これから意識すべきポイントやパワハラをしてしまうことのないように気を付けた方がいいことはありますか?
小島さん:まずは、「指導者は偉い」と思わないことですね。何のために指導、コーチングをしているのか。いろいろわかっていない人のためにいるわけで、「俺はわかっているぞ」と披露する場ではありません。見下すような感じではなく、目線を下げて選手だったり部下だったり、指導される側の人たちと同じ目線、もしくはそれより低いところから支えるという意識でコミュニケーションをとるようにしていく。みなさんも昔は指導される時期があり、若い時に暴力などで教わってきたことが、今はもうダメなわけですから。いかにコミュニケーション能力を活用して支えるかという意識を持つことが重要だと思います。
牧野アナ:指導者と選手の関係は、上下関係というよりは最高のパフォーマンスを出すためのパートナーというような!
小島さん:パートナーという意識は非常にいいと思います。
牧野アナ:小島さんは今もこういった場で指導されたりもするのでしょうか?
小島さん:アメリカでは一般社会だけでなくスポーツ界にも心理学というのが非常に浸透しています。私も四日市大学スポーツ心理学の若山教授と一緒に、精神面からアスリートを支えていくいう活動を広げたいと思っています。
牧野アナ:その際に大事なポイントは、これまでお話しいただいた以外にもありますか?
小島さん:重複してしましますが、やはりコミュニケーションですね。絶対に上から見ないようにしていますし、本当にパートナーという意識の中で支えるという、コミュニケーションの大切さを日頃から感じています。
牧野アナ:特に私を含めた40代や50代はその辺りの考え方を変えていく必要があるのかなと思いました。
今回お話をうかがったのは……小島圭市さん
川崎市出身。高校卒業後、プロ野球選手となり、読売巨人軍、アメリカ、中日ドラゴンズ、台湾でプレー。現役引退後にスポーツマネージメント会社を経て、MLBロサンゼルス・ドジャースのアジア担当スカウト、アリゾナダイヤモンドバックス顧問を歴任の後、C3.Japan合同会社を設立、代表に就任。現在プロフェッショナルコーチング&コンサルタントとして活躍中。



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る