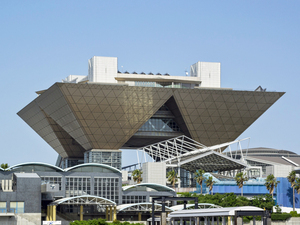(高松)自動車メーカー、スズキの鈴木修さんのお別れの会が、4月8日と14日に、都内と、本社のある浜松市でそれぞれ行われました。
(高松)自動車メーカー、スズキの鈴木修さんのお別れの会が、4月8日と14日に、都内と、本社のある浜松市でそれぞれ行われました。(山田)亡くなったのが、去年の年末でしたね。
(高松)それぞれ2000人くらいの方が参列されました。昭和の頃ならともかく、令和の今、経営者のお別れの会が大規模に行われるというのはかなり珍しいと思いました。政財界トップの方々はもちろん、浜松の会場は、一般の方が数多く来ていたのが印象的でした。こういう庶民的なところが「修さんらしいな」と思いました。
(高松)鈴木修さんについて、どういう印象をお持ちですか。
(山田)お会いしたことはないですが、静岡県政と浜松市政に結構関わっている重要な人物っていうイメージがあります。
(高松)そうですね。浜松市の12市町村合併後、行財政改革推進審議会(行革審)という、民間ベースの長期の会合が行われた際、その会長をしていました。その時は大なたを振るって、市政のいろいろな課題について「もっとコストカットできるんじゃないか」と提言を重ねていました。政治の世界への影響は非常に大きかったですね。経営者としては1978年に社長に就任し、2021年の会長退任まで40年以上にわたってスズキを率いて世界的なメーカーに育てました。
トランプ大統領の関税の件や最近の国内の物価高もあって、日本のものづくりは厳しい局面にある中、こういう昭和、平成を渡ってきた経営者を通して、「日本のものづくりはどのようにあるべきか」について考えられたらと思います。
オリジナリティへの徹底したこだわり
 (高松)鈴木修さんに関して言うと、私は2019年から22年までスズキの担当記者だったこともあり、お話をする機会がたくさんありました。
(高松)鈴木修さんに関して言うと、私は2019年から22年までスズキの担当記者だったこともあり、お話をする機会がたくさんありました。(山田)直接お話しされたんですね。
(高松)当時は現役で、さまざまな話を伺いました。修さんというと、「独創性」と「交渉力」、「チャレンジ精神」の三つが挙げられます。
本当に、オリジナリティにこだわる人でした。要するに、二番煎じじゃ嫌だと。会社の中の人やいろんな企業経営者に対して、例えば「どこの市場でもいいから一番になりなさい」と伝えていました。
あとは一般の人、昭和の言葉で言うと「大衆」が何を欲しいのかをよく観察し、「それを形にするために、徹底的に努力しなさい」とも話していましたね。
1979年にアルトという車を当時なかった全国統一価格の47万円で発売し、大ヒットさせました。乗りやすい安い車を作った結果として、セカンドカーという需要を生み、また、女性が乗れる車という市場も生み出したと言われています。
ワゴンRやスイフトなどいろんな車がありますが、鈴木修さんは一貫して、一部の限られた人が乗るというよりは、地域に住んでいる大勢の人、例えば農作業する人にも使ってもらえて、「下駄代わり」に気軽に乗れて、しかも安くて機能性が高くデザイン性もちゃんとある、というような車を目指していました。
(山田)最近ジムニーとかも人気ですね。なぜ、スズキっていろんな自動車会社の中で、軽自動車メインの会社なんですか。
(高松)スズキは、一番最初に作ったスズライトという車に始まり、軽自動車というカテゴリーを切り開いてきた会社でもあります。大きな車ももちろん必要なんですが、やはり、スズキという会社と鈴木修さんという人は、小回りが利いて、農村など全国の地方で気軽に乗れる車というところにすごくこだわっていました。
(山田)だから、軽自動車なんだ。
(高松)小さな車にこだわり、コストダウンを徹底的にやってきたことが結果として、大きな車しか作っていない海外から見るとすごい競争力になったんですよね。差別化戦略というか、海外のメーカーには、小さな車をコンパクトに安く作れるスズキのものづくりは、非常に斬新に映りました。
(山田)そうなんですね。
(高松)スズキはアメリカや中国ではなく、インドやハンガリーに展開していった会社なんですが、その展開先の国や地域も、海外メーカーの「右に倣え」になっていないんです。新しい地域に行くというところにも非常に独創性があり、特異な存在感の会社になっています。それは偶然ではなくて、戦略的にやってるんですけども。
世界のトップと渡り合う交渉力
 (高松)「交渉力」に関連して、インドになぜ進出できたのかの話になります。1980年代初頭にインドの交渉団が来日して、日本のメーカーが来てくれないかなと交渉先を探していました。その時、鈴木修さんが、他の自動車メーカーが手を付ける前に「自分がすぐに会う」と言って交渉団といち早く交渉をまとめ、すぐインド進出を決めるという力技を見せたんです。今のように経済成長する前の時代のインドです。今もインドではスズキが自動車メーカーの中でシェアトップなんですが、その理由には、他のメーカーが目をつけてないところにいち早く行ったからというのもありますよね。
(高松)「交渉力」に関連して、インドになぜ進出できたのかの話になります。1980年代初頭にインドの交渉団が来日して、日本のメーカーが来てくれないかなと交渉先を探していました。その時、鈴木修さんが、他の自動車メーカーが手を付ける前に「自分がすぐに会う」と言って交渉団といち早く交渉をまとめ、すぐインド進出を決めるという力技を見せたんです。今のように経済成長する前の時代のインドです。今もインドではスズキが自動車メーカーの中でシェアトップなんですが、その理由には、他のメーカーが目をつけてないところにいち早く行ったからというのもありますよね。(山田)多分他のメーカーだったら、だんだんと話がトップに行くっていう流れもあるじゃないですか。でもいきなり修さんが直接交渉するんですね。
(高松)他にも、ドイツのフォルクスワーゲンや、アメリカのゼネラル・モーターズといった大企業と、提携するかしないかというような交渉に取り組みました。修さんは岐阜出身の純粋な日本人。そういう人が、世界の自動車メーカーのトップ中のトップである、社長や会長と渡り合ってきたんです。
聞き上手の人
(山田)直接鈴木修さんと話していたとき、何か印象深かったことあります?(高松)ビジネスの現場ではもちろん非常に厳しい人だと思いますが、取材ベースでは、すごく柔らかい感じの人でしたね。印象としては非常に聞き上手の人でした。人の話を聞くタイミングや呼吸みたいなものが、僕が今まで人生で会った中で一番かなと感じています。
あと、すごくよく人を見てるんですよね。何百人、何千人と会っていると思いますが、相手の個人データを全部覚えてしまうという能力がありました。目の前にいる人の名前はもちろん、個人情報がいろいろ頭に入っていて、その人に会った時に、いろいろな話を当意即妙にするんです。
(山田)すごい。
(高松)そんなに頻繁に会わないはずの人の家族構成なども覚えていて、そういうのがポンポン出てくるんですね。「若いときはもっとすごかった」ってみんな言うんですが、コミュニケーションの能力は突出していたと思います。
引き継がれるチャレンジ精神
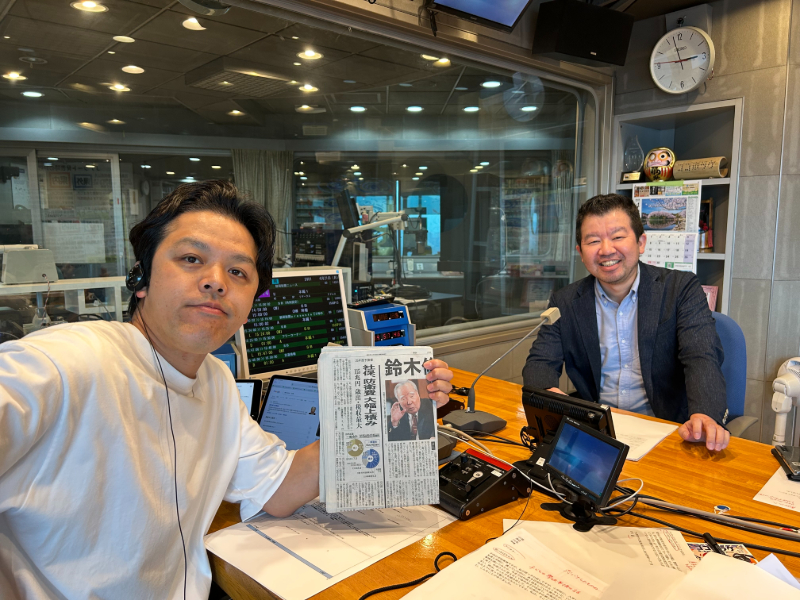 (高松)今のスズキは、鈴木俊宏社長が率いています。修さんの時は昭和、平成の時代でトップダウンの会社だったので、それが良くも悪くもっていうところも当然あったと思います。今は「チーム経営」に移行し、経営として新たな時代のスズキになってきていると言えます。
(高松)今のスズキは、鈴木俊宏社長が率いています。修さんの時は昭和、平成の時代でトップダウンの会社だったので、それが良くも悪くもっていうところも当然あったと思います。今は「チーム経営」に移行し、経営として新たな時代のスズキになってきていると言えます。今日この話をした理由の一つに、日本のものづくりについて考えたいということがあります。日本は今、アニメなどソフトコンテンツにおいては世界で高い影響力を持っていますが、一方で、ハードの分野ではなかなかヒット商品が出ない状況にあります。鈴木修さんの時代には国内で数多くのメーカーが割拠し、一世代前の時代の経営者の方々から話を聞くにつけて、高度成長期の日本は、良くも悪くも家族主義でものづくりに全力投球する時代であり、「人々の生活を豊かにしよう」という情熱や「世界市場に飛びだそう」というチャレンジ精神があったと感じます。
非常にハングリー精神の強いものづくり企業がたくさんあり、それが成長力のエンジンになったと思うんです。そうしたものづくりに対する熱量を、鈴木修さんも本当に最後までものすごくギラギラと持っていたのが印象に残っています。
(山田)彼がやってきたことからは、受け継ぐことがたくさんあるわけですね。
(高松)鈴木修さんは非常に強烈な人だったので、社員さんなどに聞くといろんな意見があるんですが、この人の持っているチャレンジ精神は、人の心に火をつけるようなところがありました。「やる気」という言葉がすごく好きで、よくサインなどに書いていました。とにかくその「挑戦しろ」「あきらめるな」というのは、僕もすごく、取材のときに言われました。
その精神は今の会社にも引き継がれていると思います。今、アメリカと中国という大きな流れの中で、日本のものづくりが生き残れるかどうかの過渡期になっています。世界的にソフトの時代になっているけれども、やっぱり重厚長大産業も大事で、きちんとものを作っていくということを今の若い人たちに受け継いでいってほしいと思います。こういったカリスマ的な経営者の時代と、令和の時代っていうのがフィットするとも思いませんし、今の時代には今の経営のあり方があると思うんですが、そういうものづくりの精神は残してほしいですね。
昭和の時代のように「日本メーカー」という枠で捉えるのはちょっと古い感覚なのかもしれませんが、やはり日本のメーカーならではの繊細さや、機能性とデザインを兼ね備えていることなど、きめ細かなものづくりが生む良さがあり、海外の人たちと違う視点でものが作れるというところは絶対あると思うんです。今の厳しい時代の中でも、中小企業も含めて、ものづくりの現場には奮起してほしいなと、強く思っています。
(山田)思いを感じました。今日の勉強はこれでおしまい!



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る