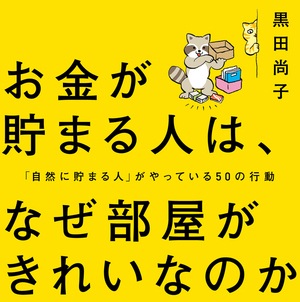高校で投資を学ぶ!?
2022年4月から高校の新しい学習指導要領が実施され、高校生が金融教育の授業を受けるようになったといいます。今回は、「高校生が学ぶ金融教育」について、経済ジャーナリストの堀浩司さんに、SBSアナウンサー牧野克彦がお話をうかがいました。
牧野:高校生が金融について学ぶ時代なんですね。どのような授業なんですか?
堀:4月から初めて金融や経済に関する教育が始まったというわけではありません。以前から高校では、公民の中の政治経済という科目で基本的なお金の仕組みを、家庭科では基本的な家計の収支管理の考え方について学んでいたんです。今回の改定された新学習指導要領では、科目としては家庭科になります。生涯を見通した家計の経済計画を立てるために、資産形成の視点から、株式や債券、投資信託などの基本的な金融の知識を学ぶことになったんです。
この4月から成人年齢が18歳に引き下げられて、親などの同意がなくてもクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができることになりました。今回の改定は、お金に関するトラブルに巻き込まれないためにも基本的な金融知識を身につけてもらおうという背景もあるのです。
海外の金融教育は?
牧野:なるほど。家庭科の先生は守備範囲が広くなって大変だけど頑張ってほしいなと思う一方で、ヨーロッパを見ると金融教育が日本より相当進んでいるのですか?イギリス
堀:一番進んでるのはイギリスと言われています。ちゃんと金融教育のカリキュラムがあって、例えば小学校の入学前からお買い物などお金を使う場面を学んだりします。学年が進むごとにクレジットカードやデビットカードあるいは投資などについても学び、年数をかけてしっかりお金の知識を増やしていくのです。アメリカ
アメリカでは、学習内容は地域や学校の裁量に任されていて、統一的なカリキュラムはないのですが、『アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書』という本が日本語訳で出版されています。中身を見ると、お金の計画の話から貯金・保険・投資の話、借金や金融詐欺の話まで、本当に社会に出て役に立つ一生もののお金の基礎知識を学ぶという内容になっています。牧野:今、キャッシュレスの時代になってきて、お金が目に見えないところでどんどん移動していく時代じゃないですか。ますますお金に関するイメージをしっかり持てるようにしないと駄目ですよね。
堀:基礎知識は大事だと思います。
牧野:今後の日本の金融教育は、どういう内容になっていくのでしょうか?
堀:高校の家庭科での金融教育は、授業内容については各高校の裁量に任されていて、授業時間は残念ながら年間1〜4時間のところが多いのです。
牧野:ちょっとだけなんですね。
金融庁の参考教材「金融経済教育指導教材」
堀:金融庁は3月17日に参考教材として、全7章からなる高校向けの「金融経済教育指導教材」を発表しています。第1章「家計管理とライフプランニング」
堀:将来やりたいことのために、どうお金を準備するか考え、一生涯の収入と支出のバランスを取ることを考える。これは本当に将来のために必要なことだと思います。第2章「使う」
堀:必要なものと欲しいものとを区別する。これは、自分でもちゃんとやっているかな?と思います。牧野:大人も学びたいですよね。
堀:それから先ほどおっしゃっていたように、今はキャッシュレスの時代なので、その使い方ですね。どんな種類のキャッシュレスがあるか大人もあまりわかっていないので、使い分けということでも大事ですよね。
第3章「備える」
堀:社会保険や民間保険について学ぶ。みなさん、自分に関わるけれど難しいと思っていますよね。第4章「貯める増やす」
堀:まずは家計管理をしっかり行って貯蓄をすること。その上で国債や社債、それから株式、投資信託の特徴を知って、自分に合った資産形成を行って将来に向けての準備をしましょうということになっています。牧野:今の国の方針も、国が保証するのではなく、みなさん個人個人が投資して増やしていってくださいよという時代になってきてますよね。
堀:貯蓄から投資へと叫ばれています。そして残りは、第5章「借りる」第6章「金融トラブル」第7章「まとめ」となっています。
牧野:これを教えるのは学校の先生になるのですか?
堀:そうですね。今年1月に日本トレンドリサーチというところが、高校で実施する金融教育を誰が教えたらいいか、アンケート調査を実施しています。本来は家庭科の科目なのですが、家庭科の先生と答えたのは実は3.4%。家庭科の先生の荷が重すぎるということなんでしょう。やはり一番多かったのは、外部の講師で6割近く。続いて3割が社会科の先生だったんです。実際、高校の先生方も初めて教える内容ばかりで戸惑っていると思うのですが、やはり当面は外部の専門家が講師として教えることになるでしょうね。
牧野:外部の講師を連れて来られるような体制にしていった方がいいですよね?
堀:もちろん基本は学校の先生ですが、「経済のことを肌で感じている方がその場で話をする」といったようにゲストも必要だと思います。
今後の課題
牧野:今後、高校生が金融を学んでいくにあたっての課題は、どのように考えていらっしゃいますか?堀:まずメリットとしては、親の同意がなくてもいろいろな契約ができてしまう成人年齢(18歳)の直前に金融教育を受けられることです。デメリットとしては、お金の話=金儲けの話と短絡的に受け取られる危惧があって、このあたりも気をつけないといけないですね。
また、高校生に限らずお金のことについて学ぶことは大切なことです。しかし、高校の授業では他に勉強することがあるので、残念ながら限られた少しの時間しか学ぶことができません。なので、イギリスのように小さい頃から少しずつ大切なお金について学べるシステムを、これから作り上げていくということが今後の課題だと思います。
牧野:高校生が学んでいたら「うちの子もちゃんとやってるな。じゃあ自分も」と学ぶ大人が増えてくると思うのです。
堀:教材を見て「こうだったか!」ということがあるかもしれないので、大人も基礎知識を学ぶことは大切だと思います。
牧野:今回、事前に堀さんから教えてもらった金融庁の金融ガイド「基礎から学べる金融ガイド」が同庁のホームページに出ていますが、これがかなり充実しています。みなさんにも役に立つと思いますので、基礎から金融のことを学んでみたいなという方は、一度、金融庁のホームページを見てもらうのもいいですよね。
堀:そうですね。カラフルで非常に上手くまとめています。中高生対象ですが、大人が読んでも本当に役立つと思います。ですので、この機会に私たち大人もお金の基礎知識を学んでいきたいですね。
牧野:みんなで金融を学んでいきましょう! どうもありがとうございました。
今回お話をうかがったのは……堀浩司さん
経済学は私たちの暮らしが良くなるためにある学問、私たちみんながわかる経済のお話を講演、ラジオ、テレビ、大学教員、執筆で。アルバイトをしていたラジオ局で学生時代に音楽番組のパーソナリティを務めて以来、その出演歴は40年! 大学常任理事として大学経営にも、税理士として企業経営指導にも携わる。



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る