堆積物と水質調査

駿府城の堀を眺めていると、「緑色に見える堀の水は汚れているのだろうか」と疑問に思うことがある。そんな中、2021年から2022年に早稲田大学教授の山田和芳(かずよし)さんと、静岡大成中学校・高等学校の生徒により堀の堆積物と水質の調査が行われたと聞いたので、その詳細を教えていただくことにした。
元々、ふじのくに地球環境史ミュージアムに勤務していたという山田さん。町の中心地で歴史と文化を感じることのできる駿府城公園が好きだと言う。しかし、市民の方と話しをする中で、堀の水が濁っていて汚いというイメージがあることを知ったそうだ。
「透き通るような透明な水場だけがきれいな環境ではありません。駿府城堀はとてもきれいな環境で、世界に誇ることのできる景観であることを多くの方に知ってほしい」と話す。そのことを科学的に証明するために、今回の調査を行ったそうだ。

堆積物調査の様子
堆積物の調査は、中堀の東側で水底から32㎝の堆積物(コア)を採取し、それを分析。このコアに含まれるプランクトンや花粉の化石などを調べることで、過去の周辺環境の変化がわかるという。結果、1972年の堀底の工事以降、周辺の植生は安定して維持されてきたことがわかった。
水質調査の様子
そして水質調査は、中堀と外堀の十数ヶ所で大成学校の生徒が中心となり実施。夏から翌春にかけて定期的に水質の調査を行った結果、河川水の環境基準と照らし合わせて、水質汚濁が起きていないことが確認できたそうだ。外堀は安倍川の伏流水が自噴している場所もあり、きれいな水が入ってきているため中堀より良い結果だったと考えられるという。駿府ホリノテラス付近などでは、濁度が水道水の基準を達成している時期もあったそうだ。
「若草色に見えるのは植物性プランクトンの影響で、閉鎖的な環境でこれらが少ない透明な水だと一面をハスが覆う環境になり、秋に枯れた際に腐敗臭が生じてしまう。また、生活排水が流入し水中の栄養が多くなると、毒素を持つアオコの発生やヘドロの堆積が促進されるなど、生き物の環境として良くなくなってしまいます。そう考えると、駿府城堀の水は、自然と調和している都市の水環境としては理想形です。水面に近づいてみるとアメンボや小魚などを見ることができます。今後、ビオトープなどの活用も面白いですね。昭和40年代に地下水の過剰くみ上げによって堀の水が枯渇しました。そのとき多くの市民から貯水の要望が出て、水がある空間を守るために不透水工事をした経緯があります。駿府城のお堀は、静岡の方々がずっと守ってきた場所です。これからも、世界に誇ることのできるこの水のある景色を残していってほしいです」と山田さんは話してくれた。
今まで、透明でないことで水の状態が悪いような気がしていたが、環境によってはやや緑色に見える状態の方が良いと知れたのは驚きだった。これから堀の周辺を歩きながら眺めるときは、違った目線で見ることができそうだ。

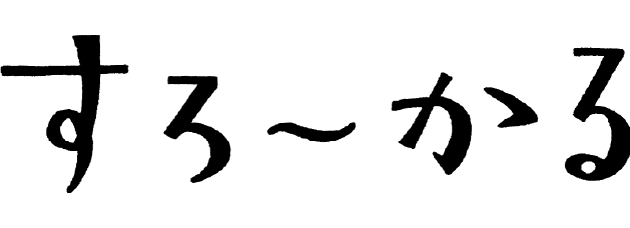

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































