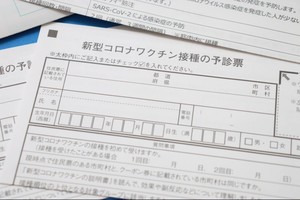(山田)今日は選択的夫婦別姓制度についてです。この前の参院選でも、ここを強く推している党と、そうでもない党がありましたね。
(山田)今日は選択的夫婦別姓制度についてです。この前の参院選でも、ここを強く推している党と、そうでもない党がありましたね。(山本)そうですね。参院選挙の街頭演説などを全て見たわけではないんですが、今回の選挙の中ではあまりこの話が出てこなかったなっていう印象を受けました。
(山田)やっぱり、経済政策や消費税ってところがメインだったのでね。でも強く押しているところもありました。
(山本)逆にはっきりと反対の姿勢を示している政党もあり、議論は分かれる話です。改めて、選択的夫婦別姓制度について話したいと思います。
夫婦同姓を定めているのは日本だけ
(山本)現在の制度は夫婦同姓です。男女が結婚する時に、同じ名字を名乗らなければいけないということで、男女どちらかが姓を変える、つまり改姓をしなければいけないという制度になっています。世界各国もそうなのかなと思っていたら、実は、法律でそう定めているのは、世界中で日本だけだそうです。
(山田)日本だけ?そうなんですね。
(山本)いろいろ文化の違いがあり、両方の名字をくっつけてミドルネームのような形を取るところもあれば、別姓で、個人についた親から受け継いだものを名乗り続けるというようなところもあります。
日本は今は夫婦同姓。現状、結婚したときに姓を変えるのは95%は女性の方なんですね。
(山田)旦那さんの方の姓に変えてるってことですね。僕は5%の方だ。妻の名字に変えてますから。
(山本)そうなんですか。
(山田)山田っていうのは僕の旧姓でそのまま通称として世間で使ってます。僕は運転免許証にも旧姓を載せています。
(山本)当然、男性で女性側の名字に変えるという方もいますが、圧倒的多数の夫婦は、結婚のタイミングで女性が改姓しています。私の周囲の職場の同僚女性も、結婚したタイミングで夫の姓になった人ばかりですね。でも、職場では旧姓のまま仕事をしている人が多く、私も旧姓で呼ぶことが多いです。
特に新聞記者の場合は、外に行って取材して知り合いも増えていきますが、名字が完全に変わってしまうと、せっかくできた人脈が保たれるのか、心配があります。ちょっと混乱をきたす部分がビジネス上あったりするわけですよね。
(山田)結婚してご主人の姓に変えたけれど、離婚をされて、そのままそのご主人の姓を仕事上使ってるって方もいますよね。
(山本)仕事上、その方がトラブルがなく進むということでしょうね。
明治時代にできた民法に定められている
 (山田)なぜこういうことになっているかというと、今は民法の規定で夫婦同姓が定められています。民法自体は明治時代の1898年につくられました。当時は戸主が強い権限を持つ「家制度」というものがあり、「家」というものが一つの単位として個人よりも重んじられていました。「どこどこの家に属する○○さん」っていうような考え方だったので、家単位でいろんなことが決められていたということです。
(山田)なぜこういうことになっているかというと、今は民法の規定で夫婦同姓が定められています。民法自体は明治時代の1898年につくられました。当時は戸主が強い権限を持つ「家制度」というものがあり、「家」というものが一つの単位として個人よりも重んじられていました。「どこどこの家に属する○○さん」っていうような考え方だったので、家単位でいろんなことが決められていたということです。当時は欧米などでも、夫婦は同じ姓にするという規定があったりしたようですが、今はないということです。日本の場合は戦後に新しい憲法ができ、「家」よりもあくまで個人に主権がある時代になりました。ただ、戸籍や夫婦同姓といった制度だけは残ったままずっと来ているんですね。
選択的夫婦別姓の場合は、同じ名字にしても、同じ家庭の男女が別々の姓を名乗ってもよく、別姓か同姓か、どちらかを個人が選べるという形です。私が学生だったのは30年前ぐらいですが、当時から議論がありました。
(山田)だから今回の選挙でも、「いつまでこれを言ってるんだ」っていう意見も出てきたのは何かで見ましたけどもね。
(山本)そうです。30年間何も進んでないなと改めて思ったんですが、ちょっとさかのぼると、1985年に日本が女性差別撤廃条約という国際条約を批准したタイミングがあるんですね。
制度上男女は同権と言われていますが、どうしても女性差別やジェンダーギャップがあるということで、条約に従って国の制度などを作っていくことになりました。
当時から、民法の規定はおかしいんじゃないかと言われていました。女性の社会進出を考え、女性が我慢を強いられずに別姓も選択できるようにすべきだということの議論はその辺りから本格的に始まり、およそ30年前の1996年に、実は一度政府が法案を作って、国会で提出したことがあるんですね。
ただ、その時点では議論がそれほど深まらず、法律としては成立しないでそのまま先送りになってきました。その後も何度か盛り上がった時があり、その間「選択的夫婦別姓制度を取り入れるべきだ」っていうような声はずっと根強くあったんです。
自民党政権の時代、それから民主党政権の時代にそれぞれ法案が検討されましたが、国会で俎上に載ることはなかったんですね。
一方、2024年6月には、企業トップなどでつくる経団連が、「女性が社会で活躍している間に名字が変わることでいろんな不利益を得ているので、別姓を選べるようにすべきだ」というような提言をしたんです。
その後、24年の9月に自民党の総裁選がありました。岸田首相が辞任し、次の総理大臣を選ぶということで、いろんな候補者が出て、その時には議論が盛り上がったなという印象があります。候補によって言うことが違って、今の首相の石破さんは割と賛成の立場で当時は話していました。明確に反対を唱える候補もいました。
石破さんが総理大臣に選ばれて、衆議院選挙が24年の秋にありました。このときも各党の公約などで政党がそれぞれ違っていましたね。野党の立憲民主党と国民民主党、日本維新の会は、それぞれ夫婦別姓に関連する別の法案を提出して、今年6月までが会期だった通常国会の中で、衆議院の法務委員会で審議をされるところまでいきました。
実に28年ぶりに国会審議の場で議論されることになったんですが、6月の国会の会期内には間に合わず、秋の臨時国会で継続して審議する形になりました。棚上げになった状態で参議院選挙を迎えたという形です。今年の参議院選挙では党によって主張が違いました。
(山田)参政党さんは反対でしたね。
(山本)立憲民主党とか国民民主党の2党は選択的夫婦別姓制度を取り入れるべきだという考えを前提とした民法改正案を出しています。
「自分の名前が変わる」ことへの不安も
 (山田)「僕自身は結婚してから名字が変わって仕事もその名字でやってますが、何ら支障は感じません」「これって習慣の問題なのに、制度に落とし込もうとするから混乱するのでは」など、リスナーの皆さんからはたくさん反応をいただいています。この問題はどう落とし込んでいかなきゃいけないんでしょうか?
(山田)「僕自身は結婚してから名字が変わって仕事もその名字でやってますが、何ら支障は感じません」「これって習慣の問題なのに、制度に落とし込もうとするから混乱するのでは」など、リスナーの皆さんからはたくさん反応をいただいています。この問題はどう落とし込んでいかなきゃいけないんでしょうか?(山本)確かに長年の慣習といいますか、明治時代から150年近く日本の場合は今のやり方でやってきたので、「それが当たり前でその方が自然だ」と思っている方も確かにいると思います。
でも、逆に「どうしてもやっぱり変えたくない」とか「自分の名前というのは自分を象徴するもので、結婚というタイミングでその上の半分が変わってしまうということにどうしても耐えられない」などと考える方も中にはいます。姓を変えるのは95%が女性なので、そう考える方の多くは女性のようです。
今回の参議院選挙に当たって、そうした思いを発信している方に、同僚の記者が取材をしました。
富士宮市出身の落語家の露の団姫(つゆの・まるこ)さんは、結婚した時に新しい姓が「自分のものとは思えない」という思いに駆られたそうで、さらに「自分が侵食されていくような気がする」という言葉で表現していましたね。
あちこちで自分の名前を呼ばれたりするときに、「それは私じゃない」っていうふうに言いたかったということです。ご主人の姓になったのがすごく嫌だというわけではなかったが、結婚してしばらく経つ間に、「それって私なのか」っていう思いが出てきたそうで、「ペーパー離婚」をして事実婚を選んだ方です。仲良く一緒に暮らしていますが、一旦結婚したのを離婚するほどに思い悩んだそうです。
(山田)その「自分のものと思えない」っていう気持ちは、何となくわからないことないんですよね。病院などで呼ばれたときに新しい姓を呼ばれると「俺か…」と。ただ一方、それもわからないことないと思った上で、僕個人の意見だと、「好きな人の名字になる」っていうことの特別感もあるなと思いますけどね。
(山本)事実婚というのは届出をした場合の婚姻に比べて相続などで制限される部分があります。「元の姓でいたい」という権利がなぜ侵害されなければいけないのか、ということを話していました。特に女性の場合は、「元の姓でいたい」ということを言うとなぜかすごく叩かれてしまう。露のさんは芸能人でもあるので、いわれのない中傷を受けたこともあって、「これはいろんな女性が受けている社会的な抑圧を象徴してるんじゃないか」という意見を持っていました。
導入には賛否両方の声が
(山本)最近の若い人の感覚だと、賛否両論は当然あるものの、感覚的には「選択的夫婦別姓制度を導入してもいいんじゃないか」と賛成している人が多いのではないでしょうか。通信社の世論調査でも、そのような結果が出ています。晩婚化や少子化が言われていますが、そうしたことの要因にもなってるんじゃないかと指摘する方もいます。逆に「導入すべきでない」と考える理由にもなっていて、配慮しなければいけないのは、子供が生まれたときに、子供の姓をどうするかどうかっていうところですね。
昔のように家を主体として考えるならば、そこにお嫁さんが来たときにその人が違う名字だとすると、その方が孤立してしまうんじゃないかというような意見もあります。
そういう例が実際あるのかは分かりませんが、子供がきょうだいで違う名字になるのかとか、親と子の名字が違うときに混乱するんじゃないかとか、そういった声があります。
(山田)それはあるかもしれない。例えば結婚して相手の両親と一緒に住むってなったときに自分の名字を変えないことにした場合、「あんたは名字が違うから」っていうような嫌な悪口はありそうな気もします。これは本当に、個人によりますけどね。
(山本)いろんなパターンはそれぞれ家庭によってありますが、ただ、「同性にしなければいけない」という制度で縛るのはどうなのかと思います。また、一方では結婚を機に姓を変えることによって、苦しみを覚える人も確実にいるんだということは、皆さんに分かっていただきたいですね。
(山田)山本さん、静岡新聞でもぜひ取り上げて、いろんな人の意見を載せていただきたいなと思います。今日の勉強はこれでおしまい!



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る