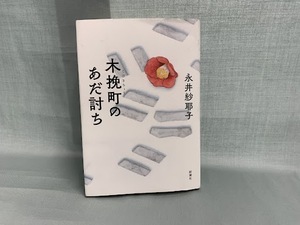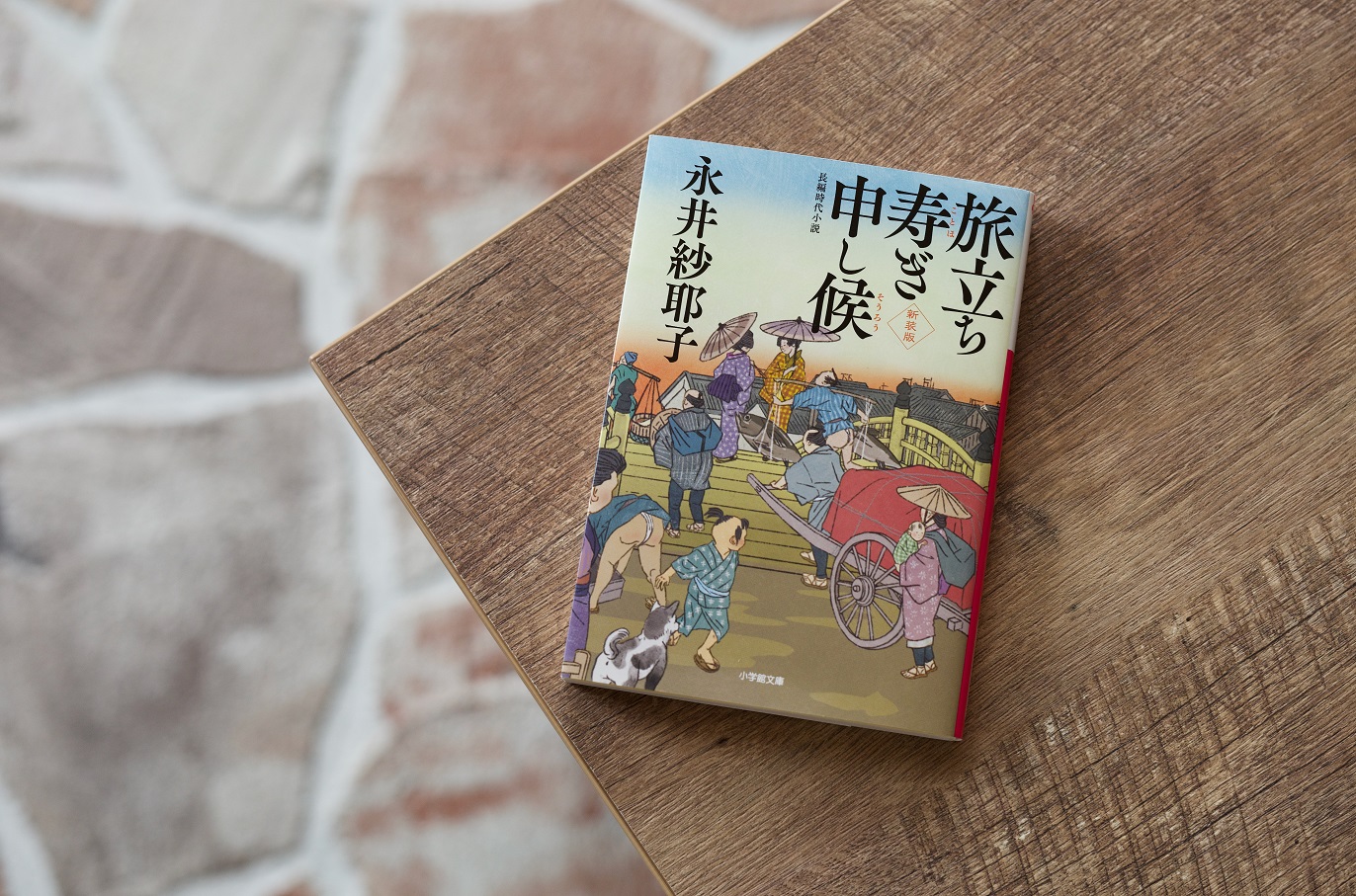
2012年に書き下ろしの単行本として世に出た今作は、2016年3月に「福を届けよ 日本橋紙問屋商い心得」と改題し小学館文庫に入った。今回は再度の文庫発売で、タイトルは原作から取っている。文庫版解説で文芸評論家細谷正充さんが指摘しているように、同一の出版社でタイトルが元に戻るのは珍しい。
幕末、江戸・日本橋で紙問屋を営む若旦那が自分なりの「商人道」を見定めるまでの成長譚。大老井伊直弼が暗殺される安政7(1860)年の「桜田門外の変」で激しく幕を開ける本作だが、物語の視点は徹頭徹尾商人の生活空間に置いている。
開国から維新にかけての激動の時期に、江戸を愛し、近隣を愛した商人たちはどう商売を成り立たせてきたのか。多くの歴史小説で強調される「武士の誇り」に匹敵する「商人の誇り」が、あちこちから噴出する。アクションあり、謎解きあり、意外な恋愛の成就あり、幕末期の歴史のおさらいあり。エンターテインメントの要素をあれこれ詰め込んだ佳作である。
あらすじは次の通り。日本橋本石町の紙問屋「永岡屋」で手代(店員)から若旦那に昇格した勘七は、小諸藩の大きな仕事を受注するが、思わぬ裏切りにあって莫大な借金を背負ってしまう。先代善五郎は病に倒れ、店の存亡は経験に乏しい勘七の双肩にかかる。悪いことは重なり、第14代将軍徳川家茂の長州征伐に合わせ、上納金の支払いを求められる。誠実信義の人である勘七は、いかに店を立て直すのか。
勘七の3人の朋友、永岡屋をはじめとする各商店の番頭や手代、恋仲になるとある女性、腹に一物秘めた武士や浪人たち。人物造形の妙は、永井さんの職人芸的腕前を感じさせる。
異色の経済小説としても読める。例えば「飲食店経営」「月刊食堂」「ファッション販売」といった、個人店向けの専門誌に掲載されていてもおかしくないのではないか。
作中で近江商人が説く「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」は、CSR(企業の社会的責任)そのもの。物価高による生活水準の低下や、今の銀行に近い「札差」のビジネスモデルも語られる。永岡屋はずっと藩や寺社の「御用」に支えられてきたが、需要減にともなって町人向けの小売りに力を入れる。ニーズに即した業態転換である。
極めつけは墨筆硯問屋「松嶋屋」のヒット商品開発のくだり。「看板商品」の筆について若女将がこう言う。「女ものの筆ですが、敢えて持ち手を赤にしたところ、花柳界で話題になりましてね」。今で言うならインフルエンサーの上手な活用例と言ったところか。
同じ店で扱う赤と黒の市松模様の矢立。勘七は一つ五百文と聞き、その高値に驚く。若女将は、傍らに置いた「田之助好み」と書いた紙を見せる。人気の女形が使っている、というアピールだ。実際は使っていないらしい。だが「田之助贔屓の女客、田之助にあやかってもてたい男客。いずれも買っていくのですから、今、当家を支える屋台骨ですよ」と頓着ない。
著名タレントを使った投資詐欺が問題視される今、本人の了解を得ないまま「広告塔」のように名前を使うことは御法度であることは間違いない。だが、江戸の昔からこうしたことを考える人は確実にいたのである。
(は)



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る