語り:春風亭昇太

徳川家康の側室で、西郷局とも呼ばれた、お愛の方の菩提寺である宝台院。
27歳の頃から家康に仕えたというお愛の方は、三方が原の戦いや、小牧長久手の戦いなど、苦難の時代にあった家康を支え、家康の三男で、のちの2代将軍となる秀忠、四男で、尾張の領主となった忠吉の母となりました。名実ともに東海一の実力者となった家康と共に天正14年、1586年駿府城に入りましたが、苦労が重なったのか、天正17年、1589年、38歳という若さで短い生涯を終えました。その遺骸は、当時、龍泉寺(りゅうせんじ)と呼ばれていたこの寺に葬られました。
将軍となった翌年、慶長9年、1604年に家康は現在の葵区柚木にあった龍泉寺を駿府城に近い紺屋町に移し、30石の寺領と自ら描いた家康像、そして、父、松平広忠から譲られた太刀を寄進して、お愛の方の17回忌の法要を営みました。家康の死後、2代将軍秀忠が、母、お愛の方のために、現在の地に大伽藍を建てて、盛大な法要を営み、その際に付けられたお愛の方の戒名から、この寺が宝台院と呼ばれるようになったと言われています。
宝台院のご本尊は、白本尊と呼ばれる阿弥陀如来立像。江戸、芝の増上寺に祀られた黒本尊と共に、家康の守り本尊と伝えられています。江戸幕府が倒れ、明治の世になると、15代将軍であった徳川慶喜がここ宝台院に蟄居し、渋沢栄一と慶喜との再会の場として、宝台院の名は歴史に刻まれることとなりました。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

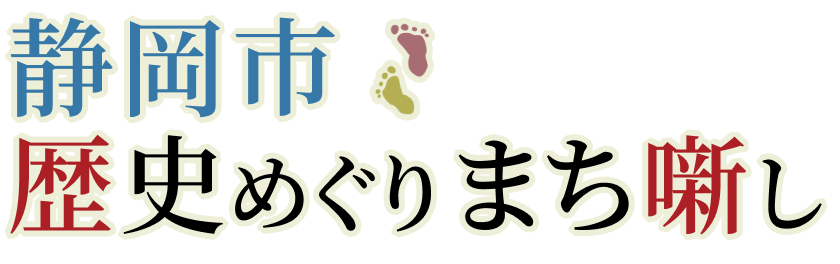

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































