
江戸時代から続く茶商の町「茶町」。この辺りに安倍・足久保のお茶を商う人々が集められたのがそのはじまりとされています。明治時代に、この地域は「お茶の町」として大きく発展しました。
静岡で生産されたお茶は、横浜の港から輸出されていましたが、明治39年に清水港からのお茶の輸出が開始され、茶町周辺に輸出用のお茶を仕上げる工場が増加しました。やがて清水港は日本一の日本茶輸出港となり、大正6年には、全国の茶の輸出高の77%を占めていました。戦後、清水港からの輸出量は減りましたが、茶町の北番町に静岡茶市場が開設され、茶業にかかわる様々な人々によって、お茶の町は発展してきました。
茶取引の仲介役である「才取」は、産地の問屋からお茶の見本を預かり、茶町の問屋にあっせんすることを仕事としており、より早く問屋にたどり着いた才取が取引の交渉権を得られることになっていました。そのため、新茶の季節を迎える初夏には、われ先にと茶問屋街に向けて静岡駅から自転車で疾走する才取たちの姿が、1960年代までの静岡のまちの風物詩でした。
「才取」にとって、自転車は大事な商売道具。当時、才取の自転車を整備していたであろう古くからの自転車屋が、茶町には残っています。そして、今でも毎年、新茶の季節になれば、この町はお茶の香りに包まれています。
静岡市歴史めぐり まち噺し 今日のお噺しはこれにて。

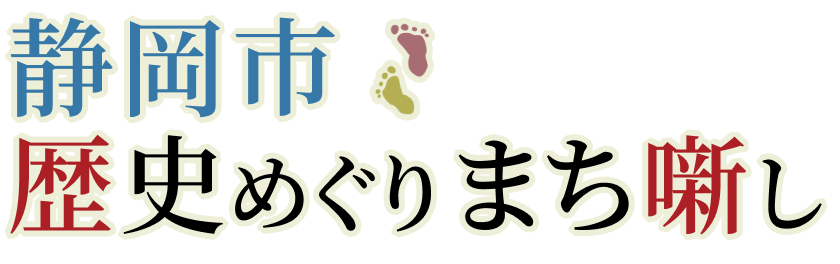

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































