コロナ禍の配信ライブも

14人編成のパスカルズが新型コロナウイルス禍の真っただ中に行った2021年4月の無観客配信ライブ、2022年4月の観客ありのライブを中心に映像を組み立てた。全編で15曲が聴ける。
伊勢監督:僕の初めての劇場公開映画が1995年の「奈緒ちゃん」。パスカルズも同じ1995年結成なんですね。「奈緒ちゃん」は同じ世代の音楽関係者がずいぶん見に来てくれて。(シンガー・ソングライターの)友部正人もその一人で。それからずっと付き合いが続いています。パスカルズは友部のバックバンドをやっていた。まるでボブ・ディランとザ・バンドみたいに。面白いなとずっと思っていました。
今回の映画は息子がきっかけなんですよ。映像の仕事をしているんですが、パスカルズに関心があって、彼らのライブドキュメントを自主製作でつくったりもしていた。そんな彼から話が来たんですよ。しりあがり寿さん(静岡市出身)の「新春! (有)さるハゲロックフェスティバル」の映像を撮影してくれないかと。それが最初です
チェリスト三木黄太さんに捧ぐ

映画はライブの模様を丁寧に追う。パスカルズは2020年4月にチェリストの三木黄太さんが死去したばかり。映像には鎮魂のムードが漂う。
伊勢監督:パスカルズは1999年からは、ずっと同じメンバーでやってきた。だから、メンバーみんな、三木さんがいなくなったことに対してのショックが大きくて。
僕も一緒に(映画製作を)やっていたクルーを何人か亡くしているから、共感があった。(よく知っている人が)いなくなってしまうということへの思いがよく分かった。
じゃあ、配信のライブをやって三木さんのために残そうかという話になった。三木さんのパートをほかのメンバーがそれぞれカバーするみたいな形で。
映画は自然な成り行きで「いまここにいないメンバー」である三木さんを強く意識させる内容になった
伊勢監督:(パスカルズのメンバー)坂本(弘道)さんやリーダーの(ロケット・)マツさんは、三木さんの音が体の中に入り込んじゃっているから代わりはいないんだというようなことを言っていた。
それで三木さんが暮らしていた(長野県)伊那市に行ったんですよ。彼が家具職人としての仕事場にしていた工房を見てこようと。それが2022年の秋。
チェロっていう楽器は、もちろん木でできているし、森から生まれてきた楽器みたいなところがある。そんなことを考えながら森を散策しながら撮影していたら、やっぱり三木さんは三木さんだなと気が付きました。
三木さんにもほかの13人のメンバーの音が体に入っていて、そんな三木さんが森で木を探したり作曲したりしたんだ。だから、単なるパーソナルな物語じゃなくて、そういうことを背景に持ったライブドキュメントを映画として見せることが必要だと思いました。
「不在の音」が聴けるのは映画だけ

これまで20本以上のドキュメンタリー映画を手がけた伊勢監督だが、音楽を素材にするのは2004年の「朋あり、太鼓奏者・林英哲」以来。音楽に関する映像が巷にあふれる今、パスカルズを扱った今作を映画として世に問う意味は何か。
伊勢監督:音楽のライブドキュメントはDVDや配信が圧倒的に多い。でも、今回のように「いないけどいる」ということを伝えられるのは映画という仕組みだけでしょう。暗い中で映像を見て、10人で見ても100人で見ても、画面と向き合っているのは一人ひとり。それぞれが画面と向き合って、いろんなことを想像できる。「不在の音」が聴こえてくる。それができるのは映画しかない。
音楽を扱っても、ドキュメンタリーの骨格は崩していないという。
伊勢監督:映画って見る人のものだからね。見る人がどれだけ想像力をもって見られるか。それがあって初めて映画が映画として成立するんです。
テレビ番組とかミュージック・ビデオはある種の「情報」。もちろん、お金をかけて面白いものになっている場合もある。でも、見る人の中に絵が浮かんできたり、見る人の中に物語が浮かんだりする機会を奪い取ってしまってはいないかな。
映画というのは「おれには分かったぞ」という思いが湧く。もっと言うと自分ごとになっていく。その道筋をつくるのが僕らの役割なんです。
時代の空気感も感じてほしい

社会の空気、時代の息遣いが入り込む余地を意識する。
伊勢監督:(ザ・バンドを描いた)「ラスト・ワルツ」は、そういう空気みたいなものが写っているから、(見た人の)自分の映画のようになっていく。
この映画はパスカルズを撮っているけど、その間に新型コロナが蔓延して、ウクライナにロシアが侵攻した。パスカルズのメンバーの発言にそういうものが出ている。マツさんも珍しく戦争について言及している。やっぱりその時間を写しとっているんだと思います。

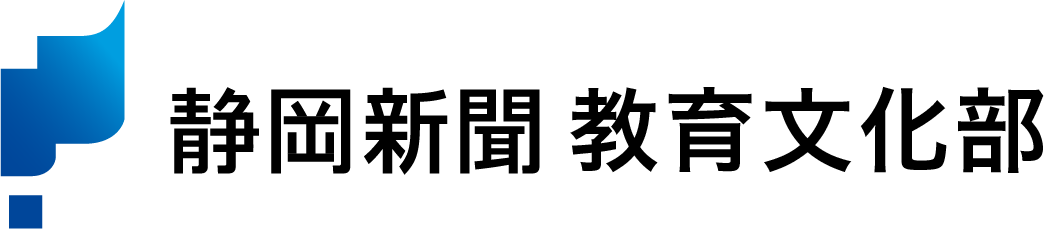

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る

































































